「冥王来訪」の感想一覧
| 良い点 / 悪い点 / コメント |
|---|
|
>もしかして、囚人懲罰大隊ですか?シュトラフバト 第一次世界大戦ではドイツ帝国のStormtroopersのことであります。囚人懲罰大隊のことではありません。 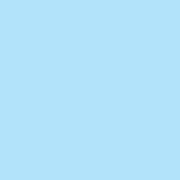
作者からの返信
2025年 05月 23日 13時 35分 プロイセンの影響を受けたとされる日本軍ですが、第一次大戦以降もフランスの軍事ドクトリンの影響は強く残っていました。 日本陸軍の編成は歩兵中隊に軽機関銃を中心にした編成で、これは第一次大戦後の仏軍の模倣でした。 機関銃も、チェコのZB26に影響を受けた96式軽機関銃が出るまで、仏製のホチキス空冷機関銃をライセンス生産したものが主力でした。 |
|
自動車化歩兵は突撃大隊と遂行して縦深作戦の基礎になるますが? 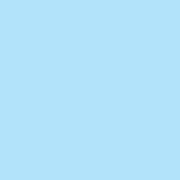
作者からの返信
2025年 05月 23日 12時 07分 もしかして、囚人懲罰大隊ですか?シュトラフバト。Штрафбат。 ロシアでは帝政時代以前から囚人兵の活用が一般的で、その事は既に外国まで伝わっていました。 フランスで出されたジュール・ベルヌの冒険小説、『皇帝の密使』(原題:”Michel Strogoff ”)では、タタール人の反乱軍に対して、政治犯からなる特別囚人部隊を結成して、イルクーツクの防衛戦に部隊を投入する場面が描かれています。 ソ連軍は1919年の時点ですでに懲罰大隊を組織していました。 ソ連の場合、特異なのは囚人部隊が平時の軍事編成でも存在し続けたことです。 1942年7月28日の命令第227号で、囚人部隊が正式に組織されたことにはなっていますが、それ以前から囚人部隊は戦争に投入されていました。 ロシアの研究者によると少なくとも427,910人の囚人が従軍し、このうち170,298人が戦死傷による損失を受けたそうです。 (別な資料だと97万5千人の囚人がグラーグより軍に移送されたとの記述があります。 実数はもっと多いでしょう) 通常の部隊の3倍から6倍の損失を受けたとの研究結果もあります。 懲罰大隊に女性はおらず、女性兵士は懲罰を受けるために後方に移送されたそうです。 また医師や衛生兵はおらず、負傷者が出ると医療大隊や近隣部隊から衛生兵や看護婦が派遣されたそうです。 また刑事犯が中心で、政治犯はごくまれに囚人部隊に入ったそうです。 政治犯を経て、囚人部隊勤務をし、ソ連邦英雄になった人物も少なからずいます。 >自動車化歩兵は突撃大隊と遂行して縦深作戦の基礎になるますが? ウクライナ戦争に関して言えば、ロシア軍は人命の犠牲をいとわない突撃大隊を組織して、小規模な波状攻撃を繰り返す戦術に変更したようですね。 ソ連型の砲兵火力で敵の陣地を徹底的に破壊した上で、装甲車両が主体の「自動車化部隊」が突っ込んでいく戦術は、将校や正規兵の損失の多さから頻度が減ったそうです。 |
|
>自分の妻と息子と疎遠でした これはソビエト連邦共産党の純粋さの象徴です。例えば、党に忠実なゴルバチョフはブレジネフの義理の息子も汚職の容疑で逮捕することを命令します。 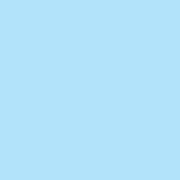
作者からの返信
2025年 05月 21日 12時 59分 1980年代以降にソ連が力を入れた禁酒運動、反アルコール運動は、アンドロポフの遺産と言っても過言ではありません。 (フルシチョフ時代、ブレジネフ時代にも禁酒運動は行われましたが、禁酒令が出されただけという形骸的なもので、ことごとく失敗しています) この当時、モスクワにあった酒蔵は1500から150まで強制的に減らされ、昼間のみの営業に限定されました。 最新の酒造設備も破壊され、酩酊者と思しき人間は片っ端から逮捕され、刑事罰を受けたと言います。 しかし、財政悪化を改善する目的でソ連は酒類の販売を緩和しました。 (革命後もソ連では、1925年まで公式には酒の販売は禁止されており、闇で酒の製造がおこなわれていました) >KGBは政治闘争のためにソビエト体制や彼らの横領することを無視しました。 KGB第三総局、通称特別部では、ソ連軍および実力部隊への浸透工作および監視が行われていました。 工作員をリクルートする際に、スカウトする人物の犯罪を把握し、脅迫を伴って工作員に誘致していました。 汚職などは見逃されたり、泳がすなどをして、場合によっては免罪事件によって、そういった人員をKGBがスカウトしていました。 創作では暴力を伴う形でスカウトする場面がありますが、大部分は巧妙に説得して、協力者にしたそうです。 |
|
>小生はそう単純ではないと思っています 雄渾さんが言った通りです。KGB幹部たちは詩を朗読して楽しんでいたフランス貴族というよりもフランス革命時のテクノクラートに近いです。 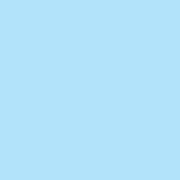
作者からの返信
2025年 05月 21日 11時 48分 理由は東ローマ帝国(今日のトルコ)、イスラム諸王朝からの圧迫を受けていたからです。 軍事力が脆弱だったキエフ・ルーシは、生き残るためにペルシャや東ローマへの間諜を繰り返している内に、自然とこの方面に関して能力が付いた面があります。 あとはタタールの軛で、蒙古の、騎馬民族の諜報活動のノウハウを吸収したのも大きいでしょう。 諜報人材の高官への採用は、少なくともピョートル一世の時代には始まっており、19世紀のアレクサンドル1世の時代には諜報工作員から首相格になった人物もいるほどでした。 ソ連の場合は、政権成立時より諜報員の育成と確保に力を入れており、創成期には旧体制派の人間や貴族なども人員として受け入れました。 ある程度人材が育ったのを見て、スターリンは人員の一新を図るべく、大粛清をエジョフに命じました。 これにより、軍や官僚を中心に20台から30代の人材に官僚機構が一新され、ソ連の頭脳部はリフレッシュされた面があります。 ここで入れ替わった人材は後のフルシチョフ、ブレジネフ、アンドロポフ、チェルネンコの時代まで、ソ連をリードする人材になりました。 ただ、そういった人材は、ゴルバチョフのグラスノスチまで再度の人員入れ替えが起こらなかったので、ソ連は長い老人の時代と言われる停滞期に入ることになりました。 |
|
>旧時代の道徳観 それは問題ではありません。なぜなら、雄渾さんはル・カレの小説『スマイリーと仲間たち』で、カーラが自分の信念のために自分の娘を諦めることができないシーンを読んだと分かります。 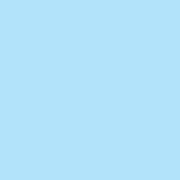
作者からの返信
2025年 05月 20日 14時 06分 話が難しすぎるかな、説明が不足していないか、自分の中だけで理解したつもりになっていないかと、悩んでおりました。 >スマイリーと仲間たち BBCで、TVドラマ化してたそうですね。 これは寡聞にして存じませんでした。 |
|
>これより、反革命分子を処断する。部隊は前へ KGB幹部たちの運命はソビエトにおける様々な民族から兵士たちによって《銀河英雄伝説》でのゴールデンバウム貴族たちと同じようにリンチされているのでしょう。 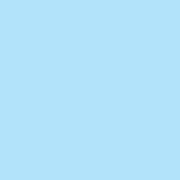
作者からの返信
2025年 05月 20日 13時 57分 KGBの部員の多くは人相も本名も不明ですから、素知らぬ顔をして新生ロシアの経済界や産業界で働く辣腕ビジネスマンとして、仕立ての良い西側風の背広を着て、米露や欧露の間を行き来していると想像しております。 それに人は弱いですから、(敗戦したドイツがNSDAPと武装親衛隊に責任を押し付けて開き直ったように)大物政治家にのみ責任を押し付けて、自分は被害者という立場をとるでしょう。 ロシア人は他責志向が強い民族ですから、それぐらいは平然とするでしょう。 |
|
>ご海容いただければ幸いです。 いや、雄渾さんの書き方はソビエト政権の偽善を浮き彫りにしていると思います。どれだけ共産主義について語り、計画経済を実施しても、人間の本性における腐敗や人類として本性を変えることはできません。(面白いことはKGBが逃亡を試みた国営企業の従業員とその家族を止めるため、「ソビエト市民なら、銃を取って日本帝国主義者と戦うべきではないのかね」と言って従業員たちを射殺しますが、ソビエト指導部にアターエフの横領や研究を告発する人々にもこのKGBの幹部たちであります。そう、KGBは政治闘争のためにソビエト体制や彼らの横領することを無視しました。 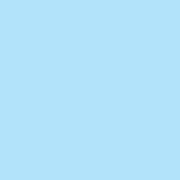
作者からの返信
2025年 05月 20日 13時 51分 >そう、KGBは政治闘争のためにソビエト体制や彼らの横領することを無視しました。 GRUのヴィクトル・スヴォ―ロフが「GRU: ソ連軍情報本部の内幕」(原題"Inside Soviet Military Intelligence”1984.)や、元KGBのオレク・ゴルジエフスキーが「KGBの内幕」(”KGB: The Inside Story. Hodder & Stoughton.”)など、多数の著作ですでに述べていることですが、KGBは縁故採用が常態化した組織でした。 伝説的なKGB工作員、スダプラートフは、兄の勧めで1918年にチェーカーに入り、そのまま破壊工作員を経て、NKVDで対外工作を指揮する立場に付きました。 本二次創作の原作である「シュヴァルツェスマーケン」の中でも、単行本未掲載の部分でアーベル・ブレーメは自分の娘ベアトリクスを守るために、軍部の人事に手を入れて、アクスマンを使嗾し、ベアトリクスを後方勤務で安全なシュタージの第8局に配備しています。 どういった経緯でベアトリクスが前線部隊に配備されたのかは不明ですが、自分の身可愛さで逃げた卑怯な男とも言えますし、冷徹な政治家のみせた最後の人間らしさとも取れます。 ブレジネフ時代のKGB長官で、後に書記長になったユーリー・アンドロポフは、自分の妻と息子と疎遠でした。 一説にはスターリン時代の大粛清の記憶から、離婚をして、縁を切っていたという説もあります。 葬儀に夫人が出てくるまで、西側の諜報機関はおろか、ソ連国民の多くはその存在を知らなかったそうです。 |
|
>倫理観のない 「祖国のために戦った人間を墓場から掘り起こして、馬車馬の如く働かせるだと!」といえますけど、ソビエトの体制が科学的管理法(レーニンの醉心するテイラー主義である)による立てたので、なぜソビエトのリーダーたちはまだ人権に配慮するふりをしたとバカバカしくないのが? 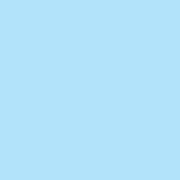
作者からの返信
2025年 05月 19日 13時 54分 私としてはアターエフを非難するのに、あえて旧時代の道徳観を持ち出して、非難したつもりだったのですが。 この点に関しては私の考察不足であったかもしれません。 スターリン主義者で知られるD.F.ウスチノフ元帥に言わせたのは失敗だったかなと…… 彼は、レニングラード軍事機械大学(ウスチノフ記念バルチック州立工科大学)卒業の技術者でした。 (国防相に就任する前は文官というのは誤りで、1955年に正式に軍人として採用されています。) 戦時中から軍需産業の管理を経験し、生産性を向上させたことで、スターリンから信頼を得たとされます。 過日、説明不足の点は書き足すつもりなので、ご海容いただければ幸いです。 |
|
Wedgieという現象についてどう思いますか?(この質問とはGalgameや古いアニメにはガキたちが女キャラたちのスカートをめくりだけ、脚本家たちがパンツの腰の部分を上に引っ張り上げ、意図的に尻の間に食い込んだ状態にするシーンが考えないと思います。) 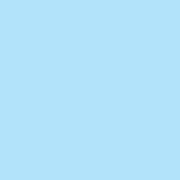
作者からの返信
2025年 05月 18日 23時 24分 ズボンの両脇から手を突っ込んで下着の端を引っ張るのですから、相手を辱める以上に、ひどい場合はケガをしますね。 スカート捲りの場合は、着ているスカートの端をめくるだけですから相手に羞恥を与える程度で、ケガするようなことはないでしょう。 アンダースコートやペチコートを履けば、いくらかマシになるかな…… カートゥーンか、ハリウッド映画か、忘れましたが、このシーンを見た時、アメリカではずいぶん野蛮な事が行われているのだなと驚いた記憶があります。 間違いなく、いじめですよね |
|
マブラヴでの白系ロシア人の役とは? 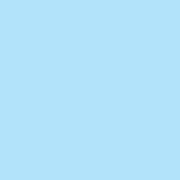
作者からの返信
2025年 05月 18日 10時 08分 よって満州国の崩壊と白系ロシア人の運命はだいぶ変わってくるのです。 南樺太が健在ですから、恐らく多くの白系ロシア人は南樺太に退避したのでしょう。 あるいは日本に帰化せずに、アメリカに逃げ渡ったのかもしれません。 香月博士が社霞を引き取ったように、ロシア人コミュニティーが史実の在日朝鮮人や在日台湾人の規模であったのでしょうか? 白人種はかなり目立ちますし、封建制の残る日本では生きづらそうですね…… |
|
>無敵の 僕はなぜ東アジアにおける人々が無敵の人ということが明確に説明します、その原因は中国では最近に脳をネットワークマシンに接続して実験を行っていだというニュースがありますから(その技術はたぶんマトリックスや攻殻機動隊に似ているのでしょう)、このニュースは東アジアにおける人々が道徳の下限ないので、生化学技術の実験場になるシンプルだと劉仲敬氏がそう述べました。 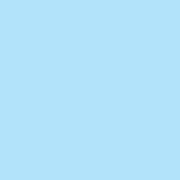
作者からの返信
2025年 05月 18日 10時 00分 1960年代以前からあるSFの空想が現実味を帯びてきたわけですか。 >このニュースは東アジアにおける人々が道徳の下限ないので、生化学技術の実験場になるシンプルだと劉仲敬氏がそう述べました。 倫理観のない中共ならやりそうですよね…… |
|
東アジア大陸(中国)における人々はあまりにも無敵の人ですから、彼らは将来でのバイオテクノロジーの実験場となる、軍閥紛争で。 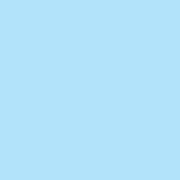
作者からの返信
2025年 05月 16日 21時 48分 予算の制約もあるのでしょうが、日本は対応できているのか、不安です。 |
|
ベレンコ中尉亡命事件のマブラヴバージョン。 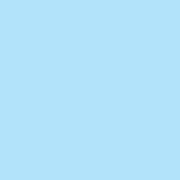
作者からの返信
2025年 05月 11日 09時 05分 そうです。 1976年9月6日に起きたヴィクトル・ベレンコ中尉亡命事件と、1984年9月6日のニコライ・オガルコフ赤軍参謀総長解任事件をミックスした話になります。 ニコライ・オガルコフは、1977年に赤軍参謀総長になるも反党的な態度を見せたので、チェルネンコとウスチノフの逆鱗に触れて解任された人物です。 オガルコフは、1994年の没年まで軍籍にあり、ソ連邦元帥になっています。 ベレンコ中尉亡命事件を扱っているかなと思って調べたのですが、他の方が二次創作で書いてなさそうなので、自分で書いてみるかなと思って、話を作りました。 今後の展開をお待ちください。 |
|
>浅学菲才な小生 僕の質問のは鉄鼠の檻では、中禅寺は禅の起源を説いていたと読んだから、禅がストア哲学に近いと思いますから。なぜなら、あの小説で、瞑想が坐禅ではないだと中禅寺はそう言えます。 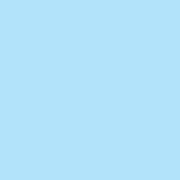
作者からの返信
2025年 05月 10日 10時 28分 >禅がストア哲学に近いと思いますから ストア学派の方が先で、禅の思想の方が数百年後になっています。 中近東経由でストア学派の思想が影響したのでしょうか。 そういう仮説があった様な気がします。 |
|
坐禅とストア哲学に似ていますか? 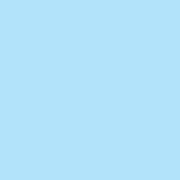
作者からの返信
2025年 05月 10日 07時 27分 付焼刃的な解説ですが、ストア哲学は理性という物を絶対視し、感情のコントロールで難事を乗り越えようとするところがあります。 一方、仏教の禅は非常に生半可な理解で述べますが、一旦自分に起こった物事を、どうしてそうなったか、冷静に見つめて客観視する面があるように思えます。 恥ずかしながら浅学菲才な小生の意見はまったくの即席漬けなので、どうぞご自身で原典に当たられることをお勧めします。 |
|
>中国製のPL-15ミサイルがかなり高性能なのかな? むしろ、アメリカ空軍システムによる訓練されたパキスタン空軍および彼らのアメリカ製のF-16が役に立ちなのだといえます。 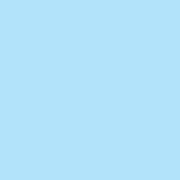
作者からの返信
2025年 05月 08日 20時 01分 共同通信の記事によれば、2008年以降、米国から供与された高解像度センサーを搭載し、精密な対地攻撃能力を得て、レーザー誘導爆弾を多用した軍事作戦をアフガン国境で行っていたようです。 ただし米国はインドとの紛争に使うのは制限しており、2019年の国境紛争の際は使っていないと米国に答えていました。 F-16で訓練したノウハウを殲撃10の運用に応用したのかもしれません。 今回の戦闘は双方の空軍が125機の戦闘機を飛ばしていますから、直接の撃墜はしていなくても、何かしらの支援という形で戦闘に関与した可能性は否定できません。 |
|
雄渾さんはインド空軍やパキスタン空軍をどう思いますが? 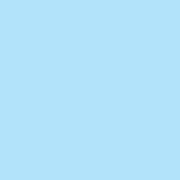
作者からの返信
2025年 05月 08日 16時 05分 インド空軍はたしか人民解放軍空軍に次ぐ世界第4位の規模ですが、練度に問題のあるように思えます。 数年前もパキスタン上空でインド空軍の戦闘機が撃墜されていますし。 ソ連製とフランス製の機体を大量に持っていますが、維持も厳しいのではないでしょうか。 パキスタン空軍は機体の保有数の割には、近年は技量が向上しているように見えます。 初期型のF-16やミラージュⅢなどの旧式の西側戦闘機の他に、中国製の殲撃10や梟龍も相当数装備してますからね。 殲撃10でソ連製のsu-30を圧倒したという話は正直疑問ですが…… 中国製のPL-15ミサイルがかなり高性能なのかな? |
|
>孤立した言語だという事です 日本語はアルタイ語族とオーストロネシア語族が混ざるクレオール語だと僕の意見から。 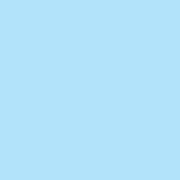
作者からの返信
2025年 05月 07日 20時 38分 確かにこういう意見はありましたね。 日本語の文法はアルタイ語族に近く、音韻はオーストロネシア語に近似しているからです。 米国の言語学者ロイ・アンドリュー・ミラー (1924年~2014年)もアルタイ語族との関係性を書いた著作を書いていますね。 彼はかつては対日戦のため情報機関の日本語通訳になった後、1950年代の頃、チベットビルマ語族の研究をしていた時期がありました。 |
|
>今回の話 この問題はアラブ人やタミル人の社交性が日本人に近いことです。その問題は欧米人が昔から日本の社会を理解できないと考えますから。 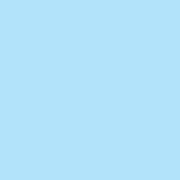
作者からの返信
2025年 05月 06日 23時 01分 フランス革命で宣伝された自由・平等・同胞愛にしても、あくまでもその価値観を共有できるには、ギリシャ・ローマ以来の歴史とそれを補う様なキリスト教の文化があってです。 日本は西欧列強からの侵略を防ぐために形だけ受け入れましたが、合わない部分はあると思いますよ。 あの独特のドライさというのは、なじめないでしょうし…… |
|
雄渾さん、アラブ人やタミル人の話し方は日本人に似ていたと思うのが? 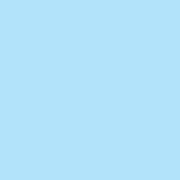
作者からの返信
2025年 05月 06日 16時 07分 日本語が、古代タミル語に影響を受けたという説は、国語学者の故・大野晋博士が40年以上前に主張されたことが始まりでした。 今回の話は、ひどく懐かしい人にあった様な気がする話題でした。 日本語に関してはっきりしているのは、印欧語族でもなく、朝鮮語や支那チベット語族とも関係性が無く、孤立した言語だという事ですね。 |
Page 3 of 75, showing 20 records out of 1481 total, starting on record 41, ending on 60

2025年 05月 23日 12時 16分