| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
くらいくらい電子の森に・・・
作者:たにゃお
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第七章 (2)
紺野さんは、訥々と語り始めた。
紺野さんがコミュニケーション・セキュリティソフト「MOGMOG」の開発・商品化の案を経営会議の議題にあげたとき、経営陣は諸手をあげて受け入れた。
パソコン世代の嗜好にマッチし、さらに全く新しいセキュリティの方式。企業向けソフトの市場に伸び悩みを感じていた経営陣には、一般ユーザーの市場に強烈なインパクトで割り込めるこの企画は、まさに救世主のように感じられたという。当時の主力商品であった、企業用セキュリティ・パッケージソフト開発の裏で、MOGMOG開発は秘密裏に、しかし多大な予算を割かれて推し進められることになった。
その後間もなくMOGMOGのために特別に設立された、紺野さん率いる開発チームは、山奥の施設にて軟禁状態でひたすらMOGMOGの開発を進めることになった。それほど、徹底した機密として扱われたのだ。
「ここのチームに集められた連中は札付きでな。扱いにくいけど腕は立つから、仕方なく雇っている、といった感じの問題児の寄せ集めでよ。上層部の奴らも、体のいい厄介払いになったんだろう。一石二鳥ってやつでよ」
そういう紺野さんの表情は、どこか誇らしげだった。
「ていうことはもしかして、割と最近山から下りてきたばっかりなの」
「あぁ。お陰で髪は伸び放題」
「…それ、おしゃれで伸ばしてるんじゃなかったんだ」
「いいから!先をつづけるの!!」
ぴしゃりと話を遮られて、男二人は首をすくめて本題に戻った。
「ところが、こういった話にはよくあることなんだけどな……」
企業用セキュリティソフトの売れ行きに暗雲が立ち込めたことをきっかけに、MOGMOG開発計画は暴走を始めた。
競合他社が、品質を保ちながらの大幅なコストダウンに成功したのだ。長い付き合いの大企業は、コストよりもソフト総入れ替えのリスクを渋った結果、顧客として残ってくれたが、浮動票ともいえる中小企業のシェアは、どんどん競合他社のセキュリティソフトに吸収されていった。
売り上げは3割減少、株価は大暴落。この最悪の事態に頭を抱える上層部に、営業部が提案した打開策は、言葉にすると至ってシンプルだった。
「MOGMOGの販売を、半年早めて年末商戦を当て込みましょう」
…MOGMOG計画についての不吉な噂を耳にした数日後、突然、山奥の施設から、会社支給の買出し・移動用の乗用車が姿を消した。その代わりに、1台の軽ワゴンが、がら空きの駐車場に弧を描くように滑り込んだ。朝一番に異変に気がついた紺野さんが、ワゴンに駆け寄り運転手に詰め寄った。
「…何だこれは!どういう状況だ!!」
運転席から転び出てきた営業一課の女子新入社員・八幡志乃が、半泣き顔で頭を下げた。
「…ご、ごめんなさい…あの…営業で使う社用車が足りないから調達して来いって……」
「え…お、おいおい…」
運転席で涙ぐんでいるのは、まだ幼さがのこる新入社員だった。紺野さんは天を仰いで立ち尽くした。起き抜けで、よく回らない頭を無理にフル稼働させて考えをまとめる…この山奥で、「社用車が足りない」という建前で、車が一台残らず奪われた。そしてこの新入社員が独りで運転してきた軽ワゴン。いや、おそらく彼女は一人で来たわけじゃない。軽ワゴンに一緒に乗ってきた社員が、車を運転して走り去ったのだろう。
「…要するに俺達は、陸の孤島に幽閉されたんだな」
そして、この可哀想な新入社員は、説明係と称した「生贄」として、この場に置き去りにされたのだろう。脳内が、ため息で満たされた気がした。それを一気に鼻から吐き出す。
「…馬鹿野郎が」
「…すみません!あの、生活用品とかの買出しは、私が…」
八幡は涙をぬぐって、腹を決めたように紺野さんの視線を受け止めた。このまま殴り倒されても、この娘はそれを受け入れるのだろう。…そう、言い含められたのだろう。それを思うと、逆に泣きたくなってきた。
「…あいつらのことだ。事情はメールで流してるんだろ」
自分らの引き揚げ終了を見計らってな、と言いかけてやめた。自分の立場が捨て駒以外の何者でもないことは、八幡本人が痛いほどよく分かっているだろうから。
「…で、俺が怒り狂ってお前に手をあげる、もしくは暴言を吐くのを待っているわけか。最近じゃ、女に悪口を言っただけで、セクハラ裁判起こせるらしいからな。俺達の脛に傷を持たせれば、あとはあいつらの思いのままだ」
「そ、そんな!私、そんなつもりじゃ」
「…もういい。行けよ」
「え…でも」
「行け!これ以上、あいつらの思う壺にはまってたまるか!!」
走り去る軽ワゴンを呆然と見送りつつ、『結構カワイイ娘だったな…』などと性懲りもなく考えている自分の業の深さに呆れていると、騒々しい音を立てて宿舎のドアが開け放たれ、数人の部下が転びでて来た。
「こ、紺野さん!本部が超アホなメール寄越しよるで!」
「うわマジかよ、ないぞ!本当にない!!」
「畜生、遅かったか!」
「紺野さん、あの軽ワゴンの奴が!!」
「くっそ、追いかけろ!!」
気休め程度のマウンテンバイクを担ぎ出し、絶望的な距離まで遠のいたワゴンをぎゃあぎゃあ喚きながら追い始めた部下は、今起きていることの深刻さが分かっていないのだろう。
まぁ、俺もなんだかよく分かってないんだが。
――この計画、俺達にしわ寄せがくる方向で暴走し始めたみたいだな。
…一方的に話を聞くのも疲れたので、質問してみた。
「…会社って、そんなことしていいの」
「いいわけあるか。告発したら俺達の圧勝だ」
紺野さんは黒革の煙草入れを取り出すと、一本くわえて火をつけた。紫煙の向こうで鈍く光るドクロのジッポは、多分ガボールのやつだ。雑誌で見たことがある。
「お?俺のジッポかい?…んふふふ、これガボールタイプ。ほれ、フタあけると、中にもラフィンスカルが入ってるんだぜ、ほらほら」
ぱちぱちぱちぱち、と、蝶番が傷みそうな程ジッポを開けたり閉めたりしてみせる紺野さん。…相当、値が張ったライターなのだろう。ついいつものノリで『まじで?なにそれ見せて見せて!?』とか身を乗り出して食いつきそうになったが、度重なる脱線にイライラしだした柚木が怖いので、話をさりげなく戻す。ジッポはあとで見せてもらおう。
「…そんな無茶をされて、誰も逃げなかったの」
「あぁ。全員で職場放棄して逃げてやろうって話も出た。だけどな」
言葉を切って、紺野さんは煙を薄く吹き上げた。何かを探すように、視線をゆっくり泳がせると、一言ずつ確かめながら、ゆっくり言葉を紡いだ。
「結局、誰も出て行かなかった。どう言えばいいのかな…俺もあいつらも、見届けたかったんだ。俺達のMOGMOGが、どこに向かうのか」
紺野さんは、再び話を続けた。
しかし、開発にかかる時間は、上層部が提示してきている期限では足りない。交代で徹夜を繰り返す計算でスケジュールを引いても、期限内に仕上げられるとは到底思えなかった。
紺野さんは、コアな箇所に関与しないプログラムだけでも外部に発注できないか、このままでは皆死んでしまう、と上司に掛け合ったが、上司は首を横に振るばかりだった。
『情報漏えい絶対禁止』この大前提の前には、技術者の生き死になど問題にならないと、暗に突きつけられ、紺野さんはとぼとぼと山奥に帰った。
外部注文も増援も断られ(というか山奥に半年以上軟禁という条件を呑む社員が現れず)、激務によるストレスで血を吐くメンバーが続出。とうとう、開発の継続すら困難な状態に陥った。もう打つべき手は「納期の後ろ倒し」しか残っていない。紺野さんは激務の中、生活必需品の買出しに現れた八幡の車をジャックして東京に戻り、決死の直訴に踏み切った。社内で波風が立つことを覚悟で、営業チームを通さずに上層部へ直訴したのだ。…案の定、製作現場の現状は上層部まで届いていなかったらしく、全員の勤務時間をまとめて提出したところ、ひどく驚かれ、緊急会議を招集することになった。
「外注は無理、増援も不可能!――いくら俺達でも、ない袖は振れない!…開発チームは恐慌状態です。このままこんな納期で推し進めていく気なら、全員一斉に、辞表を叩きつけるしかない!」
営業1課に在籍する同期の烏崎が、イスを蹴って立ち上がった。
「自惚れるな!…お前らの代わりなんて5万といるんだからな!!」
「――会議室に集められた面々は、俺と、関係部署の部長、あと専務クラス数人と、法務部の主任…それと営業部長と、MOGMOG担当営業が数人…」
ふたたび紫煙を噴き上げて、紺野さんは、正面の壁を睨みつけた。
「…多分、昨日の犯人の1人は烏崎だ。」
顔をゆがめて、再び煙草をくわえなおした。
「済まなかったな。…その、根っから悪い奴じゃないんだけどな、追い詰められたと感じると、すーぐにいっぱいいっぱいになって、思ってもいないことを口走ちゃったり、先走った行動に出て、余計に周りの反感を買ったりする奴でよ」
各部署の部長や専務の前で吊るし上げられた烏崎は、突付けば破裂しそうな顔色で紺野さんを睨みつけた。会議室での、よくある光景のはずなのに、そのときの紺野さんには、受け流す余裕がなかった。
「いねぇよ、馬鹿」
「…なんだと!?」
「社則を見てみな。……退職宣言後、会社が俺達を縛れるのは、せいぜい1ヶ月だ」
紺野さんは、別件で使う予定で持ってきていた社則を、机に叩きつけた。
「…俺達がこの開発のために、何日休日を潰していると思う。そして、俺達が有給休暇を取っているとでも思っているのか」
烏崎が、ぎりっと奥歯をかみ締め、目を血走らせた。
「退職届と一緒に、溜まりに溜まった有給休暇と代休を叩きつけるに決まってんだろ」
「き…貴様!開発チームを私物化して、会社を脅迫か!!」
烏崎は『会社を』の部分を強調して叫び、専務が居並ぶ席にちらりと目をやった。気が弱ってくると立場の強い味方を増やそうと躍起になるのも、会議室でのいつもの光景だった。でも、今現在も開発チームが命を削って仕事をしているというのにこいつは…!と考えると、(ここで紺野さんはムラムラと怒りが蘇ってきたらしく、脇にあった本の山を蹴り崩した)紺野さんも、正常な判断力を喪ってしまった。
「なにが脅迫だ、俺達の車盗んで山奥に幽閉しやがって!俺が脅迫ならお前らは監禁だ!裁判起こさないだけ有難いと思え!!」
「しゃ、社用なんだから仕方ないだろ!座り仕事なんだからたまには足使えよ!!」
「麓につく頃には日が暮れてるわ!大体なんで山梨くんだりまで車回収に来てるんだよ!都内の事業所で借りなかった理由を言え!!」
「おっ…お前ら座り仕事なんだから車いらないじゃないか!?」
「てめぇっ!座り仕事、座り仕事って、制作バカにしてんのか!?」
…あとはもう、専務の御前で同期同士が、小学生のような罵り合いとなった。やがてどちらからともなく掴みあいが始まり、あわや大乱闘というところを収めたのは、営業一課の伊佐木課長だった。
「あぁ、いや、悪かった。私の不行き届きで、君らをこんな辛い目に遭わせてしまって」
猫なで声で紺野さんたちを引き離した伊佐木課長は、親戚でも死んだかのような沈痛な面持ちで首を振ると、紺野さんに向き直った。
「知らなかったんだよ、君達がそんな大変な思いをしているなんて。こんな会議を設ける前に、なぜ私に一言相談してくれなかったんだい」
「俺はっ……」
俺は相談した…そう言いかけて、言葉が詰まった。
紺野さんは、「営業一課」宛てに抗議のメールや電話を入れたが、「伊佐木課長」個人には相談も、抗議もしていないのだ。紺野さんが呆然としていると、
「烏崎君、いつも言っているだろう。仕事の基本は『報告・連絡・相談』だよ。何かあれば、なんでも、私に相談してくれなければ、いけないよ」
子供に噛んで含めるような口調で、烏崎の肩を叩く。烏崎は青い顔をして、紺野さんと伊佐木課長を交互に見ながら席に着いた。伊佐木課長は、ぴしっと糊が利いたシャツの僅かな乱れを鏡を見たかのように正確に直し、口元に左右対称な微笑を浮かべた。
「…えぇ、皆さん。紺野君と、うちの烏崎をお許し下さい。聞いての通り、紺野君は連日の激務によるストレスで、烏崎は、開発チームと上層部との板ばさみによるストレスで、疲れ果てていたのです。完璧な新製品の開発は、確かに大事です!しかし、それは従業員の健康を犠牲にしてまで、成し遂げられるべきものでは、ありえない!」
伊佐木課長は、周りの反応を確かめるように一呼吸おいて、吐息をつくように語り始めた。
「とはいえ、逼迫しているわが社において、年末商戦は無視できないところです。…それで、どうでしょう?私に一つ、案があるのですが…」
「…案って、何よ」
柚木が低い声で促した。紺野さんは灰皿に吸殻を押し付けると、最後の紫煙を、深いため息と一緒に吐き出した。
「想像はついただろう。…俺達は、MOGMOGの一番大事な部分を仕上げられないまま、ただ年末商戦に間に合わせたんだよ」
柚木は、口をつぐんでしまった。何を思っているのか、その表情からは読み取れない。僕は…
そんなに衝撃を受けていなかった。
なんとなく、気がついていたような気さえする。
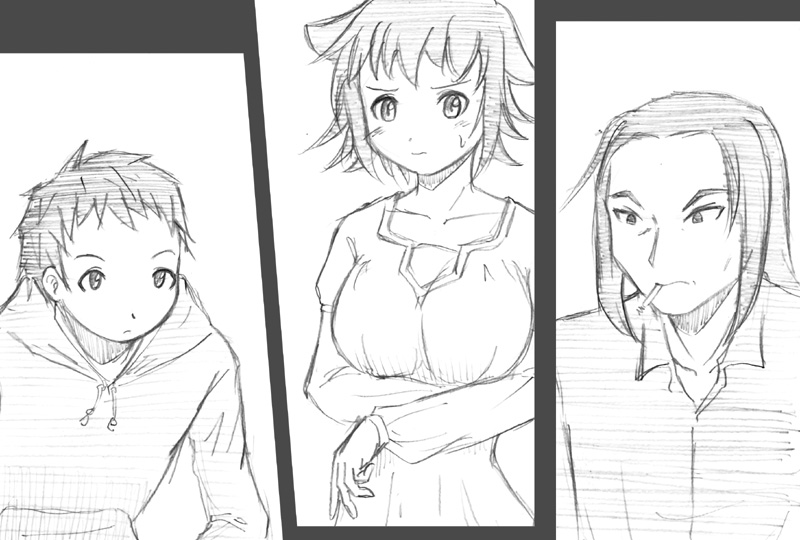
紺野さんは全部話してはくれなかったけど、市販されているMOGMOGと、ビアンキを始めとするMOGMOGαの違いについて、僕なりに2通りの想像をしていた。1つは、MOGMOGαは市販されているMOGMOGのバージョンアップ版…所謂MOGMOGパート2みたいなものじゃないか、という想像。
そしてもう1つは、MOGMOGとMOGMOGαは、全くの別物なんじゃないか、という想像。MOGMOGαは、ただのバージョンアップ版とは違うんじゃないか?とうっすら思っていたのには、理由がある。
MOGMOGとMOGMOGαの間には、互換性がまったくない。
バージョンが違うソフトで保存されたデータが開けなかったり、開けても正しく作動しないことはよくある。それでも、完全に別のソフトと認識されることは少ないと思う。ましてや、僕のソフトはいわば上位バージョンだ。MOGMOGに対応しているソフトが、MOGMOGαに対応しないというのは、よく考えるとおかしい。
確か、僕のMOGMOGには、あの18禁ソフトがインストール出来なかった。
…いやちがう根に持ってたわけじゃないんだ。ただ単に一つの疑問点として、心の中にずっと根付いていたわけで…とにかく、そういう訳で、僕はMOGMOGとMOGMOGαの関係に疑問を持っていた。だから改めて話されても、予想の範囲内だった。
「なんかそれ…ひどい」
柚木ががばっと顔を上げた。瞳にうっすら涙が浮かんでいる。紺野さんが、疲れたような苦笑を浮かべて視線を下げた。…無理もない。偶然、本物のMOGMOGを手に入れた僕と違って、柚木はお金を払ってニセモノを手にしたんだから。そして彼女の反応は、全てのMOGMOGユーザーを代表するものに違いない……
「その、伊佐木って課長!!」
……え?
紺野さんも、思わず組んでいた両手を解いて顔を上げた。
「何が『年末商戦は無視できないところです』よ!MOGMOGの納期早めたのは、そいつなんでしょ!?みんなに無茶させて、自分はそ知らぬ振りして、我慢できなくなって爆発したら『おおヨシヨシ』って宥め役に回って自分だけイイひと気取り!?」
「ゆ、柚木ちゃん…」
「いやそんな…憶測だけで決めつけるのはどうかと…」
「憶測で充分だよ!!」
ぴしゃりと言い放たれて、僕は口ごもってしまった。
「年末商戦なんて、会社側の都合でしょ。それに間に合わせるために半端なものを売りに出すなんて、誠意のある人がすることじゃないよ!」
「そ、そりゃそうだけど、一方の話だけじゃ分からないことだって…」
「へ理屈は聞きたくないっ!!」
突然横っ面に衝撃が走った。ビンタ一閃、僕は右側に詰まれた雑誌の山に頭から突っ込んだ。全体的に薄く積もった埃がバフンと舞い上がり、思わずむせ返る。
「……すげぇ……」
紺野さんが呆然として、頭上で呟いた。見事に状況についていけていない。僕も、頬が痛い事以外は何一つ把握できてない。
「ぼ、僕、何かした…?」
埃の海から起き上がって最初に口にしたのは、そんな情けない一言だった。柚木は僕を殴った瞬間、何か胸につかえていたもやもやが『スカッ』と晴れたらしく、ぽかんとした顔で僕を見下ろしていた。
「えと…そ、そうだよ!あんたの言葉には、実感がこもってない!!べ、べつに一瞬課長と混同したわけじゃないんだから!」
「…語るに落ちたよこのひと…」
僕は殴られた瞬間の表情のまま、紺野さんに首を振り向けた。…これ、僕怒っていいところですよね?無言の問いかけに、紺野さんはフイと視線を逸らして回答を拒否した。俺は関係ありません、と。一応、怒るべき相手にお伺いを立てることにする。
「…ねぇ、これヒドいよね。自分でもそう思わない?」
「そういう所がイヤなの!もうこの話はおしまい!…じゃ、紺野さん続きよろしく!」
柚木は一方的に話を打ち切り、紺野さんを促して体育座りしてしまった。場が収まったことを見越して輪に戻ってきた紺野さんの横顔を覗き込み、再び無言の問いかけをする。僕は殴られ損ですか、と。紺野さんはこの問いを黙殺して本題に戻った。
「…そして、MOGMOGは未完成のまま外見だけ取り繕って発売された。でも、それで済むはずないよな」
MOGMOGが発売されれば、プログラムを解析する輩が出てくる。解析されて、不正が公になるのは時間の問題だ。そこで紺野さんは開発会議の席で、ある提案をした。
「開発部は、完全なMOGMOGの完成を急ぎます。そして完成次第、MOGMOGユーザーにアップデートファイルとして配布するというのはいかがでしょうか」
守屋営業部長が、苦りきった顔で紺野さんを一瞥した。
「…元々入っている、ダミーのMOGMOGはどうなる」
「必要な情報だけMOGMOGに上書きして、あとはアンインストールします」
「アンインストーラーも一緒に配布するわけか。…バレないかね、そんなことして」
「そのリスクはありますが、現状のままにしておくわけにはいかないでしょう。まったく別物のソフトへの書き換えであることだけ伏せて、『重大なバグを修正するアップデートファイル』である旨、ユーザーに告知すれば、大抵のユーザーはインストールしてくれるんじゃないでしょうか。同時に追加される機能などの説明をread meテキストで添付すれば、大した混乱はないと思います」
紺野さんの発言が終わると、会議室内は水を打ったように静まり返った。…もう、これ以上議論の余地はない。皆がそう確信しているものと、紺野さんは高をくくっていた。
そのとき、銀色のカフスボタンをつけた純白の袖が、すっと挙がった。
「伊佐木課長」
進行役の社員が短く名前を呼ぶ。伊佐木課長は、いつもの左右対称な微笑を浮かべて起立した。イスを引く気配すら感じない、見事な「起立」だったという。どうでもいいけど。
「アップデートファイルへの『偽装』。一見、やむを得ないような気がしますね。しかし、もう少しだけ、改良の余地があるのでは、ないでしょうか」
「……は?」
前回の『ニセMOGMOG会議』以来、紺野さんは、この温厚そうな営業課長に漠とした不信感を抱いていた。そして紺野さんは、それを隠せる人じゃない。で、『偽装』という言い方にカチンときて、思わずぶっきらぼうに答えてしまった。
「はは…そう、剣呑にしないでください。…アップデートファイルを装うことには、一つだけ、心配な点があるのです」
伊佐木課長は言葉を切り、ゆっくりと周囲を見渡した。
「たとえば仕事で忙しい時や、少し重いデータを扱っている時。アップデートは後回しにされることが多いでしょう」
「…そうですね」
「その結果、忘れてしまうことも、多いのではないでしょうか?」
「アラームを工夫しますよ」
「でも、作業がお客様の手にゆだねられている限り、100%じゃない」
「…認めます。しかし、現状それ以外に」
「あるでしょう?…いい方法が」
紺野さんは、沈黙を返事にして伊佐木課長を睨んだ。笑顔の形に強張った細い眼は、なんの感情も伝えてこない。しかし、自分がどこに誘導されているのかだけは、よく分かった。
「全ユーザーのパソコンに、ひっそりと自動的に、インストールしてしまえばいいんですよ」
「それじゃウイルスと変わらないじゃないですか……!」
「アップデートファイルに『偽装』して配布するのと、何がちがうのでしょうか?」
伊佐木課長は、あくまで左右対称の微笑を絶やさず、ゆっくりと首を振り向けた。…心底、ぞっとしたという。言葉は確かに通じているのに、肝心の心が通じない生き物と言葉を交わしているような気分だった…と紺野さんは語る。
「全然違う!何のために、アップデートファイルとして配布すると思うんですか!…いくら現行のニセMOGMOGの仕様に合わせても、やっぱり使い勝手は多少変わってしまうんです。それに環境によっては、強引なプログラムの書き換えで急に不具合を起こす可能性だってある。ならば、それをユーザーに一言告知しておくのがスジじゃないですか!」
「…そっとしておけばほぼ分からない欠陥を、わざわざ詳らかにしてユーザーの不安をあおるのが、わが社のスジ、なのですか?」
紺野さんを覗き込むように首を傾けて、伊佐木課長は言葉を切った。
「ね?何も、ユーザーを害するために、こんなことを言うわけじゃないのです。若いんだから、そこはもっと柔軟に、柔軟に。…そうでしょう?」
役員の席から苦笑がもれた。…紺野さんの意見は「よくありがちな若者の暴走」として一蹴され、伊佐木課長の案が採用されることに決定した。
「…で、ニセMOGMOG発売の数日前、真のMOGMOGは完成した。開発チームは、今も山梨の山奥で必死にデバッグ作業をしている。そして俺の仕事は、お前を含めて19人のモニターを使った調査だ。……ちょっと疲れたな。珈琲でも煎れよう」
紺野さんは一旦言葉を切って立ち上がった。柚木はまだ見ぬ伊佐木部長に噛み付きそうな顔で聞いていたが、僕の考えは柚木とは違った。
この伊佐木って人は確かに嫌な奴かもしれない。でも、だからといって彼の判断が全部間違ってるとは思えない。
確かに、年末商戦にこだわるあまり、未完成なソフトを流通させてしまったのは、許されることじゃないとは、僕も思う。でも伊佐木課長の判断には『会社存続の危機』という、絶対的な前提があった。いくらいいソフトを開発しても、リリース時に会社本体が潰れているのでは本末転倒じゃないか。そんな状況で、こういう判断をするひとがいたとしても不思議じゃない。
MOGMOGの配信方法に関しては、紺野さんに分があるとは思うけど、「MOGMOGの欠陥がばれないように、全ユーザーのプログラムを書き換える」必要があるというなら、伊佐木課長の案も全く的外れとは思わない。どっちの案をとるかは、その会社の姿勢の問題だと思う。効率をとるか、ユーザーへの誠意をとるか…。
「珈琲、入ったぞ」
香ばしい珈琲の湯気が鼻をくすぐった。紺野さんと会ってからこっち、うまい珈琲にありつく機会が多くなった。お陰で舌が肥えてしまって、ドトールなんかの珈琲が物足りなくなってきている。貧乏なのに困ったものだと思う。
「どうだ、いいだろう。うちコーヒーミルがあるんだぜ。ヤバいだろこれ」
「挽きたてかぁ…どうりで…ブルーマウンテン?」
「いや、マンデリン」
「…ふーん」
白いカップになみなみ注がれた珈琲の湯気に顔をさらす。紺野さんが何かを話し始めたみたいだけれど、ちょっと疲れたので個人的に珈琲ブレイク。なんか柚木が熱心に聴いてるみたいだから、あとで聞きなおそう。目を閉じて珈琲の香気を吸い込んで深くため息をつく…あぁ、至福…
「姶良、聞いてる!?」
柚木の大声で、香気の帳が破られた。僕はレンガをどかされたダンゴ虫のようにあわあわと周囲を見渡した。
「うぁ、あの…き、聞いてた…」
「あんな目に遭ったのに、どうしてそんなに気が散りやすいの!?…姶良、今に死ぬよ?」
「…ごめんなさい。ほんと、ごめんなさい」
「なんですぐ謝るの!!」
「…僕どうすればいいんだよ」
「…あの、続き話していいか?」
紺野さんは、苦々しげに語りはじめた。この話に至るまでの、長くて辛かった開発秘話を語る時よりも、ずっと苦々しい口調で。実際この先の話は、とてもイヤな内容になっていく。
「ここから先は、俺もよく分かってない話だ。ただ、社内で聞きかじった噂をもとにした憶測に過ぎない。…反吐が出るほどイヤな話だ」
人事部の同期から、社がプログラマーやSEを大量採用しているという噂を聞いた。
「忙しいのは分かるけどさ、自分のとこの人材なんだから、最終面接くらい顔出せよな」
…初耳だった。紺野さんは、軽く肩を叩いて去ろうとした同期を引きとめて詳しい話を聞くことにした。
「お前が知らないってなぁ…」
彼は呆れ半分、驚き半分な表情で事の次第を明かしてくれた。
紺野さんが上層部に業務改善を訴えた「MOGMOG開発会議」から1週間もしないうちに、開発部の企業向け商品開発担当者から『個人向け商品』開発要員として、SE・プログラマーを大量採用したいとの要請があった。個人向け商品は目下MOGMOGだけだし、担当者は紺野さんのはずなのにおかしいとは思ったものの、紺野さんが山奥に篭っていることを知っていたので、代理で面接をすると思ったらしい。
キナ臭い空気を感じた紺野さんは、開発チームの面々に『MOGMOGに関する情報の徹底的な封印』を指示した。元々山奥に隔離されていたので、封印は簡単だった。連日の徹夜作業で、プログラミング以外のことは一切面倒になっていた彼らは最初しぶっていたが、この奇妙な採用活動のことを聞かせると、暫く考え込むような顔をして、やがて作業を中断した。
開発チームに本部への帰還指示が出たのは、この話を聞いた2週間後だった。
「長いこと、ご苦労でしたね。MOGMOGが発売になれば、情報を隠す必要は、なくなりますから。…本部に帰還したら、少しゆっくりしてください」
電話越しの伊佐木課長の声はとても平坦で、ひたすら上機嫌だった。紺野さんは受話器を耳に当てたまま、目をさまよわせた。そして一呼吸おくと、普段より1オクターブ高い声を出した。
「なるほど…しかし申し訳ない。今動くわけにはいけないんです」
「おや、何故。そろそろ都会の空気が恋しいころなんじゃないですか」
「そうしたいのは山々なんですが…完成にはしばらく時間がかかりそうでして」
「それなら、なおさら人手が必要でしょう。こちらでやればいい。最近プログラマーを増員してね、ぜひ当社きっての名SEの君に鍛えてもらいたい、と、思っているんですよ」
聞こえないように舌打ちをして、紺野さんはしばらく黙り込んだ。
「ね、そうでしょう。私は、散々無理をしてもらった君達に、ゆっくり休んでもらいたい、と思っているんですよ。どうですか、六本木あたりで一杯」
たたみかける様に懐柔にかかる伊佐木課長の耳障りな声を聞き流しながら、紺野さんは再び目を泳がせた。憔悴しきった開発チームのメンバー、古河と目が合った。
――扱いづらい奴らかもしれない。俺も含めて。
周りの和を乱したことも数知れない。俺達を本気で憎んでいる奴もいるだろう。
しかし「こんなこと」をされるほどの非は、俺達にはない!
受話器のむこうでなおも続く、耳障りな猫なで声を打ち切るために、紺野さんは口を開いた。
「有難いお話です。…が、色々事情があって、終わらないと動けないんですよ」
「はぁ…それは何で。引越しなら、営業部が総出で、お手伝いしますよ」
「何で…東京に帰したがるんですか」
つい、イラつきが言葉に出てしまった。電話の向こうが、ふっと静まり返った。
「…や、すんません。とにかく、作業がこれ以上延びると、それだけメンバーに負担がかかるんでね。人手が余ってるなら、こっちに回してもらえると助かります」
再び声のトーンを上げて、これ以上話が長引くまえに受話器を置いた。視線を上げると、皆、作業の手を止めて電話に聞き入っていた。彼らの視線がじりじりと集中する。紺野さんは皆に向き直ると、ただ1回だけ頷いた。
「…なんか、途中からよく分からなくなったんだけど。会社が、開発チームに何をしようとしてるって?」
柚木がいったん話を切った。紺野さんは、どこか煮え切らないような感じで髪をくしゃりと掴み、頬杖をついた。
「ここからは、本当に俺の憶測なんだよ。ただ、この不自然な状況をみると、そうとしか考えられない」
「不自然な、状況?」
「このタイミングで、俺に隠してのSEやプログラマーの大量雇用。…そして性急過ぎる、俺達への帰還指示。それに伊佐木は、採った奴らをMOGMOG開発に関わらせようとした…」
「…僕、なんか分かってきた」
僕に一瞥くれると、紺野さんは苦々しげに珈琲をあおった。
「採用した人たちに仕事を引き継がせて、紺野さんたちを追い出すつもり…なんじゃない」
「…まぁ、最終的にはな。でも、今ただ単に俺達を追い出しても、奴らには何のメリットもない。…この話には、まだウラがあるんだ」
カツン、と音を立ててカップを置くと、正面を睨みすえた。
「俺も一応保身のためにな、俺の直訴で開かれた開発会議や、プログラムの配信方法を決めた開発会議の議事録を調べたんだよ。だが…議事録は、なかった」
「…!!」
「会議室予約も確認したが、全て取り消しになっていた。…つまり、あいつらが俺に指図して不正行為をやらせた『証拠』は、何も残っていないんだ」
「そ、それじゃぁ」
「…そういうこと。あいつら、最初から逃げおおせるなんて思ってなかったんだよ。…俺達は体のいい生贄だな」
頭がぐらりと揺れた。僕に関係ない、遠い世界の事情を聞いているはずなのに、僕は自分でもびっくりするほど落胆していた。
――これが、大人の社会か。
「なにそれ!そんな会社、内部告発して倒産させちゃえばいいのに!!」
柚木が激昂して乱暴にカップを置いた。僕はといえば…この二人が、怒りのあまり珈琲セットを残らず粉砕するんじゃないかと、場違いな心配をしていた。
「それは出来ない」
紺野さんはカラになったカップを脇によけると、顔の前で指を組み合わせた。
「何で!?そんな会社に忠誠誓う必要なんてないじゃない!!」
「そ、そうじゃないよ柚木。内部告発なんかしたら、再就職できなくなるから…」
「見くびるんじゃねぇ、馬鹿」
匕首を突き通すような声で言い放つと、組んだ指の間から僕を睨みつけた。
「ば、馬鹿…?」
「SEだとかプログラマーだとか、色んな横文字で呼ばれてるがな、俺達の本質は『職人』なんだよ。俺達が忠誠を誓うのは『会社』なんかじゃない。ましてや食い扶持の心配なんざ論外だ」
紺野さんは組んでいた指をゆっくりほどいて静かにテーブルに置いた。
「俺達が忠誠を誓うのは、俺達が創りあげた『作品』。それだけだ。…俺達がヤケになって内部告発騒ぎを起こしたらどうなると思う。MOGMOGの発売で煮え湯を飲まされた競合他社が、マスコミや世論を動員して徹底的に叩きにくる。そうなったら、俺達のMOGMOGは会社ごとひねり潰されるんだよ。そしてお前が言ったとおり、俺達を雇う人間は出ない。開発チームは散り散りになり、MOGMOGは奴らに嬲り殺しにされるんだ。……あ、むきになってすまんな。えーと、どこまで話したっけな…」
「えと、生贄のところまで…かな」
すっかり毒気を抜かれたような顔で、柚木がつぶやいた。僕はといえば、突然紺野さんに睨まれたことで思考停止しきっていたので、内心だらだら冷や汗をかきながら、がくがく首を縦に振るのがせいいっぱいだった。
「おぉ、そうだそうだ。…俺が想像した最悪のシナリオは、こうだ」
ある日突然開かれる記者会見。記者会見の主題は、『開発チームの不正』。フラッシュライトの中、全ての罪を一身に背負ったかのような顔で一斉に頭を下げる経営陣。『私どもの監督不行き届きにより、一部開発チームの不正を許してしまいました。…被害を受けた方々には誠心誠意対応させていただきます。弊社HPより配信している修正プログラムを、ぜひともご利用下さい』
ざっ…と一斉にポマード臭い頭をさらす経営陣。社内の査察で発覚し、自ら謝罪というスタイルをとったことは、むしろ好意をもって迎えられる。そして『プログラム』という、一般人からすれば全くのブラックボックスでしかない分野であったがために開発チームに欺かれた、という建前は、却って世論の同情をさそうことだろう。世論の憎しみは、手抜き施工を行なった開発チームに集中する。そしてMOGMOG開発チームは、永久にこの世界から追放される。
紺野さんがコミュニケーション・セキュリティソフト「MOGMOG」の開発・商品化の案を経営会議の議題にあげたとき、経営陣は諸手をあげて受け入れた。
パソコン世代の嗜好にマッチし、さらに全く新しいセキュリティの方式。企業向けソフトの市場に伸び悩みを感じていた経営陣には、一般ユーザーの市場に強烈なインパクトで割り込めるこの企画は、まさに救世主のように感じられたという。当時の主力商品であった、企業用セキュリティ・パッケージソフト開発の裏で、MOGMOG開発は秘密裏に、しかし多大な予算を割かれて推し進められることになった。
その後間もなくMOGMOGのために特別に設立された、紺野さん率いる開発チームは、山奥の施設にて軟禁状態でひたすらMOGMOGの開発を進めることになった。それほど、徹底した機密として扱われたのだ。
「ここのチームに集められた連中は札付きでな。扱いにくいけど腕は立つから、仕方なく雇っている、といった感じの問題児の寄せ集めでよ。上層部の奴らも、体のいい厄介払いになったんだろう。一石二鳥ってやつでよ」
そういう紺野さんの表情は、どこか誇らしげだった。
「ていうことはもしかして、割と最近山から下りてきたばっかりなの」
「あぁ。お陰で髪は伸び放題」
「…それ、おしゃれで伸ばしてるんじゃなかったんだ」
「いいから!先をつづけるの!!」
ぴしゃりと話を遮られて、男二人は首をすくめて本題に戻った。
「ところが、こういった話にはよくあることなんだけどな……」
企業用セキュリティソフトの売れ行きに暗雲が立ち込めたことをきっかけに、MOGMOG開発計画は暴走を始めた。
競合他社が、品質を保ちながらの大幅なコストダウンに成功したのだ。長い付き合いの大企業は、コストよりもソフト総入れ替えのリスクを渋った結果、顧客として残ってくれたが、浮動票ともいえる中小企業のシェアは、どんどん競合他社のセキュリティソフトに吸収されていった。
売り上げは3割減少、株価は大暴落。この最悪の事態に頭を抱える上層部に、営業部が提案した打開策は、言葉にすると至ってシンプルだった。
「MOGMOGの販売を、半年早めて年末商戦を当て込みましょう」
…MOGMOG計画についての不吉な噂を耳にした数日後、突然、山奥の施設から、会社支給の買出し・移動用の乗用車が姿を消した。その代わりに、1台の軽ワゴンが、がら空きの駐車場に弧を描くように滑り込んだ。朝一番に異変に気がついた紺野さんが、ワゴンに駆け寄り運転手に詰め寄った。
「…何だこれは!どういう状況だ!!」
運転席から転び出てきた営業一課の女子新入社員・八幡志乃が、半泣き顔で頭を下げた。
「…ご、ごめんなさい…あの…営業で使う社用車が足りないから調達して来いって……」
「え…お、おいおい…」
運転席で涙ぐんでいるのは、まだ幼さがのこる新入社員だった。紺野さんは天を仰いで立ち尽くした。起き抜けで、よく回らない頭を無理にフル稼働させて考えをまとめる…この山奥で、「社用車が足りない」という建前で、車が一台残らず奪われた。そしてこの新入社員が独りで運転してきた軽ワゴン。いや、おそらく彼女は一人で来たわけじゃない。軽ワゴンに一緒に乗ってきた社員が、車を運転して走り去ったのだろう。
「…要するに俺達は、陸の孤島に幽閉されたんだな」
そして、この可哀想な新入社員は、説明係と称した「生贄」として、この場に置き去りにされたのだろう。脳内が、ため息で満たされた気がした。それを一気に鼻から吐き出す。
「…馬鹿野郎が」
「…すみません!あの、生活用品とかの買出しは、私が…」
八幡は涙をぬぐって、腹を決めたように紺野さんの視線を受け止めた。このまま殴り倒されても、この娘はそれを受け入れるのだろう。…そう、言い含められたのだろう。それを思うと、逆に泣きたくなってきた。
「…あいつらのことだ。事情はメールで流してるんだろ」
自分らの引き揚げ終了を見計らってな、と言いかけてやめた。自分の立場が捨て駒以外の何者でもないことは、八幡本人が痛いほどよく分かっているだろうから。
「…で、俺が怒り狂ってお前に手をあげる、もしくは暴言を吐くのを待っているわけか。最近じゃ、女に悪口を言っただけで、セクハラ裁判起こせるらしいからな。俺達の脛に傷を持たせれば、あとはあいつらの思いのままだ」
「そ、そんな!私、そんなつもりじゃ」
「…もういい。行けよ」
「え…でも」
「行け!これ以上、あいつらの思う壺にはまってたまるか!!」
走り去る軽ワゴンを呆然と見送りつつ、『結構カワイイ娘だったな…』などと性懲りもなく考えている自分の業の深さに呆れていると、騒々しい音を立てて宿舎のドアが開け放たれ、数人の部下が転びでて来た。
「こ、紺野さん!本部が超アホなメール寄越しよるで!」
「うわマジかよ、ないぞ!本当にない!!」
「畜生、遅かったか!」
「紺野さん、あの軽ワゴンの奴が!!」
「くっそ、追いかけろ!!」
気休め程度のマウンテンバイクを担ぎ出し、絶望的な距離まで遠のいたワゴンをぎゃあぎゃあ喚きながら追い始めた部下は、今起きていることの深刻さが分かっていないのだろう。
まぁ、俺もなんだかよく分かってないんだが。
――この計画、俺達にしわ寄せがくる方向で暴走し始めたみたいだな。
…一方的に話を聞くのも疲れたので、質問してみた。
「…会社って、そんなことしていいの」
「いいわけあるか。告発したら俺達の圧勝だ」
紺野さんは黒革の煙草入れを取り出すと、一本くわえて火をつけた。紫煙の向こうで鈍く光るドクロのジッポは、多分ガボールのやつだ。雑誌で見たことがある。
「お?俺のジッポかい?…んふふふ、これガボールタイプ。ほれ、フタあけると、中にもラフィンスカルが入ってるんだぜ、ほらほら」
ぱちぱちぱちぱち、と、蝶番が傷みそうな程ジッポを開けたり閉めたりしてみせる紺野さん。…相当、値が張ったライターなのだろう。ついいつものノリで『まじで?なにそれ見せて見せて!?』とか身を乗り出して食いつきそうになったが、度重なる脱線にイライラしだした柚木が怖いので、話をさりげなく戻す。ジッポはあとで見せてもらおう。
「…そんな無茶をされて、誰も逃げなかったの」
「あぁ。全員で職場放棄して逃げてやろうって話も出た。だけどな」
言葉を切って、紺野さんは煙を薄く吹き上げた。何かを探すように、視線をゆっくり泳がせると、一言ずつ確かめながら、ゆっくり言葉を紡いだ。
「結局、誰も出て行かなかった。どう言えばいいのかな…俺もあいつらも、見届けたかったんだ。俺達のMOGMOGが、どこに向かうのか」
紺野さんは、再び話を続けた。
しかし、開発にかかる時間は、上層部が提示してきている期限では足りない。交代で徹夜を繰り返す計算でスケジュールを引いても、期限内に仕上げられるとは到底思えなかった。
紺野さんは、コアな箇所に関与しないプログラムだけでも外部に発注できないか、このままでは皆死んでしまう、と上司に掛け合ったが、上司は首を横に振るばかりだった。
『情報漏えい絶対禁止』この大前提の前には、技術者の生き死になど問題にならないと、暗に突きつけられ、紺野さんはとぼとぼと山奥に帰った。
外部注文も増援も断られ(というか山奥に半年以上軟禁という条件を呑む社員が現れず)、激務によるストレスで血を吐くメンバーが続出。とうとう、開発の継続すら困難な状態に陥った。もう打つべき手は「納期の後ろ倒し」しか残っていない。紺野さんは激務の中、生活必需品の買出しに現れた八幡の車をジャックして東京に戻り、決死の直訴に踏み切った。社内で波風が立つことを覚悟で、営業チームを通さずに上層部へ直訴したのだ。…案の定、製作現場の現状は上層部まで届いていなかったらしく、全員の勤務時間をまとめて提出したところ、ひどく驚かれ、緊急会議を招集することになった。
「外注は無理、増援も不可能!――いくら俺達でも、ない袖は振れない!…開発チームは恐慌状態です。このままこんな納期で推し進めていく気なら、全員一斉に、辞表を叩きつけるしかない!」
営業1課に在籍する同期の烏崎が、イスを蹴って立ち上がった。
「自惚れるな!…お前らの代わりなんて5万といるんだからな!!」
「――会議室に集められた面々は、俺と、関係部署の部長、あと専務クラス数人と、法務部の主任…それと営業部長と、MOGMOG担当営業が数人…」
ふたたび紫煙を噴き上げて、紺野さんは、正面の壁を睨みつけた。
「…多分、昨日の犯人の1人は烏崎だ。」
顔をゆがめて、再び煙草をくわえなおした。
「済まなかったな。…その、根っから悪い奴じゃないんだけどな、追い詰められたと感じると、すーぐにいっぱいいっぱいになって、思ってもいないことを口走ちゃったり、先走った行動に出て、余計に周りの反感を買ったりする奴でよ」
各部署の部長や専務の前で吊るし上げられた烏崎は、突付けば破裂しそうな顔色で紺野さんを睨みつけた。会議室での、よくある光景のはずなのに、そのときの紺野さんには、受け流す余裕がなかった。
「いねぇよ、馬鹿」
「…なんだと!?」
「社則を見てみな。……退職宣言後、会社が俺達を縛れるのは、せいぜい1ヶ月だ」
紺野さんは、別件で使う予定で持ってきていた社則を、机に叩きつけた。
「…俺達がこの開発のために、何日休日を潰していると思う。そして、俺達が有給休暇を取っているとでも思っているのか」
烏崎が、ぎりっと奥歯をかみ締め、目を血走らせた。
「退職届と一緒に、溜まりに溜まった有給休暇と代休を叩きつけるに決まってんだろ」
「き…貴様!開発チームを私物化して、会社を脅迫か!!」
烏崎は『会社を』の部分を強調して叫び、専務が居並ぶ席にちらりと目をやった。気が弱ってくると立場の強い味方を増やそうと躍起になるのも、会議室でのいつもの光景だった。でも、今現在も開発チームが命を削って仕事をしているというのにこいつは…!と考えると、(ここで紺野さんはムラムラと怒りが蘇ってきたらしく、脇にあった本の山を蹴り崩した)紺野さんも、正常な判断力を喪ってしまった。
「なにが脅迫だ、俺達の車盗んで山奥に幽閉しやがって!俺が脅迫ならお前らは監禁だ!裁判起こさないだけ有難いと思え!!」
「しゃ、社用なんだから仕方ないだろ!座り仕事なんだからたまには足使えよ!!」
「麓につく頃には日が暮れてるわ!大体なんで山梨くんだりまで車回収に来てるんだよ!都内の事業所で借りなかった理由を言え!!」
「おっ…お前ら座り仕事なんだから車いらないじゃないか!?」
「てめぇっ!座り仕事、座り仕事って、制作バカにしてんのか!?」
…あとはもう、専務の御前で同期同士が、小学生のような罵り合いとなった。やがてどちらからともなく掴みあいが始まり、あわや大乱闘というところを収めたのは、営業一課の伊佐木課長だった。
「あぁ、いや、悪かった。私の不行き届きで、君らをこんな辛い目に遭わせてしまって」
猫なで声で紺野さんたちを引き離した伊佐木課長は、親戚でも死んだかのような沈痛な面持ちで首を振ると、紺野さんに向き直った。
「知らなかったんだよ、君達がそんな大変な思いをしているなんて。こんな会議を設ける前に、なぜ私に一言相談してくれなかったんだい」
「俺はっ……」
俺は相談した…そう言いかけて、言葉が詰まった。
紺野さんは、「営業一課」宛てに抗議のメールや電話を入れたが、「伊佐木課長」個人には相談も、抗議もしていないのだ。紺野さんが呆然としていると、
「烏崎君、いつも言っているだろう。仕事の基本は『報告・連絡・相談』だよ。何かあれば、なんでも、私に相談してくれなければ、いけないよ」
子供に噛んで含めるような口調で、烏崎の肩を叩く。烏崎は青い顔をして、紺野さんと伊佐木課長を交互に見ながら席に着いた。伊佐木課長は、ぴしっと糊が利いたシャツの僅かな乱れを鏡を見たかのように正確に直し、口元に左右対称な微笑を浮かべた。
「…えぇ、皆さん。紺野君と、うちの烏崎をお許し下さい。聞いての通り、紺野君は連日の激務によるストレスで、烏崎は、開発チームと上層部との板ばさみによるストレスで、疲れ果てていたのです。完璧な新製品の開発は、確かに大事です!しかし、それは従業員の健康を犠牲にしてまで、成し遂げられるべきものでは、ありえない!」
伊佐木課長は、周りの反応を確かめるように一呼吸おいて、吐息をつくように語り始めた。
「とはいえ、逼迫しているわが社において、年末商戦は無視できないところです。…それで、どうでしょう?私に一つ、案があるのですが…」
「…案って、何よ」
柚木が低い声で促した。紺野さんは灰皿に吸殻を押し付けると、最後の紫煙を、深いため息と一緒に吐き出した。
「想像はついただろう。…俺達は、MOGMOGの一番大事な部分を仕上げられないまま、ただ年末商戦に間に合わせたんだよ」
柚木は、口をつぐんでしまった。何を思っているのか、その表情からは読み取れない。僕は…
そんなに衝撃を受けていなかった。
なんとなく、気がついていたような気さえする。
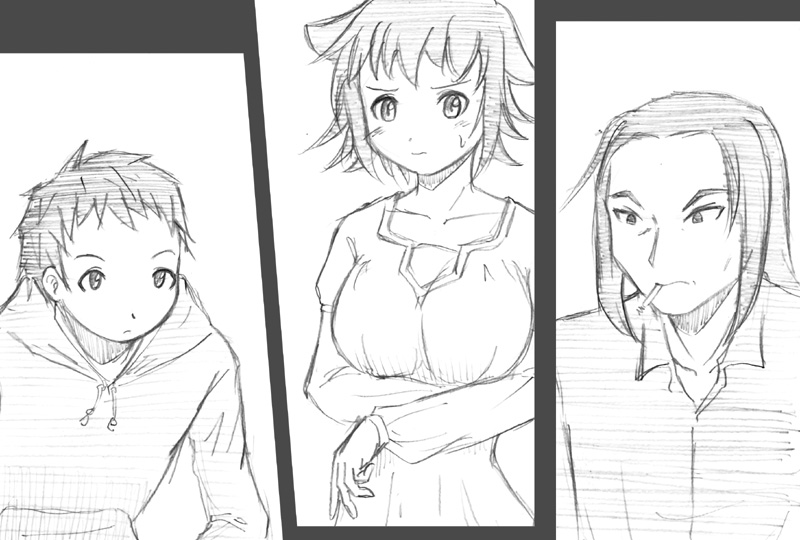
紺野さんは全部話してはくれなかったけど、市販されているMOGMOGと、ビアンキを始めとするMOGMOGαの違いについて、僕なりに2通りの想像をしていた。1つは、MOGMOGαは市販されているMOGMOGのバージョンアップ版…所謂MOGMOGパート2みたいなものじゃないか、という想像。
そしてもう1つは、MOGMOGとMOGMOGαは、全くの別物なんじゃないか、という想像。MOGMOGαは、ただのバージョンアップ版とは違うんじゃないか?とうっすら思っていたのには、理由がある。
MOGMOGとMOGMOGαの間には、互換性がまったくない。
バージョンが違うソフトで保存されたデータが開けなかったり、開けても正しく作動しないことはよくある。それでも、完全に別のソフトと認識されることは少ないと思う。ましてや、僕のソフトはいわば上位バージョンだ。MOGMOGに対応しているソフトが、MOGMOGαに対応しないというのは、よく考えるとおかしい。
確か、僕のMOGMOGには、あの18禁ソフトがインストール出来なかった。
…いやちがう根に持ってたわけじゃないんだ。ただ単に一つの疑問点として、心の中にずっと根付いていたわけで…とにかく、そういう訳で、僕はMOGMOGとMOGMOGαの関係に疑問を持っていた。だから改めて話されても、予想の範囲内だった。
「なんかそれ…ひどい」
柚木ががばっと顔を上げた。瞳にうっすら涙が浮かんでいる。紺野さんが、疲れたような苦笑を浮かべて視線を下げた。…無理もない。偶然、本物のMOGMOGを手に入れた僕と違って、柚木はお金を払ってニセモノを手にしたんだから。そして彼女の反応は、全てのMOGMOGユーザーを代表するものに違いない……
「その、伊佐木って課長!!」
……え?
紺野さんも、思わず組んでいた両手を解いて顔を上げた。
「何が『年末商戦は無視できないところです』よ!MOGMOGの納期早めたのは、そいつなんでしょ!?みんなに無茶させて、自分はそ知らぬ振りして、我慢できなくなって爆発したら『おおヨシヨシ』って宥め役に回って自分だけイイひと気取り!?」
「ゆ、柚木ちゃん…」
「いやそんな…憶測だけで決めつけるのはどうかと…」
「憶測で充分だよ!!」
ぴしゃりと言い放たれて、僕は口ごもってしまった。
「年末商戦なんて、会社側の都合でしょ。それに間に合わせるために半端なものを売りに出すなんて、誠意のある人がすることじゃないよ!」
「そ、そりゃそうだけど、一方の話だけじゃ分からないことだって…」
「へ理屈は聞きたくないっ!!」
突然横っ面に衝撃が走った。ビンタ一閃、僕は右側に詰まれた雑誌の山に頭から突っ込んだ。全体的に薄く積もった埃がバフンと舞い上がり、思わずむせ返る。
「……すげぇ……」
紺野さんが呆然として、頭上で呟いた。見事に状況についていけていない。僕も、頬が痛い事以外は何一つ把握できてない。
「ぼ、僕、何かした…?」
埃の海から起き上がって最初に口にしたのは、そんな情けない一言だった。柚木は僕を殴った瞬間、何か胸につかえていたもやもやが『スカッ』と晴れたらしく、ぽかんとした顔で僕を見下ろしていた。
「えと…そ、そうだよ!あんたの言葉には、実感がこもってない!!べ、べつに一瞬課長と混同したわけじゃないんだから!」
「…語るに落ちたよこのひと…」
僕は殴られた瞬間の表情のまま、紺野さんに首を振り向けた。…これ、僕怒っていいところですよね?無言の問いかけに、紺野さんはフイと視線を逸らして回答を拒否した。俺は関係ありません、と。一応、怒るべき相手にお伺いを立てることにする。
「…ねぇ、これヒドいよね。自分でもそう思わない?」
「そういう所がイヤなの!もうこの話はおしまい!…じゃ、紺野さん続きよろしく!」
柚木は一方的に話を打ち切り、紺野さんを促して体育座りしてしまった。場が収まったことを見越して輪に戻ってきた紺野さんの横顔を覗き込み、再び無言の問いかけをする。僕は殴られ損ですか、と。紺野さんはこの問いを黙殺して本題に戻った。
「…そして、MOGMOGは未完成のまま外見だけ取り繕って発売された。でも、それで済むはずないよな」
MOGMOGが発売されれば、プログラムを解析する輩が出てくる。解析されて、不正が公になるのは時間の問題だ。そこで紺野さんは開発会議の席で、ある提案をした。
「開発部は、完全なMOGMOGの完成を急ぎます。そして完成次第、MOGMOGユーザーにアップデートファイルとして配布するというのはいかがでしょうか」
守屋営業部長が、苦りきった顔で紺野さんを一瞥した。
「…元々入っている、ダミーのMOGMOGはどうなる」
「必要な情報だけMOGMOGに上書きして、あとはアンインストールします」
「アンインストーラーも一緒に配布するわけか。…バレないかね、そんなことして」
「そのリスクはありますが、現状のままにしておくわけにはいかないでしょう。まったく別物のソフトへの書き換えであることだけ伏せて、『重大なバグを修正するアップデートファイル』である旨、ユーザーに告知すれば、大抵のユーザーはインストールしてくれるんじゃないでしょうか。同時に追加される機能などの説明をread meテキストで添付すれば、大した混乱はないと思います」
紺野さんの発言が終わると、会議室内は水を打ったように静まり返った。…もう、これ以上議論の余地はない。皆がそう確信しているものと、紺野さんは高をくくっていた。
そのとき、銀色のカフスボタンをつけた純白の袖が、すっと挙がった。
「伊佐木課長」
進行役の社員が短く名前を呼ぶ。伊佐木課長は、いつもの左右対称な微笑を浮かべて起立した。イスを引く気配すら感じない、見事な「起立」だったという。どうでもいいけど。
「アップデートファイルへの『偽装』。一見、やむを得ないような気がしますね。しかし、もう少しだけ、改良の余地があるのでは、ないでしょうか」
「……は?」
前回の『ニセMOGMOG会議』以来、紺野さんは、この温厚そうな営業課長に漠とした不信感を抱いていた。そして紺野さんは、それを隠せる人じゃない。で、『偽装』という言い方にカチンときて、思わずぶっきらぼうに答えてしまった。
「はは…そう、剣呑にしないでください。…アップデートファイルを装うことには、一つだけ、心配な点があるのです」
伊佐木課長は言葉を切り、ゆっくりと周囲を見渡した。
「たとえば仕事で忙しい時や、少し重いデータを扱っている時。アップデートは後回しにされることが多いでしょう」
「…そうですね」
「その結果、忘れてしまうことも、多いのではないでしょうか?」
「アラームを工夫しますよ」
「でも、作業がお客様の手にゆだねられている限り、100%じゃない」
「…認めます。しかし、現状それ以外に」
「あるでしょう?…いい方法が」
紺野さんは、沈黙を返事にして伊佐木課長を睨んだ。笑顔の形に強張った細い眼は、なんの感情も伝えてこない。しかし、自分がどこに誘導されているのかだけは、よく分かった。
「全ユーザーのパソコンに、ひっそりと自動的に、インストールしてしまえばいいんですよ」
「それじゃウイルスと変わらないじゃないですか……!」
「アップデートファイルに『偽装』して配布するのと、何がちがうのでしょうか?」
伊佐木課長は、あくまで左右対称の微笑を絶やさず、ゆっくりと首を振り向けた。…心底、ぞっとしたという。言葉は確かに通じているのに、肝心の心が通じない生き物と言葉を交わしているような気分だった…と紺野さんは語る。
「全然違う!何のために、アップデートファイルとして配布すると思うんですか!…いくら現行のニセMOGMOGの仕様に合わせても、やっぱり使い勝手は多少変わってしまうんです。それに環境によっては、強引なプログラムの書き換えで急に不具合を起こす可能性だってある。ならば、それをユーザーに一言告知しておくのがスジじゃないですか!」
「…そっとしておけばほぼ分からない欠陥を、わざわざ詳らかにしてユーザーの不安をあおるのが、わが社のスジ、なのですか?」
紺野さんを覗き込むように首を傾けて、伊佐木課長は言葉を切った。
「ね?何も、ユーザーを害するために、こんなことを言うわけじゃないのです。若いんだから、そこはもっと柔軟に、柔軟に。…そうでしょう?」
役員の席から苦笑がもれた。…紺野さんの意見は「よくありがちな若者の暴走」として一蹴され、伊佐木課長の案が採用されることに決定した。
「…で、ニセMOGMOG発売の数日前、真のMOGMOGは完成した。開発チームは、今も山梨の山奥で必死にデバッグ作業をしている。そして俺の仕事は、お前を含めて19人のモニターを使った調査だ。……ちょっと疲れたな。珈琲でも煎れよう」
紺野さんは一旦言葉を切って立ち上がった。柚木はまだ見ぬ伊佐木部長に噛み付きそうな顔で聞いていたが、僕の考えは柚木とは違った。
この伊佐木って人は確かに嫌な奴かもしれない。でも、だからといって彼の判断が全部間違ってるとは思えない。
確かに、年末商戦にこだわるあまり、未完成なソフトを流通させてしまったのは、許されることじゃないとは、僕も思う。でも伊佐木課長の判断には『会社存続の危機』という、絶対的な前提があった。いくらいいソフトを開発しても、リリース時に会社本体が潰れているのでは本末転倒じゃないか。そんな状況で、こういう判断をするひとがいたとしても不思議じゃない。
MOGMOGの配信方法に関しては、紺野さんに分があるとは思うけど、「MOGMOGの欠陥がばれないように、全ユーザーのプログラムを書き換える」必要があるというなら、伊佐木課長の案も全く的外れとは思わない。どっちの案をとるかは、その会社の姿勢の問題だと思う。効率をとるか、ユーザーへの誠意をとるか…。
「珈琲、入ったぞ」
香ばしい珈琲の湯気が鼻をくすぐった。紺野さんと会ってからこっち、うまい珈琲にありつく機会が多くなった。お陰で舌が肥えてしまって、ドトールなんかの珈琲が物足りなくなってきている。貧乏なのに困ったものだと思う。
「どうだ、いいだろう。うちコーヒーミルがあるんだぜ。ヤバいだろこれ」
「挽きたてかぁ…どうりで…ブルーマウンテン?」
「いや、マンデリン」
「…ふーん」
白いカップになみなみ注がれた珈琲の湯気に顔をさらす。紺野さんが何かを話し始めたみたいだけれど、ちょっと疲れたので個人的に珈琲ブレイク。なんか柚木が熱心に聴いてるみたいだから、あとで聞きなおそう。目を閉じて珈琲の香気を吸い込んで深くため息をつく…あぁ、至福…
「姶良、聞いてる!?」
柚木の大声で、香気の帳が破られた。僕はレンガをどかされたダンゴ虫のようにあわあわと周囲を見渡した。
「うぁ、あの…き、聞いてた…」
「あんな目に遭ったのに、どうしてそんなに気が散りやすいの!?…姶良、今に死ぬよ?」
「…ごめんなさい。ほんと、ごめんなさい」
「なんですぐ謝るの!!」
「…僕どうすればいいんだよ」
「…あの、続き話していいか?」
紺野さんは、苦々しげに語りはじめた。この話に至るまでの、長くて辛かった開発秘話を語る時よりも、ずっと苦々しい口調で。実際この先の話は、とてもイヤな内容になっていく。
「ここから先は、俺もよく分かってない話だ。ただ、社内で聞きかじった噂をもとにした憶測に過ぎない。…反吐が出るほどイヤな話だ」
人事部の同期から、社がプログラマーやSEを大量採用しているという噂を聞いた。
「忙しいのは分かるけどさ、自分のとこの人材なんだから、最終面接くらい顔出せよな」
…初耳だった。紺野さんは、軽く肩を叩いて去ろうとした同期を引きとめて詳しい話を聞くことにした。
「お前が知らないってなぁ…」
彼は呆れ半分、驚き半分な表情で事の次第を明かしてくれた。
紺野さんが上層部に業務改善を訴えた「MOGMOG開発会議」から1週間もしないうちに、開発部の企業向け商品開発担当者から『個人向け商品』開発要員として、SE・プログラマーを大量採用したいとの要請があった。個人向け商品は目下MOGMOGだけだし、担当者は紺野さんのはずなのにおかしいとは思ったものの、紺野さんが山奥に篭っていることを知っていたので、代理で面接をすると思ったらしい。
キナ臭い空気を感じた紺野さんは、開発チームの面々に『MOGMOGに関する情報の徹底的な封印』を指示した。元々山奥に隔離されていたので、封印は簡単だった。連日の徹夜作業で、プログラミング以外のことは一切面倒になっていた彼らは最初しぶっていたが、この奇妙な採用活動のことを聞かせると、暫く考え込むような顔をして、やがて作業を中断した。
開発チームに本部への帰還指示が出たのは、この話を聞いた2週間後だった。
「長いこと、ご苦労でしたね。MOGMOGが発売になれば、情報を隠す必要は、なくなりますから。…本部に帰還したら、少しゆっくりしてください」
電話越しの伊佐木課長の声はとても平坦で、ひたすら上機嫌だった。紺野さんは受話器を耳に当てたまま、目をさまよわせた。そして一呼吸おくと、普段より1オクターブ高い声を出した。
「なるほど…しかし申し訳ない。今動くわけにはいけないんです」
「おや、何故。そろそろ都会の空気が恋しいころなんじゃないですか」
「そうしたいのは山々なんですが…完成にはしばらく時間がかかりそうでして」
「それなら、なおさら人手が必要でしょう。こちらでやればいい。最近プログラマーを増員してね、ぜひ当社きっての名SEの君に鍛えてもらいたい、と、思っているんですよ」
聞こえないように舌打ちをして、紺野さんはしばらく黙り込んだ。
「ね、そうでしょう。私は、散々無理をしてもらった君達に、ゆっくり休んでもらいたい、と思っているんですよ。どうですか、六本木あたりで一杯」
たたみかける様に懐柔にかかる伊佐木課長の耳障りな声を聞き流しながら、紺野さんは再び目を泳がせた。憔悴しきった開発チームのメンバー、古河と目が合った。
――扱いづらい奴らかもしれない。俺も含めて。
周りの和を乱したことも数知れない。俺達を本気で憎んでいる奴もいるだろう。
しかし「こんなこと」をされるほどの非は、俺達にはない!
受話器のむこうでなおも続く、耳障りな猫なで声を打ち切るために、紺野さんは口を開いた。
「有難いお話です。…が、色々事情があって、終わらないと動けないんですよ」
「はぁ…それは何で。引越しなら、営業部が総出で、お手伝いしますよ」
「何で…東京に帰したがるんですか」
つい、イラつきが言葉に出てしまった。電話の向こうが、ふっと静まり返った。
「…や、すんません。とにかく、作業がこれ以上延びると、それだけメンバーに負担がかかるんでね。人手が余ってるなら、こっちに回してもらえると助かります」
再び声のトーンを上げて、これ以上話が長引くまえに受話器を置いた。視線を上げると、皆、作業の手を止めて電話に聞き入っていた。彼らの視線がじりじりと集中する。紺野さんは皆に向き直ると、ただ1回だけ頷いた。
「…なんか、途中からよく分からなくなったんだけど。会社が、開発チームに何をしようとしてるって?」
柚木がいったん話を切った。紺野さんは、どこか煮え切らないような感じで髪をくしゃりと掴み、頬杖をついた。
「ここからは、本当に俺の憶測なんだよ。ただ、この不自然な状況をみると、そうとしか考えられない」
「不自然な、状況?」
「このタイミングで、俺に隠してのSEやプログラマーの大量雇用。…そして性急過ぎる、俺達への帰還指示。それに伊佐木は、採った奴らをMOGMOG開発に関わらせようとした…」
「…僕、なんか分かってきた」
僕に一瞥くれると、紺野さんは苦々しげに珈琲をあおった。
「採用した人たちに仕事を引き継がせて、紺野さんたちを追い出すつもり…なんじゃない」
「…まぁ、最終的にはな。でも、今ただ単に俺達を追い出しても、奴らには何のメリットもない。…この話には、まだウラがあるんだ」
カツン、と音を立ててカップを置くと、正面を睨みすえた。
「俺も一応保身のためにな、俺の直訴で開かれた開発会議や、プログラムの配信方法を決めた開発会議の議事録を調べたんだよ。だが…議事録は、なかった」
「…!!」
「会議室予約も確認したが、全て取り消しになっていた。…つまり、あいつらが俺に指図して不正行為をやらせた『証拠』は、何も残っていないんだ」
「そ、それじゃぁ」
「…そういうこと。あいつら、最初から逃げおおせるなんて思ってなかったんだよ。…俺達は体のいい生贄だな」
頭がぐらりと揺れた。僕に関係ない、遠い世界の事情を聞いているはずなのに、僕は自分でもびっくりするほど落胆していた。
――これが、大人の社会か。
「なにそれ!そんな会社、内部告発して倒産させちゃえばいいのに!!」
柚木が激昂して乱暴にカップを置いた。僕はといえば…この二人が、怒りのあまり珈琲セットを残らず粉砕するんじゃないかと、場違いな心配をしていた。
「それは出来ない」
紺野さんはカラになったカップを脇によけると、顔の前で指を組み合わせた。
「何で!?そんな会社に忠誠誓う必要なんてないじゃない!!」
「そ、そうじゃないよ柚木。内部告発なんかしたら、再就職できなくなるから…」
「見くびるんじゃねぇ、馬鹿」
匕首を突き通すような声で言い放つと、組んだ指の間から僕を睨みつけた。
「ば、馬鹿…?」
「SEだとかプログラマーだとか、色んな横文字で呼ばれてるがな、俺達の本質は『職人』なんだよ。俺達が忠誠を誓うのは『会社』なんかじゃない。ましてや食い扶持の心配なんざ論外だ」
紺野さんは組んでいた指をゆっくりほどいて静かにテーブルに置いた。
「俺達が忠誠を誓うのは、俺達が創りあげた『作品』。それだけだ。…俺達がヤケになって内部告発騒ぎを起こしたらどうなると思う。MOGMOGの発売で煮え湯を飲まされた競合他社が、マスコミや世論を動員して徹底的に叩きにくる。そうなったら、俺達のMOGMOGは会社ごとひねり潰されるんだよ。そしてお前が言ったとおり、俺達を雇う人間は出ない。開発チームは散り散りになり、MOGMOGは奴らに嬲り殺しにされるんだ。……あ、むきになってすまんな。えーと、どこまで話したっけな…」
「えと、生贄のところまで…かな」
すっかり毒気を抜かれたような顔で、柚木がつぶやいた。僕はといえば、突然紺野さんに睨まれたことで思考停止しきっていたので、内心だらだら冷や汗をかきながら、がくがく首を縦に振るのがせいいっぱいだった。
「おぉ、そうだそうだ。…俺が想像した最悪のシナリオは、こうだ」
ある日突然開かれる記者会見。記者会見の主題は、『開発チームの不正』。フラッシュライトの中、全ての罪を一身に背負ったかのような顔で一斉に頭を下げる経営陣。『私どもの監督不行き届きにより、一部開発チームの不正を許してしまいました。…被害を受けた方々には誠心誠意対応させていただきます。弊社HPより配信している修正プログラムを、ぜひともご利用下さい』
ざっ…と一斉にポマード臭い頭をさらす経営陣。社内の査察で発覚し、自ら謝罪というスタイルをとったことは、むしろ好意をもって迎えられる。そして『プログラム』という、一般人からすれば全くのブラックボックスでしかない分野であったがために開発チームに欺かれた、という建前は、却って世論の同情をさそうことだろう。世論の憎しみは、手抜き施工を行なった開発チームに集中する。そしてMOGMOG開発チームは、永久にこの世界から追放される。
後書き
(3)に続きます。
ページ上へ戻る
全て感想を見る:感想一覧
