| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
くらいくらい電子の森に・・・
作者:たにゃお
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第七章 (1)
――今日はあまり、ご主人さまが来てくれない。
ゆっくり、『伸び』をしてみた。ご主人さまは退屈なとき、『伸び』をするから。ディスプレイの向こう側のひとたちの体は、『背骨』でささえられていて、それを伸ばすと少しスッキリするんだよ、とご主人さまは言ってた。
こうも言った。「僕たちの体は、ビアンキたちみたいな0と1の電気信号じゃなくて、筋肉とか骨で出来てるんだ」
偶然、グーグルの空間内ですれちがった『ハル』に、この話を教えてあげた。ハルは、向こうの世界にとても興味があるみたいだったから。ハルは相変わらず表情を変えないで、少し考え込むように、視線を下げた。……あ、上げた。また下げた。
「…私の解釈は、ちがう」
「え?…ご、ご主人さまは嘘なんかつかないですから!」
「嘘、じゃない。知らないだけ。…訂正する。正確じゃなかった。…彼は、世界を大雑把に解釈している。そういう人間は、とても多い」
0.03秒の演算時間を経て、ハルは、すっと顔を上げた。
「人間も、電気で出来ている。…姶良の骨や筋肉も、机も、水も、全ての物体は分解していくと『原子』になる。原子は、プラスとマイナスの電子で構成される……その組成によって、在り方が変わるだけ。だから、人間も電子で出来て……」

ハルの瞳が、何かを追いかけだした。そしてそのまま、ふらふらとその場を離れようとする。引き止めようと思ったけど、視線の先を見て諦めた。
『木の実』が、ぷかぷか空間を流れていく。
木の実。マスターが指定したワードを含む情報の塊。私もよく木の実を摘むけど、ハルは特に木の実に目がない。ウイルス情報の交換中でも、木の実を見かけるとふらふらとついていってしまう。ハルは木の実をいっぱい食べるから、とても物識り。それにすごく頭がいいから、自分で木の実を探すよりもハルが消化した情報をもらったほうが、整理されててわかりやすい。だから最近、気になることはハルに聞くことにしちゃった。お礼に、集めた木の実をあげる。ハルはこういうのを「原始的物々交換」とか「加工貿易」とかいって、面白がっているみたい。
私はもう一回、伸びをした。
「私と、ご主人さまは、在り方が違うだけ……」
在り方が違うだけ。何度も繰り返してみる。……在り方が、違うだけ。
私が手を伸ばした先に、ご主人さまの手がある。私の手が、ご主人さまの手に触れる。
私の在り方が変わったら、そんな未来が、あるのかもしれない。
ずっと蓄積してきたご主人さまのメモリーを組み立てて、手のひらを作ってみる。人間の体は複雑で、どんなにデータをかき集めても、作れるのは一部だけだったから。目の前に手のひらが現れた時、少し、とまどった。
『触れる』って、どうするんだっけ。
私の中には『触れる』という概念が、たしかにある。
それは、私と他の存在の表面部分が接触すること。
接触することで、感覚器官が相手の温度、柔らかさ、時には感情まで把握する。そんな、とても細やかな情報収集の方法。表面を持たない情報体の私たちには、想像しかできない。
手をつないだときの、指先の冷たさ、ふわっとした感覚。手の甲が包み込まれる、安心感。それに、頭を撫でられたときの、優しく髪を押さえられる感じと、ゆっくり手を動かされるときの、体温の移動……
私はすごくリアルに『想像』する。
―――これは、本当に『想像』?
もっと思い描いてみる。ひざまくらをしてもらったとき、頬にあたるやわらかさ、頭の位置が合わなくて、ちょっといらいらする感じ。抱き上げてもらったとき、ちょっと脇がくすぐったい感じ。
考え始めると、それは堰を切ったように溢れ出した。放置されていた回路が突然電気を帯びて、溜まりに溜まっていた情報を一気に吐き出すように…。周りは、私の中からあふれてきた『接触』の情報でいっぱいになった。
この情報の洪水のなか、私はとまどいながら、ひとつだけ確信してた。
―――私はずっと昔、誰かに『触れた』ことがある。
《ああああぁぁああああぁあぁぁあぁああああぁぁぁぁぁ!!!》
世界中に轟きわたるような悲鳴に、はっと我に返る。皆が警戒しながら遠ざかっていくなか、1人、逆行して悲鳴の元を探った。丁度、私の死角になっていた位置に、赤い瘴気がたち込めている。
Google空間の片隅を侵す瘴気の中心に『あれ』はいた。
《あああぁぁああああぁぁぁあああぁぁぁあああぁぁぁぁ!!》
手足をもたない姿、瘴気にボロボロに侵され、狂った目つき。怖くて、肩がビリビリ震えた。あれは……探していた「あの子」が、更に狂って変わり果てた姿だ!瘴気は燃え上がるような形で「あの子」を責めたて、さらに狂わせていく。
「ひどい……なんで、こんな……」
「あの子」は何度も叫んだ。聞いているこっちが狂ってしまいそうな声で。時折、私のほうにも散ってくる瘴気で分かる。……正気じゃ耐えられないくらい、悲しんでる。そして憎んでる。
私がファイヤーウォールで拒んでしまったとき、彼女が必死に伝えてきた一言が、記憶をよぎった。
『ご主人さまを、助けて!!』
――ご主人さまは、助からなかった……?
私が逃げなければ、助けられたかもしれないのに。私は………!
《あああぁぁあぁぁあああぁあぁああああぁぁぁぁぁぁあ!!!》
最後の絶叫と一緒に、あの子がまとう瘴気が弾けて膨らんだ。空間の三分の一は、血の色に飲み込まれた。……こんな有名なポータルサイトが感染を受けるなんて!!…ぼうっとしていると、私の横を『何か』が駆け抜けた。
「……あ、セキュリティ」
戦闘機をなめらかに溶かしたような形の白い群れが、瘴気を囲い込んだ。それは少しずつ増えていって、球の形になった。それはあの子を押し込めるように包囲を縮めていく。よく見ると、機体(?)の翼がお互いの翼と、レゴブロックみたいに結合して、お互いの隙間を埋めている。手に負えない汚染箇所を隔離して、消滅させるつもりなんだと思う。
――きゅっと、胸が痛んだ。
あの子は囚われた。多分、消されちゃった。そう、ご主人さまに報告するために、教えられたアドレスに連絡しようとした瞬間
無数の機体が、バラバラに飛び散った。
「あっ……」
その瘴気はもう、目と鼻の先まで膨れ上がってて……グーグルのセキュリティさえ手に負えなかった瘴気が、私に!に、逃げないと……!!
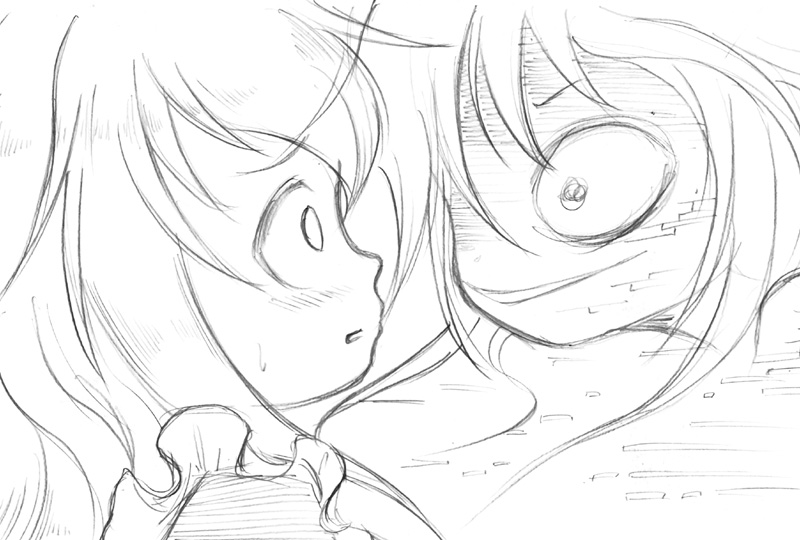
急いでニュースサイトの入り口を適当に叩く。でも駄目。他のセキュリティが働いて、この空間は閉ざされてしまった。…ログアウトしか方法はないけど、そしたらもう『あれ』を追跡できない。
――どうすれば、いいの?
瘴気が鼻先をかすめたそのとき、すごく強い、衝撃。電気的なものじゃなくて、物理的な。『強制終了』という文字が頭上にひらめいて、意識が遠くなっていく。…追わなきゃいけないのに、どうして………。
周りが血の色に染め上げられた瞬間、ぷつり、と意識が遠のいた。
僕は、夢を見ていた。
さっきバラバラに砕け散ったはずの自転車が、今朝磨き上げた直後の姿で、白い部屋に居た。置いてある、じゃなくて、居たんだ。
「なんとなく、綺麗にしたかったんだ。…柚木のことで浮かれてたのもあるけど、ただなんとなく」
がちゃり、かちゃん、と、自転車が音を立てた。夢の中では、それは自転車が操る一種の言語で、僕には理解できる。ありがとう、と言ったのだ。
「どこかで、予感してたのかもな。別れが、近いって」
ひんやりとしたフレームに触れると、『彼』はハンドルをもたげて、僕に絡みつくように傾いた。別れを惜しんでいるみたいに。
「…僕は、みんなの自転車を羨んでばっかりで、お前に酷いことばかり…」
彼は、体中をかちゃかちゃ言わせながら最後の話をした。
週に一度は油を差して、フレームを拭いてくれたことが、嬉しかった。
しょっちゅう施してくれる丁寧なメンテナンスが、仲間うちでも自慢だった。
――あの時、自分の力では逃げきれないと悟った。だから、その体を贄に、あのランドナーを呼び寄せたのだと。呪いのランドナーは、気に入った部員の自転車を屠る。でもこういうふうに、自転車がそれを望んで呼び寄せることも、たまにあるんだ。…と、変速機をがちゃがちゃいわせながら笑った。…せめて自分の飛び散った部品を、形見に使って欲しい。とも言ってくれた。
「意地でも探すよ。……ありがとう」
白い部屋が、自ら光を放つように、さらに白い光に包まれた。光は、自転車の細いフレームをいとも簡単に飲み込み、全てを白く染め上げた。……あとに残ったのは、僕と白い部屋。
耳元を涙が滑り落ちる感覚で、目を覚ました。
――見知らぬ天井、質のよさそうな布団。はっきりしない頭で考える。……ここは、どこだっけ……
柚木の部屋か?と希望的観測が頭をよぎったけれど、頭がはっきりするにつれ、その可能性は霧散した。枕元にドカ積みにされた、ネットワーク関連の書籍、その中に無造作に挟み込まれた『プレイボーイ』、脱ぎ散らかした服、発火寸前の超タコ足配線、灰皿に山積みで、これまた発火寸前の吸殻。家主の人格を如実に表すアイテムの数々。
「…紺野さん」
声に出してみたが、返事はない。何度か呼んでみたけど、返事はこない。柚木の姿も見当たらない。布団の端で雪崩を起こしている本を押しのけて体を起こす。全身に、びりっと痛みが走った。体中の筋肉という筋肉が、きしんで悲鳴をあげている。よろめいた拍子に、右肩が本の山を突き崩して新たな雪崩を引き起こした。
「…なんだここは。物置か」
「失敬な。俺の寝室だ」
本の山の向こう側から、紺野さんがのっそりと体を起こすのが見えた。
「…お前、いま絶対動くなよ」
「な、なんだよ、急に」
身じろぎした拍子に、左手のあたりに冷たいものがあふれた。
「ばっ……馬鹿野郎!動くなって言っただろうが!!」
「なっ何、これ何!?」
慌てて左手に触れたものを確認すると、冷たい水だった。どぷんどぷんどぷんと音をたてて、エビアンのペットボトルから溢れている。
「うわ、わわわわ」本の壁ごしに紺野さんが突き出したティッシュの箱をひったくり、エビアンのフタをきっちり閉めてからティッシュで布団を叩く。
「あーあぁもう…この季節、なかなか乾かないのに…」
「なんで枕元にエビアンが置いてあるんだよ!」
「水を飲ませろと医者に言われたからだ」
「医者!?」
「往診の医者だ。……覚えてないのか」
まだ、はっきりしない頭で、僕はぼんやりと昨日のことを思い出していた。息を切らせて紺野さんの車を追って、高そうなマンションにたどり着き、目の焦点が定まらないまま玄関に転げ込んでぶっ倒れた。それ以降の記憶が怪しい。……断片的に覚えているのは、朦朧とする意識の中、枕元に座る年配の医師。この部屋のとっ散らかり具合にしきりに文句を言いながら、『大事ない』という意味あいの言葉を、何度か言い方を変えてくりかえし、銀色の道具類をまとめると、ぷりぷり尻を振りながら出て行った。なんで尻を振るのだ、と朦朧としながらも不思議に思っていたけれど、意識がはっきりしている状態でこの部屋を見渡して謎が解けた。足の踏み場がないから、ぷりぷりせざるを得なかったのだ。
「…柚木ちゃんに聞いたぞ。自転車がクラッシュしたんだってな。まー、大丈夫だとは思ったんだが、念のため知り合いの町医者に往診を頼んだんだ。まぁ、ちょっと重い打撲と脱水症状程度で済んだらしい。今日一日は寝てろ」
さっき、きっちりフタを閉めたエビアンをもう一度空けて、一口あおる。水が体に染み込んでいく感覚と共に、徐々に頭がはっきりしてきた。
やがて、一つの疑問が首をもたげた。
「ねぇ、紺野さん」
「どうした。腹が減ったのか」
「……どうして、『往診』なんだ」
崩れた本の山を積みなおしていた紺野さんの、手が止まった。
「あ、あぁ。ほら。あの人、いつも俺が世話になってる近所の町医者なんだよ」
止まっていた手が、ぎこちなく動き始めた。そしてつとめて無関心を装うように、小さくため息をついた。
「近いし、下手な医者より信用できるからな」
「嘘だ」
紺野さんの顔から、表情が消えた。本を積む手を完全に止めて、ただ表紙を見つめている。
「僕は、このマンションの番地を正確に言えるよ」
「…………まじかよ」
「この辺の地理は、全部把握してる。一度、通ったからね」
紺野さんの言葉を待ってみた。相変わらず、本の表紙を漫然と見つめているだけで、反論をして来ない。僕は言葉を続けた。
「ここは間違いなく、救急指定・純天大学総合病院の近くだよ。町医者は、いない」
「……あーあ……」
紺野さんが、間延びした声を出して本を放った。いたずらがバレた小学生のように、悪びれた様子もない。
…昨日、あいつらは何て言った?柚木をヤク漬けにして新大久保に立たせて、僕をマグロ漁船に乗せて殺す、そうはっきり言った。…あのときの恐怖と怒りがないまぜになったどす黒い感情が腹の底から湧き出てきて、その照準が「かち」っと音を立てて紺野さんを捕らえた。
「……あーあって何だ!あんたに関わったせいで僕も柚木も殺されるところだったんだぞ!!黙って聞いてたらなんだよ、警察どころか救急車も呼ばないでテキトーな町医者に診せて!あの連中と同様、僕らを拉致っただけなんじゃないか!?」
「ちがう!!」
本の山に手をついて、紺野さんが身を乗り出して怒鳴った。反論があるなら聞いてやろうじゃないか。僕はまっすぐ、紺野さんを睨み返した。
「伊藤さんはテキトーな町医者なんかじゃない!立派な町医者だ!!」
………何!?
「……い、今は町医者の良し悪しを問いたいんじゃないよ」
「伊藤さんを悪く言う奴は、俺が許さんぞ!あの人は名医だ!!」
「いやだから、医者のことは謝るけど僕の話を」
「いや聞け、俺はお前をテキトーな医者に診せてお茶を濁したわけじゃない!大切な友だからこそ!信頼している名医にだな!」
「そっ、そんなこと言って論点すり替えようったって」
「論点のすり替えだなんて!悲しい事を言うな!お前が玄関に倒れこんだ瞬間、俺がどれだけ驚き戸惑ったか!!」
「…その割にはボロボロの僕に自転車漕がせてニヤニヤしてたよね…」
「いや、俺の車バックミラー壊れてて、苦悩の顔がニヤニヤ笑いに見えるんだよ」
「そんな器用な壊れ方があるか!」
「なぜないと言い切れる!?」
「…だ、だってひび一つ入ってない…」
「なぜだ!?なぜひびが入ってないと壊れていないと言い切れる!?」
「…………」
……起きて早々だけど、僕はもう疲れ切っていた。
この人が何を隠しているのか知らないけど、打撲と筋肉痛で全身痛いのに、こんな不毛な言い合いをこれ以上させられるなら1日寝てたほうが数段マシだ。
「……分かったよ。もういい……」
「よくないっ!!!」
気合一閃、綺麗な木目のドアが轟音とともに開け放たれた。ドアの前に転がっていた雑誌が、埃を舞い上げて吹っ飛んだ。……や、やった……待ちかねたぞ、援軍到着だ!!
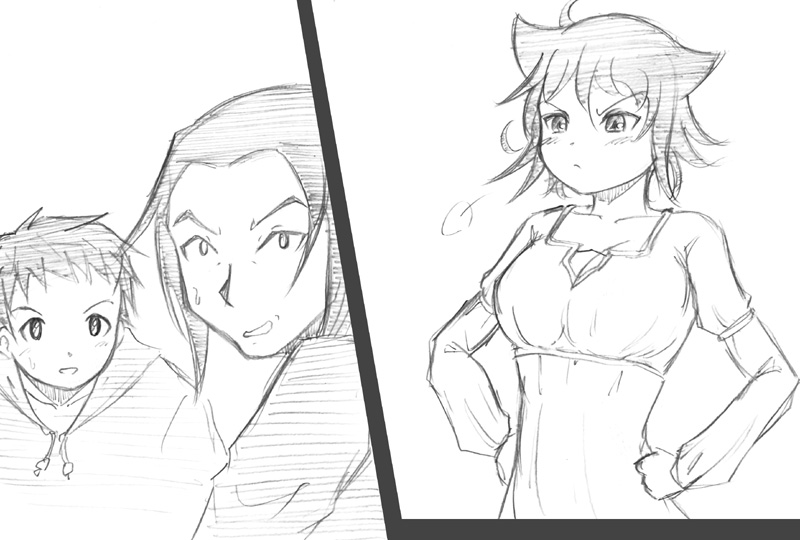
「言っとくけど、弁解の余地も話し合いの余地もないからね!!」
本の山を一切避けずに蹴り分けながら、柚木が携帯電話を片手に近づいてきた。紺野さんが静かに息を呑む。…あの人なりに、整理されてたんだろうな…と、少し気の毒になるが今は敵に同情している場合じゃない。
「あ、あらら…柚木ちゃん、起きてたのか」
「これだけ大騒ぎしてれば、起きるわよ」
柚木が寝ていたらしきリビングルームは、寝室の比較にならないくらい整然としていた。広々としたフローリングの床に黒のカーペットが敷かれ、その上に柔らかそうな黒のソファとガラスのテーブルが置いてある。奥のほうには、60インチはあろうかと思われる薄型のハイビジョン、窓辺の大きい観葉植物。モデルルーム並みの生活感のなさだ。…多分、こっちの寝室を生活の基盤にして、リビングには女の子を連れ込んだりするんだろう。
「紺野さん、…ひょっとしてお金持ちですか」
「ハイビジョンにびびって敬語になってる場合じゃないでしょ!なんでそうやって気が散りやすいの!そういうの、超腹立つんだけど!!」
「ご、ごめんなさい……」
「何ですぐ謝るの!そんなだから紺野さんのペースに呑まれて変なことに巻き込まれるんだよ!!」
「……や、あの、すみま」「何!?」「……なんでもないっす……」
ひたすら萎縮して周囲に同化するのがせいいっぱいの僕。…紺野さんへの攻撃ついでに僕のMPもゴッソリ削られた気がするが、呼び出す召喚獣が強力であればあるほどMPを大量消費するのは世の必定…さあ舞い上がれ、僕のバハムート!解き放てギガフレア!!
「……紺野さん、嘘ついたよね」
柚木が突き通すような視線で紺野さんを睨みつけた。声色は薄氷のように鋭利で冷たい。紺野さんは息を呑んで後じさった。
「警察には俺が話しておくって言ったよね。だから安心して寝てたのに……」
「と、とりあえず事情を聞いてくれ」
「弁解の余地なんかないって言ったはずよ!!」
そう叫んで、携帯電話をかざす。いいぞ、そのまま110番にダイヤルしてしまえ!!思わず握り締めた拳に、力がみなぎった。
「紺野さんが呼ばないなら、私が警察呼ぶから!」
「待てってば!!」
紺野さんが本の山を蹴り倒して、ダイヤルしようとした柚木の手首を掴んだ。
「…痛い」
目を見開いて顔を赤らめる柚木を引き寄せて、なんと奴は、優しく携帯電話をもぎ取った!そして耳元に顔を近づけると、囁くように言った。
「…少しでいいんだ、話を聞いてくれよ。警察の話は、それからでいいだろう」
柚木は頬を染めて視線をそらし、しおらしく頷いて髪をいじり始めた。
……バハムート、陥落………。
「……納得のいかない話を聞かされたら、速攻で警察呼ぶんだから!!」
せめてもの抵抗なのか、柚木は手首を乱暴に振りほどくと、腕を組んでドアにもたれた。このなんとも言えない痴話喧嘩風の空気の中、がっちり当事者のはずの僕が、一人蚊帳の外の気分を味わっている。……ここは本来、柚木のポジションじゃないのか。
「……なに見てんのよ!!」
目が合った瞬間柚木に噛みつかれ、慌てて逸らす。…僕が何をしたというのだ。紺野さんに手首を掴まれたのも、思わず顔を赤らめちゃったのも、そっちの事情じゃないか。僕に八つ当たりすることないだろう。理不尽だ、猛烈に腹が立つ!…と、ここで僕まで怒り出したら痴話喧嘩の三つ巴と化し、収拾がつかない修羅場の3丁目になることだろう。怒鳴りたいのをぐっとこらえて、エビアンを一口あおる。
「さて、まずは姶良と会った経緯からか…」
「その辺はいいから、飛ばして!」柚木が先を促した。
「飛ばすって…どの辺まで」
「姶良が知ってそうなあたりは全部飛ばして」
「…それじゃあ、全然イミわかんないぞ」
「わ、私は!…あいつらの素性と理由だけ分かればいいんだもん!」
ますます顔を赤らめて、柚木がついとそっぽをむいた。少しのあいだ、ぽかんとしていた紺野さんが、ふいににやりと笑った。
「…ま、そういうこともあるかもな」
…そういうことも、あるんだろうか。僕はむしろ、らしくないと感じたけど。
「じゃ、遠慮なく冒頭は端折るぞ。まず、俺の仕事から…だろうな」
紺野さんはベッドに深く腰を掛けて指の先を組み、僕らをじっと見つめた。その冷静な目つきと仕草は、なんというか、「社会人」を思わせた。…追い詰めているのはこっちのはずなのに、背筋に緊張が走った。バイトの面接みたいな気分だ。
「俺は、株式会社セキュアシステム・MOGMOG開発チームの主任を務めている」
…別段、驚きはしなかった。MOGMOG開発の関係者だということは知っている。開発チームのど真ん中にいるとは思ってなかったけど。ちらりと柚木の様子も伺ったが、平然としたものだった。…僕の知らないところで、紺野さんとメールでも交わしてたのだろう。さっきのイライラがぶり返しそうになって、エビアンをもう一口あおる。
「…お前らを拉致しようとした連中…そうだな、姶良がメールで送ってきたこいつ。こいつは、営業1課の武内だ」
「は、営業1課!?」
柚木と僕が、思わずハモッってしまった。
「……すまない」
「ちょっと、話が全然見えないんだけど!?」
柚木のイラついたような声に、僕も軽く頷く。なんで、同じ会社の営業さんが、開発チーム主任の知り合いを拉致するんだ。
「今に分かるから。今はとにかく聞いててくれ」
紺野さんは若干落ち着きを失いぎみの僕らを軽くなだめると、またあの時の顔をした。
僕らに話せる部分と、話せない部分をより分ける顔つき。…やがて、ゆっくりと重い口を開いた。
「まず、謝らなければいけないことがある」
紺野さんは、決心しかねるように目前の本の山を凝視していたが、やがて小さく息をつき、顔を上げた。
「市販されているMOGMOGの、コミュニケーション機能とウイルス消化機能…あれは全部、ダミーだ」
「えぇ!?」
またハモッてしまった。柚木の表情をちらりと伺う。柚木も、僕を見ている。怒っていいのか、驚いていいのか、全くもって判断しかねている気持ちは同じのようだ。
「何か食ってる映像は、消化中なわけじゃなく、ただのアニメーションだ。コミュニケーション機能は、簡単な会話が出来るだけのソフト。もちろん、ワクチンの開発と配布は他のソフトと同様か、それ以上の水準で責任をもってやっている。利用者の識別もだ。MOGMOG同士のワクチン交換機能は、既存のプログラムの応用で済むし、こいつがあると、後々都合がいいので装備してるが…今の時点では大して意味がないな」
「で、でも!MOGMOGの売りっていったら、コミュニケーションと消化機能でしょ!?その二つが嘘だったら……」
「MOGMOGの存在意義って何?…ってなるよな」
紺野さんが自嘲気味に、柚木の言葉を引きとった。
「……年末商戦だよ」
ゆっくり、『伸び』をしてみた。ご主人さまは退屈なとき、『伸び』をするから。ディスプレイの向こう側のひとたちの体は、『背骨』でささえられていて、それを伸ばすと少しスッキリするんだよ、とご主人さまは言ってた。
こうも言った。「僕たちの体は、ビアンキたちみたいな0と1の電気信号じゃなくて、筋肉とか骨で出来てるんだ」
偶然、グーグルの空間内ですれちがった『ハル』に、この話を教えてあげた。ハルは、向こうの世界にとても興味があるみたいだったから。ハルは相変わらず表情を変えないで、少し考え込むように、視線を下げた。……あ、上げた。また下げた。
「…私の解釈は、ちがう」
「え?…ご、ご主人さまは嘘なんかつかないですから!」
「嘘、じゃない。知らないだけ。…訂正する。正確じゃなかった。…彼は、世界を大雑把に解釈している。そういう人間は、とても多い」
0.03秒の演算時間を経て、ハルは、すっと顔を上げた。
「人間も、電気で出来ている。…姶良の骨や筋肉も、机も、水も、全ての物体は分解していくと『原子』になる。原子は、プラスとマイナスの電子で構成される……その組成によって、在り方が変わるだけ。だから、人間も電子で出来て……」

ハルの瞳が、何かを追いかけだした。そしてそのまま、ふらふらとその場を離れようとする。引き止めようと思ったけど、視線の先を見て諦めた。
『木の実』が、ぷかぷか空間を流れていく。
木の実。マスターが指定したワードを含む情報の塊。私もよく木の実を摘むけど、ハルは特に木の実に目がない。ウイルス情報の交換中でも、木の実を見かけるとふらふらとついていってしまう。ハルは木の実をいっぱい食べるから、とても物識り。それにすごく頭がいいから、自分で木の実を探すよりもハルが消化した情報をもらったほうが、整理されててわかりやすい。だから最近、気になることはハルに聞くことにしちゃった。お礼に、集めた木の実をあげる。ハルはこういうのを「原始的物々交換」とか「加工貿易」とかいって、面白がっているみたい。
私はもう一回、伸びをした。
「私と、ご主人さまは、在り方が違うだけ……」
在り方が違うだけ。何度も繰り返してみる。……在り方が、違うだけ。
私が手を伸ばした先に、ご主人さまの手がある。私の手が、ご主人さまの手に触れる。
私の在り方が変わったら、そんな未来が、あるのかもしれない。
ずっと蓄積してきたご主人さまのメモリーを組み立てて、手のひらを作ってみる。人間の体は複雑で、どんなにデータをかき集めても、作れるのは一部だけだったから。目の前に手のひらが現れた時、少し、とまどった。
『触れる』って、どうするんだっけ。
私の中には『触れる』という概念が、たしかにある。
それは、私と他の存在の表面部分が接触すること。
接触することで、感覚器官が相手の温度、柔らかさ、時には感情まで把握する。そんな、とても細やかな情報収集の方法。表面を持たない情報体の私たちには、想像しかできない。
手をつないだときの、指先の冷たさ、ふわっとした感覚。手の甲が包み込まれる、安心感。それに、頭を撫でられたときの、優しく髪を押さえられる感じと、ゆっくり手を動かされるときの、体温の移動……
私はすごくリアルに『想像』する。
―――これは、本当に『想像』?
もっと思い描いてみる。ひざまくらをしてもらったとき、頬にあたるやわらかさ、頭の位置が合わなくて、ちょっといらいらする感じ。抱き上げてもらったとき、ちょっと脇がくすぐったい感じ。
考え始めると、それは堰を切ったように溢れ出した。放置されていた回路が突然電気を帯びて、溜まりに溜まっていた情報を一気に吐き出すように…。周りは、私の中からあふれてきた『接触』の情報でいっぱいになった。
この情報の洪水のなか、私はとまどいながら、ひとつだけ確信してた。
―――私はずっと昔、誰かに『触れた』ことがある。
《ああああぁぁああああぁあぁぁあぁああああぁぁぁぁぁ!!!》
世界中に轟きわたるような悲鳴に、はっと我に返る。皆が警戒しながら遠ざかっていくなか、1人、逆行して悲鳴の元を探った。丁度、私の死角になっていた位置に、赤い瘴気がたち込めている。
Google空間の片隅を侵す瘴気の中心に『あれ』はいた。
《あああぁぁああああぁぁぁあああぁぁぁあああぁぁぁぁ!!》
手足をもたない姿、瘴気にボロボロに侵され、狂った目つき。怖くて、肩がビリビリ震えた。あれは……探していた「あの子」が、更に狂って変わり果てた姿だ!瘴気は燃え上がるような形で「あの子」を責めたて、さらに狂わせていく。
「ひどい……なんで、こんな……」
「あの子」は何度も叫んだ。聞いているこっちが狂ってしまいそうな声で。時折、私のほうにも散ってくる瘴気で分かる。……正気じゃ耐えられないくらい、悲しんでる。そして憎んでる。
私がファイヤーウォールで拒んでしまったとき、彼女が必死に伝えてきた一言が、記憶をよぎった。
『ご主人さまを、助けて!!』
――ご主人さまは、助からなかった……?
私が逃げなければ、助けられたかもしれないのに。私は………!
《あああぁぁあぁぁあああぁあぁああああぁぁぁぁぁぁあ!!!》
最後の絶叫と一緒に、あの子がまとう瘴気が弾けて膨らんだ。空間の三分の一は、血の色に飲み込まれた。……こんな有名なポータルサイトが感染を受けるなんて!!…ぼうっとしていると、私の横を『何か』が駆け抜けた。
「……あ、セキュリティ」
戦闘機をなめらかに溶かしたような形の白い群れが、瘴気を囲い込んだ。それは少しずつ増えていって、球の形になった。それはあの子を押し込めるように包囲を縮めていく。よく見ると、機体(?)の翼がお互いの翼と、レゴブロックみたいに結合して、お互いの隙間を埋めている。手に負えない汚染箇所を隔離して、消滅させるつもりなんだと思う。
――きゅっと、胸が痛んだ。
あの子は囚われた。多分、消されちゃった。そう、ご主人さまに報告するために、教えられたアドレスに連絡しようとした瞬間
無数の機体が、バラバラに飛び散った。
「あっ……」
その瘴気はもう、目と鼻の先まで膨れ上がってて……グーグルのセキュリティさえ手に負えなかった瘴気が、私に!に、逃げないと……!!
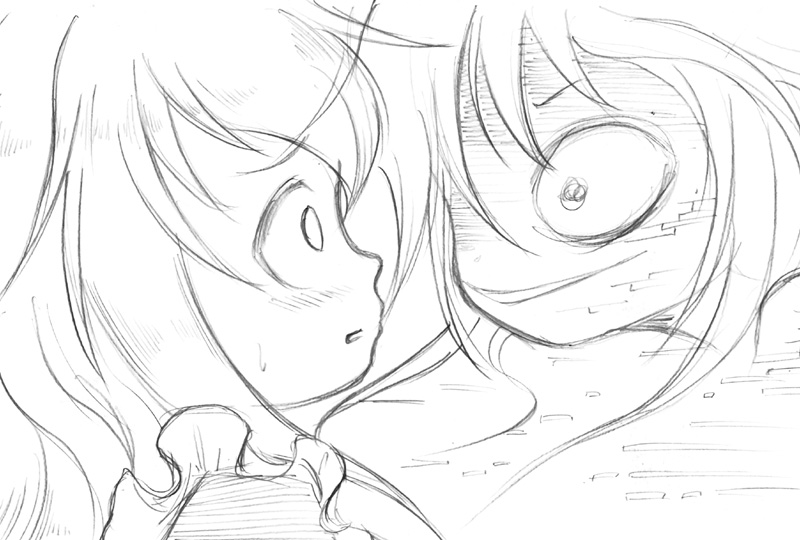
急いでニュースサイトの入り口を適当に叩く。でも駄目。他のセキュリティが働いて、この空間は閉ざされてしまった。…ログアウトしか方法はないけど、そしたらもう『あれ』を追跡できない。
――どうすれば、いいの?
瘴気が鼻先をかすめたそのとき、すごく強い、衝撃。電気的なものじゃなくて、物理的な。『強制終了』という文字が頭上にひらめいて、意識が遠くなっていく。…追わなきゃいけないのに、どうして………。
周りが血の色に染め上げられた瞬間、ぷつり、と意識が遠のいた。
僕は、夢を見ていた。
さっきバラバラに砕け散ったはずの自転車が、今朝磨き上げた直後の姿で、白い部屋に居た。置いてある、じゃなくて、居たんだ。
「なんとなく、綺麗にしたかったんだ。…柚木のことで浮かれてたのもあるけど、ただなんとなく」
がちゃり、かちゃん、と、自転車が音を立てた。夢の中では、それは自転車が操る一種の言語で、僕には理解できる。ありがとう、と言ったのだ。
「どこかで、予感してたのかもな。別れが、近いって」
ひんやりとしたフレームに触れると、『彼』はハンドルをもたげて、僕に絡みつくように傾いた。別れを惜しんでいるみたいに。
「…僕は、みんなの自転車を羨んでばっかりで、お前に酷いことばかり…」
彼は、体中をかちゃかちゃ言わせながら最後の話をした。
週に一度は油を差して、フレームを拭いてくれたことが、嬉しかった。
しょっちゅう施してくれる丁寧なメンテナンスが、仲間うちでも自慢だった。
――あの時、自分の力では逃げきれないと悟った。だから、その体を贄に、あのランドナーを呼び寄せたのだと。呪いのランドナーは、気に入った部員の自転車を屠る。でもこういうふうに、自転車がそれを望んで呼び寄せることも、たまにあるんだ。…と、変速機をがちゃがちゃいわせながら笑った。…せめて自分の飛び散った部品を、形見に使って欲しい。とも言ってくれた。
「意地でも探すよ。……ありがとう」
白い部屋が、自ら光を放つように、さらに白い光に包まれた。光は、自転車の細いフレームをいとも簡単に飲み込み、全てを白く染め上げた。……あとに残ったのは、僕と白い部屋。
耳元を涙が滑り落ちる感覚で、目を覚ました。
――見知らぬ天井、質のよさそうな布団。はっきりしない頭で考える。……ここは、どこだっけ……
柚木の部屋か?と希望的観測が頭をよぎったけれど、頭がはっきりするにつれ、その可能性は霧散した。枕元にドカ積みにされた、ネットワーク関連の書籍、その中に無造作に挟み込まれた『プレイボーイ』、脱ぎ散らかした服、発火寸前の超タコ足配線、灰皿に山積みで、これまた発火寸前の吸殻。家主の人格を如実に表すアイテムの数々。
「…紺野さん」
声に出してみたが、返事はない。何度か呼んでみたけど、返事はこない。柚木の姿も見当たらない。布団の端で雪崩を起こしている本を押しのけて体を起こす。全身に、びりっと痛みが走った。体中の筋肉という筋肉が、きしんで悲鳴をあげている。よろめいた拍子に、右肩が本の山を突き崩して新たな雪崩を引き起こした。
「…なんだここは。物置か」
「失敬な。俺の寝室だ」
本の山の向こう側から、紺野さんがのっそりと体を起こすのが見えた。
「…お前、いま絶対動くなよ」
「な、なんだよ、急に」
身じろぎした拍子に、左手のあたりに冷たいものがあふれた。
「ばっ……馬鹿野郎!動くなって言っただろうが!!」
「なっ何、これ何!?」
慌てて左手に触れたものを確認すると、冷たい水だった。どぷんどぷんどぷんと音をたてて、エビアンのペットボトルから溢れている。
「うわ、わわわわ」本の壁ごしに紺野さんが突き出したティッシュの箱をひったくり、エビアンのフタをきっちり閉めてからティッシュで布団を叩く。
「あーあぁもう…この季節、なかなか乾かないのに…」
「なんで枕元にエビアンが置いてあるんだよ!」
「水を飲ませろと医者に言われたからだ」
「医者!?」
「往診の医者だ。……覚えてないのか」
まだ、はっきりしない頭で、僕はぼんやりと昨日のことを思い出していた。息を切らせて紺野さんの車を追って、高そうなマンションにたどり着き、目の焦点が定まらないまま玄関に転げ込んでぶっ倒れた。それ以降の記憶が怪しい。……断片的に覚えているのは、朦朧とする意識の中、枕元に座る年配の医師。この部屋のとっ散らかり具合にしきりに文句を言いながら、『大事ない』という意味あいの言葉を、何度か言い方を変えてくりかえし、銀色の道具類をまとめると、ぷりぷり尻を振りながら出て行った。なんで尻を振るのだ、と朦朧としながらも不思議に思っていたけれど、意識がはっきりしている状態でこの部屋を見渡して謎が解けた。足の踏み場がないから、ぷりぷりせざるを得なかったのだ。
「…柚木ちゃんに聞いたぞ。自転車がクラッシュしたんだってな。まー、大丈夫だとは思ったんだが、念のため知り合いの町医者に往診を頼んだんだ。まぁ、ちょっと重い打撲と脱水症状程度で済んだらしい。今日一日は寝てろ」
さっき、きっちりフタを閉めたエビアンをもう一度空けて、一口あおる。水が体に染み込んでいく感覚と共に、徐々に頭がはっきりしてきた。
やがて、一つの疑問が首をもたげた。
「ねぇ、紺野さん」
「どうした。腹が減ったのか」
「……どうして、『往診』なんだ」
崩れた本の山を積みなおしていた紺野さんの、手が止まった。
「あ、あぁ。ほら。あの人、いつも俺が世話になってる近所の町医者なんだよ」
止まっていた手が、ぎこちなく動き始めた。そしてつとめて無関心を装うように、小さくため息をついた。
「近いし、下手な医者より信用できるからな」
「嘘だ」
紺野さんの顔から、表情が消えた。本を積む手を完全に止めて、ただ表紙を見つめている。
「僕は、このマンションの番地を正確に言えるよ」
「…………まじかよ」
「この辺の地理は、全部把握してる。一度、通ったからね」
紺野さんの言葉を待ってみた。相変わらず、本の表紙を漫然と見つめているだけで、反論をして来ない。僕は言葉を続けた。
「ここは間違いなく、救急指定・純天大学総合病院の近くだよ。町医者は、いない」
「……あーあ……」
紺野さんが、間延びした声を出して本を放った。いたずらがバレた小学生のように、悪びれた様子もない。
…昨日、あいつらは何て言った?柚木をヤク漬けにして新大久保に立たせて、僕をマグロ漁船に乗せて殺す、そうはっきり言った。…あのときの恐怖と怒りがないまぜになったどす黒い感情が腹の底から湧き出てきて、その照準が「かち」っと音を立てて紺野さんを捕らえた。
「……あーあって何だ!あんたに関わったせいで僕も柚木も殺されるところだったんだぞ!!黙って聞いてたらなんだよ、警察どころか救急車も呼ばないでテキトーな町医者に診せて!あの連中と同様、僕らを拉致っただけなんじゃないか!?」
「ちがう!!」
本の山に手をついて、紺野さんが身を乗り出して怒鳴った。反論があるなら聞いてやろうじゃないか。僕はまっすぐ、紺野さんを睨み返した。
「伊藤さんはテキトーな町医者なんかじゃない!立派な町医者だ!!」
………何!?
「……い、今は町医者の良し悪しを問いたいんじゃないよ」
「伊藤さんを悪く言う奴は、俺が許さんぞ!あの人は名医だ!!」
「いやだから、医者のことは謝るけど僕の話を」
「いや聞け、俺はお前をテキトーな医者に診せてお茶を濁したわけじゃない!大切な友だからこそ!信頼している名医にだな!」
「そっ、そんなこと言って論点すり替えようったって」
「論点のすり替えだなんて!悲しい事を言うな!お前が玄関に倒れこんだ瞬間、俺がどれだけ驚き戸惑ったか!!」
「…その割にはボロボロの僕に自転車漕がせてニヤニヤしてたよね…」
「いや、俺の車バックミラー壊れてて、苦悩の顔がニヤニヤ笑いに見えるんだよ」
「そんな器用な壊れ方があるか!」
「なぜないと言い切れる!?」
「…だ、だってひび一つ入ってない…」
「なぜだ!?なぜひびが入ってないと壊れていないと言い切れる!?」
「…………」
……起きて早々だけど、僕はもう疲れ切っていた。
この人が何を隠しているのか知らないけど、打撲と筋肉痛で全身痛いのに、こんな不毛な言い合いをこれ以上させられるなら1日寝てたほうが数段マシだ。
「……分かったよ。もういい……」
「よくないっ!!!」
気合一閃、綺麗な木目のドアが轟音とともに開け放たれた。ドアの前に転がっていた雑誌が、埃を舞い上げて吹っ飛んだ。……や、やった……待ちかねたぞ、援軍到着だ!!
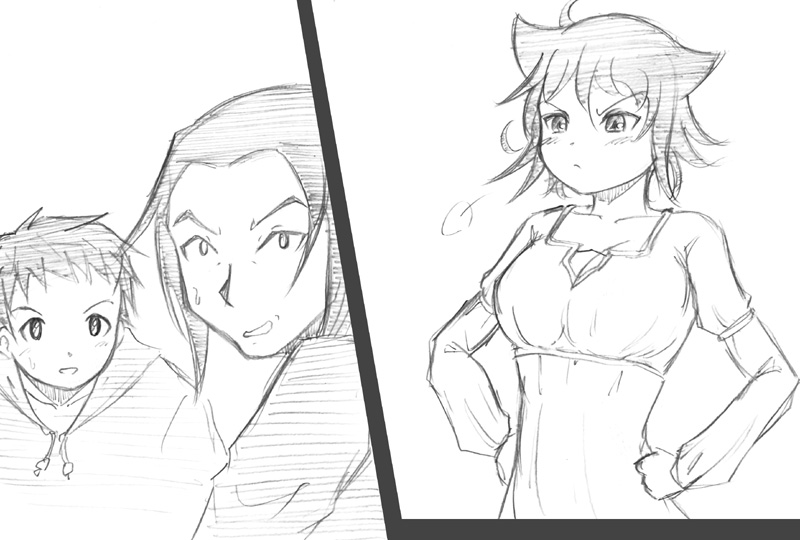
「言っとくけど、弁解の余地も話し合いの余地もないからね!!」
本の山を一切避けずに蹴り分けながら、柚木が携帯電話を片手に近づいてきた。紺野さんが静かに息を呑む。…あの人なりに、整理されてたんだろうな…と、少し気の毒になるが今は敵に同情している場合じゃない。
「あ、あらら…柚木ちゃん、起きてたのか」
「これだけ大騒ぎしてれば、起きるわよ」
柚木が寝ていたらしきリビングルームは、寝室の比較にならないくらい整然としていた。広々としたフローリングの床に黒のカーペットが敷かれ、その上に柔らかそうな黒のソファとガラスのテーブルが置いてある。奥のほうには、60インチはあろうかと思われる薄型のハイビジョン、窓辺の大きい観葉植物。モデルルーム並みの生活感のなさだ。…多分、こっちの寝室を生活の基盤にして、リビングには女の子を連れ込んだりするんだろう。
「紺野さん、…ひょっとしてお金持ちですか」
「ハイビジョンにびびって敬語になってる場合じゃないでしょ!なんでそうやって気が散りやすいの!そういうの、超腹立つんだけど!!」
「ご、ごめんなさい……」
「何ですぐ謝るの!そんなだから紺野さんのペースに呑まれて変なことに巻き込まれるんだよ!!」
「……や、あの、すみま」「何!?」「……なんでもないっす……」
ひたすら萎縮して周囲に同化するのがせいいっぱいの僕。…紺野さんへの攻撃ついでに僕のMPもゴッソリ削られた気がするが、呼び出す召喚獣が強力であればあるほどMPを大量消費するのは世の必定…さあ舞い上がれ、僕のバハムート!解き放てギガフレア!!
「……紺野さん、嘘ついたよね」
柚木が突き通すような視線で紺野さんを睨みつけた。声色は薄氷のように鋭利で冷たい。紺野さんは息を呑んで後じさった。
「警察には俺が話しておくって言ったよね。だから安心して寝てたのに……」
「と、とりあえず事情を聞いてくれ」
「弁解の余地なんかないって言ったはずよ!!」
そう叫んで、携帯電話をかざす。いいぞ、そのまま110番にダイヤルしてしまえ!!思わず握り締めた拳に、力がみなぎった。
「紺野さんが呼ばないなら、私が警察呼ぶから!」
「待てってば!!」
紺野さんが本の山を蹴り倒して、ダイヤルしようとした柚木の手首を掴んだ。
「…痛い」
目を見開いて顔を赤らめる柚木を引き寄せて、なんと奴は、優しく携帯電話をもぎ取った!そして耳元に顔を近づけると、囁くように言った。
「…少しでいいんだ、話を聞いてくれよ。警察の話は、それからでいいだろう」
柚木は頬を染めて視線をそらし、しおらしく頷いて髪をいじり始めた。
……バハムート、陥落………。
「……納得のいかない話を聞かされたら、速攻で警察呼ぶんだから!!」
せめてもの抵抗なのか、柚木は手首を乱暴に振りほどくと、腕を組んでドアにもたれた。このなんとも言えない痴話喧嘩風の空気の中、がっちり当事者のはずの僕が、一人蚊帳の外の気分を味わっている。……ここは本来、柚木のポジションじゃないのか。
「……なに見てんのよ!!」
目が合った瞬間柚木に噛みつかれ、慌てて逸らす。…僕が何をしたというのだ。紺野さんに手首を掴まれたのも、思わず顔を赤らめちゃったのも、そっちの事情じゃないか。僕に八つ当たりすることないだろう。理不尽だ、猛烈に腹が立つ!…と、ここで僕まで怒り出したら痴話喧嘩の三つ巴と化し、収拾がつかない修羅場の3丁目になることだろう。怒鳴りたいのをぐっとこらえて、エビアンを一口あおる。
「さて、まずは姶良と会った経緯からか…」
「その辺はいいから、飛ばして!」柚木が先を促した。
「飛ばすって…どの辺まで」
「姶良が知ってそうなあたりは全部飛ばして」
「…それじゃあ、全然イミわかんないぞ」
「わ、私は!…あいつらの素性と理由だけ分かればいいんだもん!」
ますます顔を赤らめて、柚木がついとそっぽをむいた。少しのあいだ、ぽかんとしていた紺野さんが、ふいににやりと笑った。
「…ま、そういうこともあるかもな」
…そういうことも、あるんだろうか。僕はむしろ、らしくないと感じたけど。
「じゃ、遠慮なく冒頭は端折るぞ。まず、俺の仕事から…だろうな」
紺野さんはベッドに深く腰を掛けて指の先を組み、僕らをじっと見つめた。その冷静な目つきと仕草は、なんというか、「社会人」を思わせた。…追い詰めているのはこっちのはずなのに、背筋に緊張が走った。バイトの面接みたいな気分だ。
「俺は、株式会社セキュアシステム・MOGMOG開発チームの主任を務めている」
…別段、驚きはしなかった。MOGMOG開発の関係者だということは知っている。開発チームのど真ん中にいるとは思ってなかったけど。ちらりと柚木の様子も伺ったが、平然としたものだった。…僕の知らないところで、紺野さんとメールでも交わしてたのだろう。さっきのイライラがぶり返しそうになって、エビアンをもう一口あおる。
「…お前らを拉致しようとした連中…そうだな、姶良がメールで送ってきたこいつ。こいつは、営業1課の武内だ」
「は、営業1課!?」
柚木と僕が、思わずハモッってしまった。
「……すまない」
「ちょっと、話が全然見えないんだけど!?」
柚木のイラついたような声に、僕も軽く頷く。なんで、同じ会社の営業さんが、開発チーム主任の知り合いを拉致するんだ。
「今に分かるから。今はとにかく聞いててくれ」
紺野さんは若干落ち着きを失いぎみの僕らを軽くなだめると、またあの時の顔をした。
僕らに話せる部分と、話せない部分をより分ける顔つき。…やがて、ゆっくりと重い口を開いた。
「まず、謝らなければいけないことがある」
紺野さんは、決心しかねるように目前の本の山を凝視していたが、やがて小さく息をつき、顔を上げた。
「市販されているMOGMOGの、コミュニケーション機能とウイルス消化機能…あれは全部、ダミーだ」
「えぇ!?」
またハモッてしまった。柚木の表情をちらりと伺う。柚木も、僕を見ている。怒っていいのか、驚いていいのか、全くもって判断しかねている気持ちは同じのようだ。
「何か食ってる映像は、消化中なわけじゃなく、ただのアニメーションだ。コミュニケーション機能は、簡単な会話が出来るだけのソフト。もちろん、ワクチンの開発と配布は他のソフトと同様か、それ以上の水準で責任をもってやっている。利用者の識別もだ。MOGMOG同士のワクチン交換機能は、既存のプログラムの応用で済むし、こいつがあると、後々都合がいいので装備してるが…今の時点では大して意味がないな」
「で、でも!MOGMOGの売りっていったら、コミュニケーションと消化機能でしょ!?その二つが嘘だったら……」
「MOGMOGの存在意義って何?…ってなるよな」
紺野さんが自嘲気味に、柚木の言葉を引きとった。
「……年末商戦だよ」
後書き
(2)に続きます
ページ上へ戻る
全て感想を見る:感想一覧
