| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
霊群の杜
作者:たにゃお
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動書の洞
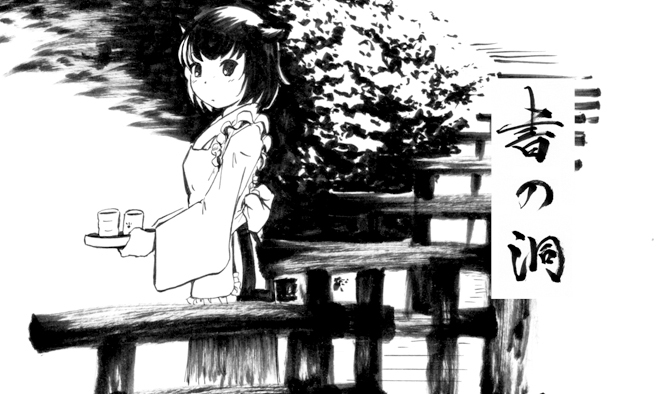
この町の外れには、旧い屋敷がある。鬱蒼と茂る鎮守の杜に抱え込まれた屋敷の裏手に、古い鳥居が連なる。鳥居は幾重にも連なり、山奥の御神体を守っているのだ。誰も顧みることのない、御神体を。
「何十本立てるんだろうな、これは…」
こういう鳥居は大抵、朱色に塗られていることが多いが、ここの鳥居は黒ずんだ樹皮つきっぱなしの丸太で組まれている。何の木なのかは知らない。それが稲荷大社の千本鳥居の如く、しつこく連なってる。
この鳥居を拵えたのは、俺の友人だ。……ということになっている。
『こちら側』に戻ってくる度に鳥居を一つ増やす。そんなことを云っていた。
「今日は暑いな……」
気が遠くなるような長い石段を登りながら、独りごちる。何回も、いや何千回も登り慣れた石段だが、未だに三分の二程登ると息切れする。まだ4月半ばだというのに妙に緑が濃いし、最近は暦通りに季節が巡らない。
俺の少し前を、茶色のカーディガンを羽織った信心深そうな婆さんが、こつりこつりと杖を鳴らしながら歩いている。そっと追い抜きながら、非常に居たたまれないというか、申し訳ない気分がじわりと胸に広がる。追い抜きざま、軽く会釈をすると、じんわりと笑顔を返してきた。…本当に、申し訳ない。
ここのご御神体が、あんな『たわけ者』だと知れたら……。
この婆さんの信仰心は、決して報われないのだと思うと、ひたすら申し訳ない。だから俺は婆さんが荷物を持っている時は、肩代わりしてやることにしている。今日は手ぶらのようだ。
山腹の社に着くと、婆さんに見られていないことを確認して裏に回る。社にはテキトーな幣とそれっぽい御神体の由来(アラハバキということになっている。何故か)がある。
まだ柔らかい楓の若葉に隠された洞に入る。すぐに突き当りが見えるが、脇の岩を力いっぱい押し込むと、人が一人通れるくらいの隙間ができた。肩から体を滑り込ませる。冷えた空気に土と紙の入り混じった匂いが充満していた。
土の壁は、途中から徐々に『紙』で押し固められた洞と化していく。『紙』の正体は、読みっぱなしで放置された書の山だ。それらは不思議に洞の内部に張り付き、紙のトンネルを形作る。下の方は土に還っているようだ。
「またお前か」
洞の奥から、奴の声が聞こえた。街中ではくぐもって聞こえるが、この洞の中では妙に通りがよい。奥に進んでいくにつれ、妙に明るくなっていく。何が光源になっているのか、未だに分からないが。
何処かで拾って来たような灯篭風の灯りの下で、奉は今日も本を繰っていた。適当に切られた(というか俺が切った)ぼさぼさの髪で、顔がよく見えない。自分では床屋にも行こうとしないので、伸びすぎかなと思ったタイミングで、気が付いた人間が切るシステムだ。確か中学の制服だったと思われる白のワイシャツに、恐ろしく古い黒の羽織を適当に羽織って寒さをしのいでいる。…適当なのだ、何もかも。
「他に誰が来るんだよ。ややこしい隠れ家作りやがって」
「カムフラージュだ。植え込みで隠したくらいじゃ、目敏い小学生が入り込んでくるんだぞ」
奴は本から目も離さずに、無愛想に返してきた。いつも通り傍らに立っている小柄な少女が、肩あたりで切り揃えた綺麗な黒髪をさらりと揺らして軽く会釈をする。綺麗な二重の切れ長の双眸は、常に伏し目がちだ。
「…よ、きじとらさん。今日は袴なんですね。…袴も、お似合いです」
きじとらさんは、少しだけ笑う。あまり饒舌ではないこの子がどうして常に奉の傍らにいるのかはよく分からない。こいつも大して話が好きなタイプじゃないし、気を遣うタイプでもない。俺が居ない間ひたすら沈黙してんのか。書が溶けて出来た洞の中で。究極につまんねぇ空間だろ。
「あと、そろそろ試験だぞ。大学にもたまには来い」
「代返頼むよ」
「出来るか!俺が留年するわ!!」
「それより甘味は持ってきたのか。持っていれば茶を出す」
「手土産がないと茶も出さないとかもうな……」
追分だんごの豆大福を取り出してきじとらさんに渡すと、彼女は小さく会釈して更に奥の暗がりに消えた。
「当然だ。霊験高き玉群神社のご神水で淹れた茶だぞ、只で飲めると思うなよ」
「何が霊験だ。ここの御神体がお前みたいなたわけ者と知ったら、あの婆さんの寿命も3年は縮まるわ」
懐紙を引いた皿に乗った大福が、香りのいい茶と共に出て来た。…確かに、ここの水で淹れた茶は格別に旨い。きじとらさんが淹れてくれた茶だから、だろうか。ちらと目を上げると、彼女と目が合った。慌てて目を反らす。…このひとの、偶にじっと凝視してくる感じが少しだけ苦手だ。俺は割とシャイなのだ。
玉群 奉。
この辺りの大地主、玉群家の次男坊だ。俺は昔からこの家に出入りがある造園屋の息子で、小さい頃から親父の仕事について行っては、ここの子供たちと遊んでいた。兄さんも妹も割と普通の子だったが、こいつだけは小さい頃から変わっていた。
俺が物心ついたころから、奉はこの洞に居着いて書を読んでは捨てていた。同じ年の俺に無理やり引っ張り出されて嫌々遊ぶ以外は、いつもここにいたものだ。学校も来たり来なかったりだった。
小さい頃から目を酷使していたせいだろうか、ずいぶんと昔から、奉はずっと眼鏡をかけていた。薄い煙のような灰色が入った丸い、同じレンズの眼鏡をフレームだけを微妙に変えて使い続けている。奉の話では、このレンズはガラスではなく、何かの石を磨いて作ったものらしい。
「こいつは象が踏んでも壊れないんだ」
と奴が得意げに言うのを、幼い俺は真に受けて思い切り踏みつけた事がある。当然、フレームはぐっしゃぐしゃにひしゃげた。奉は
「いやそういうことじゃねぇよ」
と、さも可笑しそうに笑ったが、親父は大慌てで俺に拳骨を振り下ろし、奉と親に平謝りに謝った。奉の親は怒るどころか、『もうお宅に出入りさせない』という親父を必死になって止めた。今思い出してもおかしいほどに。
「奉には、この子が必要なんです」
そう云われた時、何故かぞっとした覚えがある。…その声色に。
「……あの子が生まれた時にな、俺は少し気になることがあった」
眼鏡を踏んだ帰り道、親父がぽつりぽつりと語り始めた。さっきの剣幕はどこへやら。
「子供が生まれた時ってなお前、普通『子供が生まれた!』って言うだろ?順序としては、子供が出来る、名前を考える、生まれる、名前を呼ぶ、だ」
そりゃそうだろう。何言ってんだ親父は。その時はそう思っていた。
「あそこの次男坊…奉くんの時は、違ったんだよ」
興味はなかったが、一応気になるふりをする。
「………『奉』が生まれた。あの人たちはそう言ってた」
「え、それじゃまるで」
造園道具を荷台から降ろしながら、親父は深くため息をついた。
「『奉』という名前が、一番最初にきてるんだよ。あの子だけは。なんかあるぞ、玉群には。…今回のことは、お前をあの家から引き離す、いい機会だと思ったんだけどなぁ…」
「やだよ、奉は仲良しなんだ。…眼鏡壊したけど」
「あぁそうだな。知ってる。悪い、忘れろ」
あたりはすっかり夕日の朱に染まり、東の暗がりに、玉群の鎮守がうっそりと広がっているのが見えた。親父は小さく背を丸めて、また呟いた。
「……俺、あの家怖いわ」
「その眼鏡、まだ掛けてるんだな」
『眼鏡事件』を思い出しがてら、ちらっと口にしてみた。奉は豆大福をぐいと呑み込んで、にやりと笑った。
「……象が踏んでも壊れないぜ」
覚えていたか。忌々しい。
「レンズがな。…お前は説明が足りないんだよ」
俺の分の豆大福にまで手を伸ばし始めたので、すっと皿を引く。
「……こら」
「こら、は俺の言い分だ。なに俺の皿に手を出している」
「これは玉群神社への供え物だろ。それなら全て俺に権利がある」
奉はしつこく皿に食い下がる。
「俺は『奉』。玉群神社の奉る神だ」
結局、奉は俺の分の豆大福まで平らげ、書を放り捨てて、机に突っ伏して寝てしまった。奴が寝落ちた頃合いに、きじとらさんが豆大福をもう一つ、俺の皿に載せてくれた。新しく淹れたお茶を添えて。
きじとらさんに礼をして、洞を出て階段を下ると、前の方をさっきの婆さんが歩いているのが見えた。…こんな男が奉られている神社に日参なんて、その労力に対して申し訳な過ぎて泣けてくる。
馬鹿みたいに連なる鳥居のトンネルに差し掛かった。丸太で作られた雑な鳥居が連なる様は、神社というよりアスレチックのようだ。
「俺が玉群に生まれる毎に、参道の鳥居を一本ずつ増やしている」
以前、奉がそんなことを云っていた。鳥居の数は37本。奴の言い分を鵜呑みにすれば、奴はもう37回生まれ変わって、ここに奉られていることになる。ダライ・ラマかよ。
―――俺、あの家怖いわ
あの日の、父の言葉が頭をよぎる。『奉には、この子が必要なんです』という、奉んとこの母さんの言葉と共に。生まれ変わり云々の話は眉唾としても、玉群に何かあるのは間違いないだろう。『奉』は名前というより恐らく、役職のようなものなのだ。
まぁ、俺には関係ないし、俺の最優先ミッションは、奴に期末試験を受けさせることだ。

後書き
次回更新予定は、来週です。
ページ上へ戻る
全て感想を見る:感想一覧
