| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
Chocolate Time
作者:Simpson
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第3章 揺れる想い
3-2 理解者
理解者
8月13日。日曜日。
その日の午後。ケンジはケネスを連れて帰宅した。
「紹介するよ。こいつはケニー。ケネス・シンプソン。俺と同い年」ケンジが言った。
「い、いらっしゃい。ゆっくりしていってね。自分の家だと思って」母親が引きつった顔でそう言うのをマユミは隣であきれ顔で見ていた。
ケネスは右手を母親に差し出しながら言った。「よろしゅう頼みますわ。わいケネス・シンプソン言いますねん。愛称ケニー。二晩やけどお世話になります」
「ず、ずいぶん流暢な、」母親が口をぽかんと開けて呟いた。「大阪弁だな」父親が背後で腕をこまぬいて同じように呟いた。
その日の夜。ケニーと共に食卓を囲んだケンジたちは、いつもと違う雰囲気での夕食をとっていた。
「で、ケニーはどうしてそんなに流暢な、その、大阪弁をしゃべるのかね?」父親が切り出した。
「わい、10歳まで大阪に住んでましてん。母親が大阪のおばはんですよってにな。ほんで小学校高学年の時に父親の母国カナダに引っ越したっちゅうわけですねん」
「ほう……」
「カナダでは水泳で記録を持ってるんだって?」母親が訊いた。
「へえ、中学生の時に全国大会まで行きましてな、100mバタフライで三位に」
「そりゃあすごい!」
「わい、自分の能力を伸ばすために今回日本に来ましてん。ほんで水泳の強豪校に留学しとるっちゅうわけですねん」
「バタフライか……。ケンジとライバルってわけね」母親がケンジをちらりと見て言った。
ケネスがミニトマトを口に入れ、もぐもぐさせながら言った。
「それはそうと、ケンジの妹はん、ごっつかいらしな。改めて見ると」
「え?」マユミは海老フライを箸でつまんだまま、動きを止めて顔を上げた。
「ケンジもイケメンやけど、妹はんも素敵なべっぴんさんやで。わいにもこんな妹おったら毎日なんか買うてきたったるけどな。マユミはん……やったな?」
「そう。マユミだ」ケンジがぽつりと言った。
「マユミはん。名前もいけてるやんか。わい、惚れてまうな」
「ふざけんな。ケニー」
ケネスは箸を咥えたまま口をとがらせた。「何やの、冗談やんか。なにキレてんねん、ケンジ」

「もういい。部屋に行くぞ。早く片付けろ」ケンジは食器を持って立ち上がった。
「ごちそうさま。めっちゃうまかったです」
ケネスは丁寧に手を合わせた後、慌てて立ち上がりケンジの後を追った。
「待ってえな、ケンジ」そしてどたどたと階段を上がっていった。
「親しそうだな」後ろ姿を目で追って父親が言った。
「あれを『親しい』というのかしら……」母親も言った。
ケンジの部屋に入ったケネスは、ドアを開けて中に入るなり言った。「さっき荷物置きに来た時も思ったんやけど、」
「何だよ」ケンジが無愛想な口調で言った。
「この部屋、女の子の匂いがするな」
「ぎくっ!」
「彼女、おらんはずやろ? ケンジ」
「い、いないよ、彼女なんか」
「つき合うてる女子、ほんまにおれへんのか?」
「いないって。神に誓って」
「誓わんでもええ」ケネスは鼻をくんくんと鳴らした。「なんでやろなあ……」ケネスはケンジの顔を見た。
ケンジは目をそらして言った。「コーヒー飲むか? ケニー」
「おお、ええな。わいコーヒー好っきゃねん。ごちそうしてくれんの?」
「ああ。待ってな」
ケンジは階段を降りた。丁度降りた所でマユミと鉢合わせをした。「マ、マユ……」
「コーヒー淹れた。今持っていこうと思ってたとこ」
「お、おまえの分も、」
「あるよ。でも自分の部屋で飲むから、気を遣わないで」マユミは自分のカップを手に持つと、二つのカップとデキャンタの載ったトレイをケンジに預けて、自分だけさっさと階段を昇っていった。
「なあなあ、ケンジ、」
「何だよ」
「お前、何で家に帰るなり機嫌悪くなんねん。何かおもろないことでもあんのんか? 家庭に」
「べ、別にないよ……そんなこと」
「それに妹はんも、何か怒ってるみたいなんやけど、気のせいかな」
「ああいうヤツなんだ。まったく可愛げのない」ケンジはぶつぶつ言ってコーヒーカップを口に運んだ。
「おまえら、ケンカしてるやろ。ホントはめっちゃ仲ええんとちゃう? こないだも街でデートしとったし」
「デ、デートなんかじゃない!」
ケンジは自分でもびっくりするぐらいの大声を出した。
「何やの。そないに火ぃ吹いて怒る事かいな」
「だからどうでもいいだろ、妹の事なんか」
ケネスは少し考えていた。そしておもむろに立ち上がった。
「ど、どうしたんだ、ケニー」
ケネスは自分のバッグからごそごそと小さな箱を取り出すと、振り向いてケンジに言った。「仲裁したるわ」
「え?」
ケネスはケンジの持っていたカップを奪い取り、無理矢理トレイに戻すと、それを持ってドアを開け、部屋を出た。
「ほれ、ケンジ、おまえも」
「よ、余計な事を……」

ケンジの焦りをよそに、ケネスはマユミの部屋をノックした。「すんまへん、ケニーです。ちょっとお邪魔してもよろしか?」
しばらくしてドアが開けられた。「何か用? ケニーくん」
「一緒にお茶しまへんか? お土産もありますよってに」
「お土産?」
「そうです。カナダ土産のチョコレート。ほれ、ケンジも早う来んかい。ほたらお邪魔します」
ケネスに促されてケンジはしぶしぶマユミの部屋に入った。
「ん?」
「な、何だよケニー」
ケネスはまた鼻を鳴らした。「この部屋、ケンジの部屋と同じ匂いがすんねけど」
「そ、そりゃあ、同じ家の中だからな。と、当然だろ」
「そうかなあ……」
「ケニーくんのお土産のチョコレートって?」マユミが口を開いた。
「チョコレートお好きですか?」ケネスが訊ねた。
「大好物だ」ケンジが言った。
「ケンジには訊いてへん」
「わ、悪かったよ」
「甘いもんとコーヒー、よく合いますな。ところでマユミはん、ケンジとなんでケンカしてはんの?」
「こ、こらっ、ケニー!」
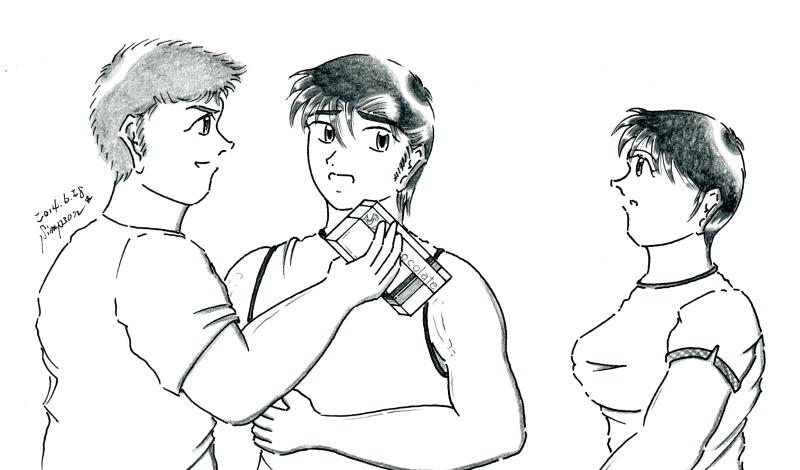
ケネスはあきれ顔でケンジを見た。「あのな、ケンジ、わい三日間もここで暮らすねんで、おまえらの事よう知っとかんといろいろと気まずい事もあるやろ?」
「ケンカ、って言うか……」マユミがうつむき加減で言った。「何でもない。気にしないで、ケニーくん」
「それにしても、ほんまかいらしな、マユミはん」
マユミは恥ずかしげに目をそらした。
「わいの好みのタイプやなー。いや、冗談抜きでやで。でもな、」ケネスが急に小声になった。「わいな、実はバイですねん」
「バイ?」
「誰にも言わんといてな。バイ。『バイセクシャル』。つまり、オトコでも女でも同じように愛せるって事や。あーこんなとこでカミングアウトしてもうた」
「そ、それって……」
「大丈夫や、ケンジ、心配せんでもええ。わいにも理性はある。おまえを夜中に襲ったりはせえへんから心配いらんで」
「当たり前だ! 俺にはそんなシュミはない!」
ケネスはコーヒーを一口飲んだ。「そやけど、便利やで」
「何がだよ」
「好きになる対象の人間が普通の人の倍おるっちゅうことや」
「何だよそれ」
「そやけどな、誤解せんといてな。オトコとみれば誰にでも欲情するっちゅうわけやあれへん。そやから銭湯行ってオトコどものハダカ見てもいつも興奮するわけやないんや」
「へえ」
「『へえ』って。やっぱり誤解してたやろ? ノンケの男かて、女とみれば誰にでも欲情するわけやないやろ? それと同じや。好みのルックス、好みのプロポーション、ドキドキする対象はたまにしかおれへん。それがオトコでもな」
「なるほど」
「そんなん、男湯に入る度に興奮しとったら身がもてへんがな。それは単なる変態や」
「面白い」マユミがクスッと笑った。
ケネスもにっこりと笑って言った。「ああ。笑ろた方が百倍魅力的やで、マユミはん」
「ケニーくんて、ユーモアがある。話を聞いてると和む」
「そりゃ嬉しなあ。っちゅうわけやから、ケンジ、わい、おまえあんまり好みやないねん。そやから夜中襲ったりせえへんから安心しいや」
「変なヤツ」ケンジは遠慮なくあきれ顔をした。
「おお、もうこんな時間や。遅いから寝るわな。ほな、マユミはん、おやすみなさい。ええ夢みてな」
「おやすみなさい」
マユミの部屋を出て、ケネスたちはケンジの部屋に戻った。
「本当におまえおしゃべりだな」
「大阪のおばはんの血が混じってるよってにな」
ケネスはコーヒーの最後の一口を飲み干すと、トレイにそのカップを置いた。「それはそうと、ケンジ、昨日の大会、何であないに調子悪かったんや?」
「……」
「いつものケンジやない、って感じやったけど、何かあったんか?」
ケンジはしばらく考えて口を開いた。「俺、自分でも意志が弱いやつだと思う」
「弱い?」
「そう。些細な事が気になって、大切な時に集中できなくなっちまってた」
「いやあ、今までのケンジやったら多少の事で力を出せなくなったりせえへんやろ。……そうか、今回のは些細な事やなかった、っちゅうことやな。何? どないしたんや? 言うてみ」
ケンジは少しの間黙っていたが、やがて決心したように顔を上げた。「大会の時の俺を見てほしい人に見てもらえなかった、とだけ言っとくよ」
「へえ」ケネスも少し考えて続けた。「いつもその人はケンジを大会の度に見に来てくれてたんか?」
「ああ。いつも。欠かさずな」
「待てよ、おまえ彼女おれへんかったんちゃうか?」
「いや、彼女とは違うから」
「女の人か?」
「もういいだろ。俺も大会でいい結果出せなかったから落ち込んでんだ。蒸し返さないでくれ」
「何やの、自分から言い出したくせに……。勝手なヤツやな」
「い、今言ったことは忘れてくれ」ケンジは焦ったようにカップを口に運んだ。
「ま、いいけどな。ん?」ケネスは、ケンジのベッドの布団の隙間から白い布が少しだけ出ているのに気づいた。
彼はそれを引きずり出して広げた。「なんや? これ」
「あっ! やめろ。そ、それに触るなっ!」
「おおっ! 女物のショーツやんか!」
「よこせっ!」ケンジはケネスの手からそのマユミの下着を奪い取った。そして真っ赤になった。

「考えられる事その1、ケンジは普通の高校生で、女子の下着に興味があり、それを一人エッチのアイテムにしている。その2、実はケンジは女装癖があり、夜な夜なそれを穿いて近所を出歩いている。さあ、どっちや? 白状しい」
「残念ながら前者だよ。そんな格好で外を出歩くわけないだろっ!」
「わいはいっぺんぐらい、そんな下着一枚で表、出歩きたい、思てるで。考えただけで興奮するやんか」
「俺はノーマルなんだよ。お前みたいな変質者じゃない」
「『変質者』。ええ言葉やなー」ケネスは笑った。「ほたら、そのショーツの元の持ち主は誰なんや? 考えられる事その1、マユミはんの干してあった洗濯物に手をつけた。その2、母親の干してあった洗濯物に手をつけた。その3、自分で購入した」
「なんでそんな事いちいち聞く必要があるんだよ。いいかげんにしろ」
「いやいや、これは男同士で語らう話題の定番、エロトークの一種やないか。あんまり深く考えんと、答えるんや、さあ!」
「エロトークって……おまえな」
「最も簡単に手に入るんは妹はんのやろけど……。見たところお母はんの年代が穿くようなショーツではなさそうや」
ケンジはぶっきらぼうに言った。「そうだよ。マユのだよ。悪いか」
ケネスはにっこりと笑った。「ケンジは健全やな」
「誰にも言うなよ」
「言わへんて。それにわい、明後日には日本からいなくなるよってにな、話したくても面白がって聞いてくれる人、残念ながらカナダにはおれへん」
「そういう問題じゃない」
「なあ、ケンジ、正直に遠慮なく言わしてもらうけどな、おまえとマユミはん、雰囲気おかしいで」
「な、何だよ、いきなり」
「何度も言うようやけど、ほんまはもっと仲ええんやろ? こないだのデートの時の雰囲気とはえらい違いやないか」
「だから、デートじゃないって」
「それにやな、学校でもいつもおまえの口からマユミはんの名前が出てくるやんか。にこにこ生き生きして語っとるやん」
「た、たまたまだ。そんなのおまえの思い過ごしだ。別に普通の兄妹だし」
「そうか? そうかなあ……」
ケネスは目を閉じて腕組みをした。
「もう遅いから寝るぞ」ケンジは客用の布団を床に敷き始めた。そしてさっさと自分はベッドにばたんと倒れ込み、灯りを消してしまった。
「おいおい、ケンジ、お客さんに対して失礼やないか。なんやの、勝手に電気消さんといて」
ケネスも仕方なくケンジが敷いてくれた布団に横になった。
◆
明くる月曜日。朝からケンジと一緒に学校へ行ったケネスは、夕方ケンジよりも先に帰ってきた。
「ただいま帰りました」
「お帰りなさい。ケニー、先にお風呂いいわよ」母親が促した。
「すんまへん。ほな遠慮なくいただきます」ケネスはそう言って、二階のケンジの部屋に入っていった。
着替えを持って階下に降りる前に、すでに部屋にいたマユミに声を掛けた。「マユミはん、お風呂先にいただいてもええですか?」
「あ、ケニー君。お帰り。いいよ。あたし先に済ませたから」
「そうでっか。ほな」
ケネスは階段を降り、浴室に入った。
風呂上がり、ノースリーブ姿のケネスは、マユミの部屋をノックした。
「どうぞー」
「すんまへん。お邪魔してもええですか?」ケネスは手にチョコレートの箱を持っていた。
「いいよ。どうぞ」マユミはケネスを部屋に招き入れた。
「はい、これ、マユミはんの好きなチョコレート・アソート」
「え? どうしてあたしが好きなチョコレートを?」
「ケンジに訊きましてん」
「そ、そうなんだ……」
「ケンジ、ちょっと遅くなる言うてた」
「ふうん」マユミはそのつれない反応とは裏腹に、ひどく残念そうな顔をした。
ちらりと横目でその様子を見たケネスは静かに口を開いた。
「マユミはん、伝えたい事、あんねけど」
「え? 何?」
「ケンジな、こないだの大会、全然あかんかってん」
「知ってる」
「その原因がな、言いにくい事なんやけど、マユミはんなんや」
「え? あたし?」
「マユミはん、ケンジが出場する大会には毎回欠かさず行ってたんちゃうか?」
「え?」
「ほんで、昨日は初めて見に行ってやらなんだ。そやろ?」
「と、友だちと約束があったから……」マユミはケネスから目をそらした。
「裏付け完了」ケネスは小さく言った。
ケネスは後ろの床に手をついて、マユミを見た。
「ケンジはそんな事一言も言わへんのやけど、わい、あいつと話してるとわかるんや」
「え?」
「ケンジにとってマユミはんが欠かせない人なんやっちゅうことが」
「…………」
「わいな、もう何週間もケンジと一緒に学校で過ごしとって、はっきり解る事が一つだけあんねん」
「はっきり解る……事?」
「そや。ケンジはあんさんの事が大好きやって事」
「えっ?!」
「それも、ただの妹としてではのうて、一人の女のコとして誰よりも好きなんやって事」
「そ、それは……」マユミは焦ったように目を泳がせた。
「毎日毎日顔合わせる度に、わいケンジからあんさんの事聞かされてきた。今日は妹がどうしたーとか、マユの好きなのはメリーのチョコレートでーとか。そらもう会話の8割はあんさんネタや」
「そ、そうなんだ……」
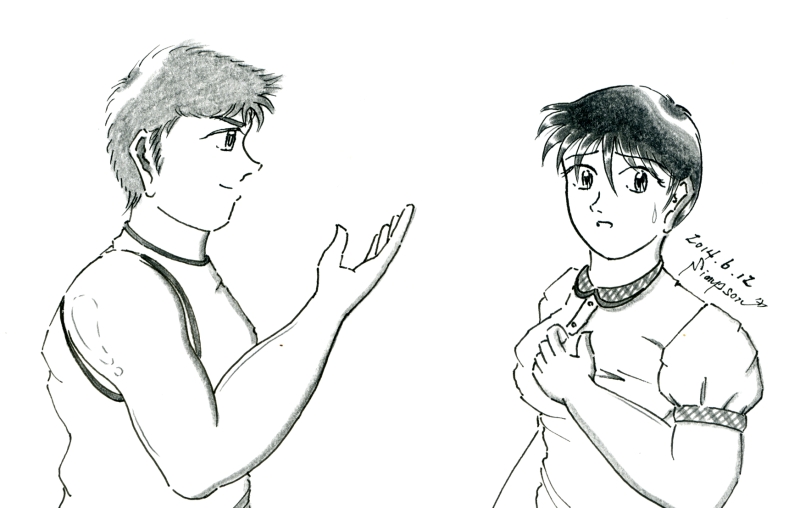
「でもな、ケンジのやつ、最近あんさんと気まずうなって、めっちゃ落ち込んでるねん」
「ど、どうしてそんな事がわかるの? ケニーくん」
「街で会うた時のあんさんらの雰囲気と、大会でのケンジの様子とのギャップ。あの時とまるで別人のような顔しとるわ、今のあいつ。何があったんか知らんけど、気まずうなったん、大会の前やろ?」
マユミは小さく頷いた。
「あいつは何でもすぐ顔と口に出るねんな。なんでこいつこんな暗い顔しとんのやろ、思て、よう観察しとったら、あれほど熱く語っとったあんさんの話題がぱたっと止んでしもてる。これはもう間違いあれへん、マユミっちゅう妹との関係が悪化しとるんやな、てな」
マユミはあっけにとられてケネスの顔を見つめた。「ケニーくんって……」
「ケンジ、あんさんの気持ちが自分から離れていくんやないか、ってめっちゃ怯えとるんやないかなあ」
「あ、あたしの気持ちがケン兄から離れていく事なんて、あり得ない」マユミが大声を出した。
「わかってるがな」ケネスは微笑んだ。「マユミはんも好きなんやろ? ケンジの事。兄として以上に」
「え? あ、あの……」マユミは赤くなってうつむいた。
「でもな、あいつも年頃の高校生や。あんさんを好きやっちゅう感情が、単に女のコに触りたい、抱きたいっちゅう思春期の一症状やないか、妹であるあんさんをエッチの対象としてしか見てへんのとちゃうかなって迷てるフシがあんねんな、これが」
マユミは独り言のように小さな声で言った。「それは……違うと思う。たぶん……」
「そのくせあいつは、あんさんの優しさにあぐらかいとるんとちゃうかな」
「……」
「あいつにいろいろ気ぃ遣うて、あれこれしてやっとるんやろ?」
マユミはうつむいたまま、少し拗ねたように言った。「あたし、ケン兄の喜ぶ顔が見たい。それだけだもん……」
「それは、たぶんあいつのためになれへんで。マユミはんのためにもなれへんけど」ケネスは人差し指を立てて続けた。「ケンジはあんさんのその気遣いを当たり前や、思い始めてんねん。思い上がりっちゅうかな」
「え? 思い上がり?」マユミは顔を上げた。
「もういっつも横にいて当たり前の存在になっとるやろ? 何しろ元々兄妹やし」
「……」
「ちょっと極端な表現でいやな言い方するとな、ケンジはあんさんを好きな時に自由にできる、思てるねん。意識しとるかどうかはわかれへんねけど。そやからいきなりマユミはんにつれなくされてめっちゃ動揺しとるんやろな」
「でも……」マユミはまたうつむいた。「あたし、ケン兄が疲れてるのに、無理にお茶に誘ったりしたの」
「ほう……ほんで?」
「ケン兄、部活でくたくただから遠慮するって言ったのに、あたし拗ねちゃって……」
「なるほどな」
「だからあたしも同じ……ケン兄はいつもあたしの思い通りに相手してくれるもんだ、って思ってた……」
マユミは切なげな瞳でケネスを見た。
ケネスは優しく微笑んでマユミの肩に手を置いた。
「マユミはんがそない思て後悔しとるんなら心配ないわ」
「え?」
「気の遣い過ぎやし、思いの伝え不足、やな。お互いに」
「……あたし、どうしたらいいか、わからない……」
「マユミはん、わいな、あんさんらに恩返ししたいねん」
「恩返し?」
「日本に来て、一番世話になり、一番のライバルやったケンジが苦しんどる。そしてそいつが大好きな妹もなんやもがいとる。これはもうわいが一肌脱ぐしかないやろ?」
「ごめんね、ごめんね、ケニーくん」マユミは眼に涙を溜めて震える声で言った。
「心配いらへん。わいに任せとき。気まずうて、よう話もできんあんさんに代わってわいがケンジに説教したるわ」ケネスは笑いながらそう言って立ち上がった。「そろそろやつが帰ってくる頃や」
ケネスはマユミの手を取ってその潤んだ目を一瞬見つめ、部屋を出た。
風呂から上がったケンジを待ち構えていたケネスは、彼が部屋に入ってくるなり言った。「ケンジ、おまえに言いたい事があんねけど」
「何だよ」
「マユミはん、えらく落ち込んでるで」
「落ち込んでる?」
「そや」
「あいつは落ち込んでるんじゃなくて、怒ってるんだろ。俺に」
「ちゃうちゃう。おまえもいいかげん意固地になんの止めた方がええで」
「意固地になんかなってねえし」
「おまえ、マユミはんの気持ち、考えてないやろ?」
「何言ってるんだ。俺はあいつの事をいつも気にしてやってる。妹だからな」
「わかってへんな。おまえ、マユミはんがいつも優しく声を掛けてくれる事を『当然や』思てるんとちゃうか?」
「え……」
「今日やのうても明日でええやろ、一緒に暮らしてる仲やし、てな感じで思てたんちゃうか?」
ケンジは動揺したように目を泳がせた。「な、何のこと言ってるんだ? おまえ」
「普通の恋人同士やったら、そない簡単には会えへんのやで? 二人の時間は大切にせな」
「な、何だよ、恋人って」
「何とぼけとるんや。見え見えやがな、おまえら兄妹」
ケンジは頬を赤く染めて困ったような目をした。
ケネスは静かに続けた。
「兄の事を誰よりも思てるマユミはんの言葉を、おまえはちゃんと聞いてやらんかった。おおかたそんなとこやろ。そやからケンカみたいになっとるんとちゃうか?」
「……」ケンジはうつむいてわずかに唇を噛んだ。
「ま、マユミはんがどれだけ兄を想てるか、っちゅうことをおまえ自身、過小評価しとるっちゅうことやな」

少しの沈黙があった。
ケネスは優しく言った。「どうしたらええかわかれへん、ちゅうて、泣いてたで、妹はん」
「えっ?……」ケンジは思わず顔を上げた。
「自分もわがまま言って、ケン兄の気持ちを考えなかった、ちゅうてな」
「そうか……」ケンジはまた目を伏せた。
「おまえとマユミはんが、お互い気まずい思いしたまま背中を向け合って、ケンジが部活にも集中できへんようになって、結果わいのライバルでなくなる事が、わいにとっては一番悔しい」ケネスは笑顔を作って続けた。「また日本に来る時、ケンジが変わらずわいのライバルでいてくれる事が、わいの最大の望みやからな」
ケンジは恐る恐る目を上げた。「どうしたら……いいかな」
ケネスは肩をすくめた。「簡単なこっちゃ。とにかくマユミはんといっぱい話すんやな。都合良く一つ屋根の下に住んどるわけやし」
ケンジは小さくため息をついて、またうつむいた。
「わかり合うっちゅうのんは、お互いへの思いやりがあってこそやで」
「ケニー……」
「わいがここにおる間に、仲直りせなあかんぞ」
ケネスはにっこり笑ってケンジの肩を叩いた。
「わい、大阪の血が混じってるせいか、めっちゃお節介焼きなんや。悪う思わんといてな」
ページ上へ戻るその日の午後。ケンジはケネスを連れて帰宅した。
「紹介するよ。こいつはケニー。ケネス・シンプソン。俺と同い年」ケンジが言った。
「い、いらっしゃい。ゆっくりしていってね。自分の家だと思って」母親が引きつった顔でそう言うのをマユミは隣であきれ顔で見ていた。
ケネスは右手を母親に差し出しながら言った。「よろしゅう頼みますわ。わいケネス・シンプソン言いますねん。愛称ケニー。二晩やけどお世話になります」
「ず、ずいぶん流暢な、」母親が口をぽかんと開けて呟いた。「大阪弁だな」父親が背後で腕をこまぬいて同じように呟いた。
その日の夜。ケニーと共に食卓を囲んだケンジたちは、いつもと違う雰囲気での夕食をとっていた。
「で、ケニーはどうしてそんなに流暢な、その、大阪弁をしゃべるのかね?」父親が切り出した。
「わい、10歳まで大阪に住んでましてん。母親が大阪のおばはんですよってにな。ほんで小学校高学年の時に父親の母国カナダに引っ越したっちゅうわけですねん」
「ほう……」
「カナダでは水泳で記録を持ってるんだって?」母親が訊いた。
「へえ、中学生の時に全国大会まで行きましてな、100mバタフライで三位に」
「そりゃあすごい!」
「わい、自分の能力を伸ばすために今回日本に来ましてん。ほんで水泳の強豪校に留学しとるっちゅうわけですねん」
「バタフライか……。ケンジとライバルってわけね」母親がケンジをちらりと見て言った。
ケネスがミニトマトを口に入れ、もぐもぐさせながら言った。
「それはそうと、ケンジの妹はん、ごっつかいらしな。改めて見ると」
「え?」マユミは海老フライを箸でつまんだまま、動きを止めて顔を上げた。
「ケンジもイケメンやけど、妹はんも素敵なべっぴんさんやで。わいにもこんな妹おったら毎日なんか買うてきたったるけどな。マユミはん……やったな?」
「そう。マユミだ」ケンジがぽつりと言った。
「マユミはん。名前もいけてるやんか。わい、惚れてまうな」
「ふざけんな。ケニー」
ケネスは箸を咥えたまま口をとがらせた。「何やの、冗談やんか。なにキレてんねん、ケンジ」

「もういい。部屋に行くぞ。早く片付けろ」ケンジは食器を持って立ち上がった。
「ごちそうさま。めっちゃうまかったです」
ケネスは丁寧に手を合わせた後、慌てて立ち上がりケンジの後を追った。
「待ってえな、ケンジ」そしてどたどたと階段を上がっていった。
「親しそうだな」後ろ姿を目で追って父親が言った。
「あれを『親しい』というのかしら……」母親も言った。
ケンジの部屋に入ったケネスは、ドアを開けて中に入るなり言った。「さっき荷物置きに来た時も思ったんやけど、」
「何だよ」ケンジが無愛想な口調で言った。
「この部屋、女の子の匂いがするな」
「ぎくっ!」
「彼女、おらんはずやろ? ケンジ」
「い、いないよ、彼女なんか」
「つき合うてる女子、ほんまにおれへんのか?」
「いないって。神に誓って」
「誓わんでもええ」ケネスは鼻をくんくんと鳴らした。「なんでやろなあ……」ケネスはケンジの顔を見た。
ケンジは目をそらして言った。「コーヒー飲むか? ケニー」
「おお、ええな。わいコーヒー好っきゃねん。ごちそうしてくれんの?」
「ああ。待ってな」
ケンジは階段を降りた。丁度降りた所でマユミと鉢合わせをした。「マ、マユ……」
「コーヒー淹れた。今持っていこうと思ってたとこ」
「お、おまえの分も、」
「あるよ。でも自分の部屋で飲むから、気を遣わないで」マユミは自分のカップを手に持つと、二つのカップとデキャンタの載ったトレイをケンジに預けて、自分だけさっさと階段を昇っていった。
「なあなあ、ケンジ、」
「何だよ」
「お前、何で家に帰るなり機嫌悪くなんねん。何かおもろないことでもあんのんか? 家庭に」
「べ、別にないよ……そんなこと」
「それに妹はんも、何か怒ってるみたいなんやけど、気のせいかな」
「ああいうヤツなんだ。まったく可愛げのない」ケンジはぶつぶつ言ってコーヒーカップを口に運んだ。
「おまえら、ケンカしてるやろ。ホントはめっちゃ仲ええんとちゃう? こないだも街でデートしとったし」
「デ、デートなんかじゃない!」
ケンジは自分でもびっくりするぐらいの大声を出した。
「何やの。そないに火ぃ吹いて怒る事かいな」
「だからどうでもいいだろ、妹の事なんか」
ケネスは少し考えていた。そしておもむろに立ち上がった。
「ど、どうしたんだ、ケニー」
ケネスは自分のバッグからごそごそと小さな箱を取り出すと、振り向いてケンジに言った。「仲裁したるわ」
「え?」
ケネスはケンジの持っていたカップを奪い取り、無理矢理トレイに戻すと、それを持ってドアを開け、部屋を出た。
「ほれ、ケンジ、おまえも」
「よ、余計な事を……」

ケンジの焦りをよそに、ケネスはマユミの部屋をノックした。「すんまへん、ケニーです。ちょっとお邪魔してもよろしか?」
しばらくしてドアが開けられた。「何か用? ケニーくん」
「一緒にお茶しまへんか? お土産もありますよってに」
「お土産?」
「そうです。カナダ土産のチョコレート。ほれ、ケンジも早う来んかい。ほたらお邪魔します」
ケネスに促されてケンジはしぶしぶマユミの部屋に入った。
「ん?」
「な、何だよケニー」
ケネスはまた鼻を鳴らした。「この部屋、ケンジの部屋と同じ匂いがすんねけど」
「そ、そりゃあ、同じ家の中だからな。と、当然だろ」
「そうかなあ……」
「ケニーくんのお土産のチョコレートって?」マユミが口を開いた。
「チョコレートお好きですか?」ケネスが訊ねた。
「大好物だ」ケンジが言った。
「ケンジには訊いてへん」
「わ、悪かったよ」
「甘いもんとコーヒー、よく合いますな。ところでマユミはん、ケンジとなんでケンカしてはんの?」
「こ、こらっ、ケニー!」
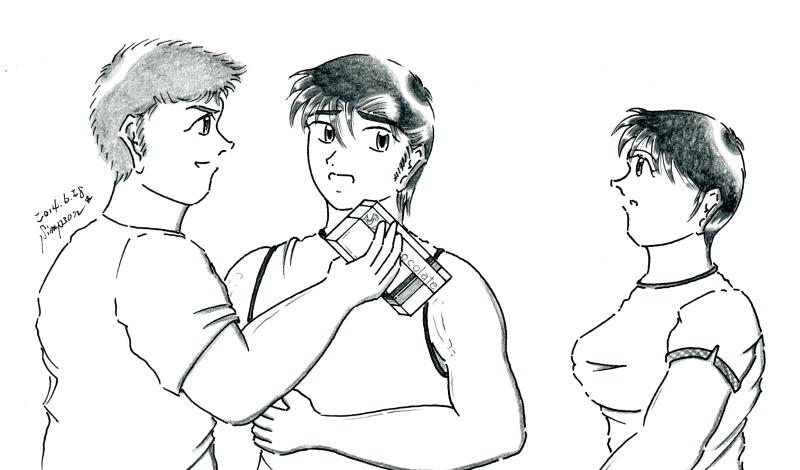
ケネスはあきれ顔でケンジを見た。「あのな、ケンジ、わい三日間もここで暮らすねんで、おまえらの事よう知っとかんといろいろと気まずい事もあるやろ?」
「ケンカ、って言うか……」マユミがうつむき加減で言った。「何でもない。気にしないで、ケニーくん」
「それにしても、ほんまかいらしな、マユミはん」
マユミは恥ずかしげに目をそらした。
「わいの好みのタイプやなー。いや、冗談抜きでやで。でもな、」ケネスが急に小声になった。「わいな、実はバイですねん」
「バイ?」
「誰にも言わんといてな。バイ。『バイセクシャル』。つまり、オトコでも女でも同じように愛せるって事や。あーこんなとこでカミングアウトしてもうた」
「そ、それって……」
「大丈夫や、ケンジ、心配せんでもええ。わいにも理性はある。おまえを夜中に襲ったりはせえへんから心配いらんで」
「当たり前だ! 俺にはそんなシュミはない!」
ケネスはコーヒーを一口飲んだ。「そやけど、便利やで」
「何がだよ」
「好きになる対象の人間が普通の人の倍おるっちゅうことや」
「何だよそれ」
「そやけどな、誤解せんといてな。オトコとみれば誰にでも欲情するっちゅうわけやあれへん。そやから銭湯行ってオトコどものハダカ見てもいつも興奮するわけやないんや」
「へえ」
「『へえ』って。やっぱり誤解してたやろ? ノンケの男かて、女とみれば誰にでも欲情するわけやないやろ? それと同じや。好みのルックス、好みのプロポーション、ドキドキする対象はたまにしかおれへん。それがオトコでもな」
「なるほど」
「そんなん、男湯に入る度に興奮しとったら身がもてへんがな。それは単なる変態や」
「面白い」マユミがクスッと笑った。
ケネスもにっこりと笑って言った。「ああ。笑ろた方が百倍魅力的やで、マユミはん」
「ケニーくんて、ユーモアがある。話を聞いてると和む」
「そりゃ嬉しなあ。っちゅうわけやから、ケンジ、わい、おまえあんまり好みやないねん。そやから夜中襲ったりせえへんから安心しいや」
「変なヤツ」ケンジは遠慮なくあきれ顔をした。
「おお、もうこんな時間や。遅いから寝るわな。ほな、マユミはん、おやすみなさい。ええ夢みてな」
「おやすみなさい」
マユミの部屋を出て、ケネスたちはケンジの部屋に戻った。
「本当におまえおしゃべりだな」
「大阪のおばはんの血が混じってるよってにな」
ケネスはコーヒーの最後の一口を飲み干すと、トレイにそのカップを置いた。「それはそうと、ケンジ、昨日の大会、何であないに調子悪かったんや?」
「……」
「いつものケンジやない、って感じやったけど、何かあったんか?」
ケンジはしばらく考えて口を開いた。「俺、自分でも意志が弱いやつだと思う」
「弱い?」
「そう。些細な事が気になって、大切な時に集中できなくなっちまってた」
「いやあ、今までのケンジやったら多少の事で力を出せなくなったりせえへんやろ。……そうか、今回のは些細な事やなかった、っちゅうことやな。何? どないしたんや? 言うてみ」
ケンジは少しの間黙っていたが、やがて決心したように顔を上げた。「大会の時の俺を見てほしい人に見てもらえなかった、とだけ言っとくよ」
「へえ」ケネスも少し考えて続けた。「いつもその人はケンジを大会の度に見に来てくれてたんか?」
「ああ。いつも。欠かさずな」
「待てよ、おまえ彼女おれへんかったんちゃうか?」
「いや、彼女とは違うから」
「女の人か?」
「もういいだろ。俺も大会でいい結果出せなかったから落ち込んでんだ。蒸し返さないでくれ」
「何やの、自分から言い出したくせに……。勝手なヤツやな」
「い、今言ったことは忘れてくれ」ケンジは焦ったようにカップを口に運んだ。
「ま、いいけどな。ん?」ケネスは、ケンジのベッドの布団の隙間から白い布が少しだけ出ているのに気づいた。
彼はそれを引きずり出して広げた。「なんや? これ」
「あっ! やめろ。そ、それに触るなっ!」
「おおっ! 女物のショーツやんか!」
「よこせっ!」ケンジはケネスの手からそのマユミの下着を奪い取った。そして真っ赤になった。

「考えられる事その1、ケンジは普通の高校生で、女子の下着に興味があり、それを一人エッチのアイテムにしている。その2、実はケンジは女装癖があり、夜な夜なそれを穿いて近所を出歩いている。さあ、どっちや? 白状しい」
「残念ながら前者だよ。そんな格好で外を出歩くわけないだろっ!」
「わいはいっぺんぐらい、そんな下着一枚で表、出歩きたい、思てるで。考えただけで興奮するやんか」
「俺はノーマルなんだよ。お前みたいな変質者じゃない」
「『変質者』。ええ言葉やなー」ケネスは笑った。「ほたら、そのショーツの元の持ち主は誰なんや? 考えられる事その1、マユミはんの干してあった洗濯物に手をつけた。その2、母親の干してあった洗濯物に手をつけた。その3、自分で購入した」
「なんでそんな事いちいち聞く必要があるんだよ。いいかげんにしろ」
「いやいや、これは男同士で語らう話題の定番、エロトークの一種やないか。あんまり深く考えんと、答えるんや、さあ!」
「エロトークって……おまえな」
「最も簡単に手に入るんは妹はんのやろけど……。見たところお母はんの年代が穿くようなショーツではなさそうや」
ケンジはぶっきらぼうに言った。「そうだよ。マユのだよ。悪いか」
ケネスはにっこりと笑った。「ケンジは健全やな」
「誰にも言うなよ」
「言わへんて。それにわい、明後日には日本からいなくなるよってにな、話したくても面白がって聞いてくれる人、残念ながらカナダにはおれへん」
「そういう問題じゃない」
「なあ、ケンジ、正直に遠慮なく言わしてもらうけどな、おまえとマユミはん、雰囲気おかしいで」
「な、何だよ、いきなり」
「何度も言うようやけど、ほんまはもっと仲ええんやろ? こないだのデートの時の雰囲気とはえらい違いやないか」
「だから、デートじゃないって」
「それにやな、学校でもいつもおまえの口からマユミはんの名前が出てくるやんか。にこにこ生き生きして語っとるやん」
「た、たまたまだ。そんなのおまえの思い過ごしだ。別に普通の兄妹だし」
「そうか? そうかなあ……」
ケネスは目を閉じて腕組みをした。
「もう遅いから寝るぞ」ケンジは客用の布団を床に敷き始めた。そしてさっさと自分はベッドにばたんと倒れ込み、灯りを消してしまった。
「おいおい、ケンジ、お客さんに対して失礼やないか。なんやの、勝手に電気消さんといて」
ケネスも仕方なくケンジが敷いてくれた布団に横になった。
◆
明くる月曜日。朝からケンジと一緒に学校へ行ったケネスは、夕方ケンジよりも先に帰ってきた。
「ただいま帰りました」
「お帰りなさい。ケニー、先にお風呂いいわよ」母親が促した。
「すんまへん。ほな遠慮なくいただきます」ケネスはそう言って、二階のケンジの部屋に入っていった。
着替えを持って階下に降りる前に、すでに部屋にいたマユミに声を掛けた。「マユミはん、お風呂先にいただいてもええですか?」
「あ、ケニー君。お帰り。いいよ。あたし先に済ませたから」
「そうでっか。ほな」
ケネスは階段を降り、浴室に入った。
風呂上がり、ノースリーブ姿のケネスは、マユミの部屋をノックした。
「どうぞー」
「すんまへん。お邪魔してもええですか?」ケネスは手にチョコレートの箱を持っていた。
「いいよ。どうぞ」マユミはケネスを部屋に招き入れた。
「はい、これ、マユミはんの好きなチョコレート・アソート」
「え? どうしてあたしが好きなチョコレートを?」
「ケンジに訊きましてん」
「そ、そうなんだ……」
「ケンジ、ちょっと遅くなる言うてた」
「ふうん」マユミはそのつれない反応とは裏腹に、ひどく残念そうな顔をした。
ちらりと横目でその様子を見たケネスは静かに口を開いた。
「マユミはん、伝えたい事、あんねけど」
「え? 何?」
「ケンジな、こないだの大会、全然あかんかってん」
「知ってる」
「その原因がな、言いにくい事なんやけど、マユミはんなんや」
「え? あたし?」
「マユミはん、ケンジが出場する大会には毎回欠かさず行ってたんちゃうか?」
「え?」
「ほんで、昨日は初めて見に行ってやらなんだ。そやろ?」
「と、友だちと約束があったから……」マユミはケネスから目をそらした。
「裏付け完了」ケネスは小さく言った。
ケネスは後ろの床に手をついて、マユミを見た。
「ケンジはそんな事一言も言わへんのやけど、わい、あいつと話してるとわかるんや」
「え?」
「ケンジにとってマユミはんが欠かせない人なんやっちゅうことが」
「…………」
「わいな、もう何週間もケンジと一緒に学校で過ごしとって、はっきり解る事が一つだけあんねん」
「はっきり解る……事?」
「そや。ケンジはあんさんの事が大好きやって事」
「えっ?!」
「それも、ただの妹としてではのうて、一人の女のコとして誰よりも好きなんやって事」
「そ、それは……」マユミは焦ったように目を泳がせた。
「毎日毎日顔合わせる度に、わいケンジからあんさんの事聞かされてきた。今日は妹がどうしたーとか、マユの好きなのはメリーのチョコレートでーとか。そらもう会話の8割はあんさんネタや」
「そ、そうなんだ……」
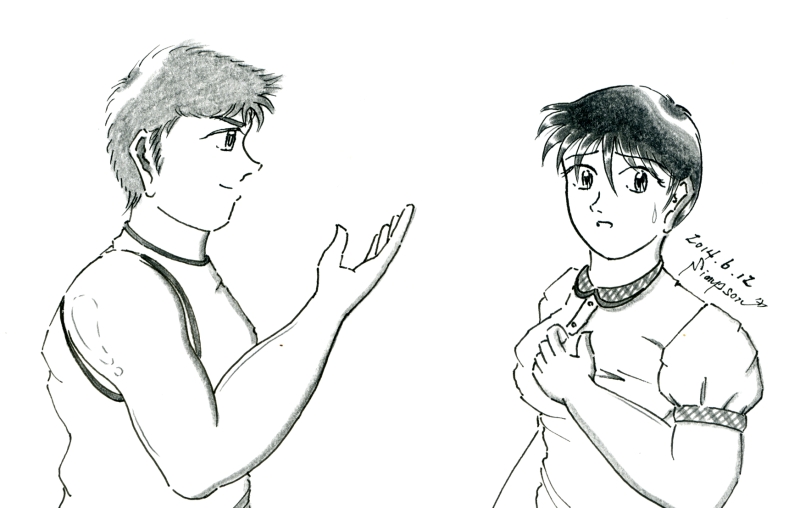
「でもな、ケンジのやつ、最近あんさんと気まずうなって、めっちゃ落ち込んでるねん」
「ど、どうしてそんな事がわかるの? ケニーくん」
「街で会うた時のあんさんらの雰囲気と、大会でのケンジの様子とのギャップ。あの時とまるで別人のような顔しとるわ、今のあいつ。何があったんか知らんけど、気まずうなったん、大会の前やろ?」
マユミは小さく頷いた。
「あいつは何でもすぐ顔と口に出るねんな。なんでこいつこんな暗い顔しとんのやろ、思て、よう観察しとったら、あれほど熱く語っとったあんさんの話題がぱたっと止んでしもてる。これはもう間違いあれへん、マユミっちゅう妹との関係が悪化しとるんやな、てな」
マユミはあっけにとられてケネスの顔を見つめた。「ケニーくんって……」
「ケンジ、あんさんの気持ちが自分から離れていくんやないか、ってめっちゃ怯えとるんやないかなあ」
「あ、あたしの気持ちがケン兄から離れていく事なんて、あり得ない」マユミが大声を出した。
「わかってるがな」ケネスは微笑んだ。「マユミはんも好きなんやろ? ケンジの事。兄として以上に」
「え? あ、あの……」マユミは赤くなってうつむいた。
「でもな、あいつも年頃の高校生や。あんさんを好きやっちゅう感情が、単に女のコに触りたい、抱きたいっちゅう思春期の一症状やないか、妹であるあんさんをエッチの対象としてしか見てへんのとちゃうかなって迷てるフシがあんねんな、これが」
マユミは独り言のように小さな声で言った。「それは……違うと思う。たぶん……」
「そのくせあいつは、あんさんの優しさにあぐらかいとるんとちゃうかな」
「……」
「あいつにいろいろ気ぃ遣うて、あれこれしてやっとるんやろ?」
マユミはうつむいたまま、少し拗ねたように言った。「あたし、ケン兄の喜ぶ顔が見たい。それだけだもん……」
「それは、たぶんあいつのためになれへんで。マユミはんのためにもなれへんけど」ケネスは人差し指を立てて続けた。「ケンジはあんさんのその気遣いを当たり前や、思い始めてんねん。思い上がりっちゅうかな」
「え? 思い上がり?」マユミは顔を上げた。
「もういっつも横にいて当たり前の存在になっとるやろ? 何しろ元々兄妹やし」
「……」
「ちょっと極端な表現でいやな言い方するとな、ケンジはあんさんを好きな時に自由にできる、思てるねん。意識しとるかどうかはわかれへんねけど。そやからいきなりマユミはんにつれなくされてめっちゃ動揺しとるんやろな」
「でも……」マユミはまたうつむいた。「あたし、ケン兄が疲れてるのに、無理にお茶に誘ったりしたの」
「ほう……ほんで?」
「ケン兄、部活でくたくただから遠慮するって言ったのに、あたし拗ねちゃって……」
「なるほどな」
「だからあたしも同じ……ケン兄はいつもあたしの思い通りに相手してくれるもんだ、って思ってた……」
マユミは切なげな瞳でケネスを見た。
ケネスは優しく微笑んでマユミの肩に手を置いた。
「マユミはんがそない思て後悔しとるんなら心配ないわ」
「え?」
「気の遣い過ぎやし、思いの伝え不足、やな。お互いに」
「……あたし、どうしたらいいか、わからない……」
「マユミはん、わいな、あんさんらに恩返ししたいねん」
「恩返し?」
「日本に来て、一番世話になり、一番のライバルやったケンジが苦しんどる。そしてそいつが大好きな妹もなんやもがいとる。これはもうわいが一肌脱ぐしかないやろ?」
「ごめんね、ごめんね、ケニーくん」マユミは眼に涙を溜めて震える声で言った。
「心配いらへん。わいに任せとき。気まずうて、よう話もできんあんさんに代わってわいがケンジに説教したるわ」ケネスは笑いながらそう言って立ち上がった。「そろそろやつが帰ってくる頃や」
ケネスはマユミの手を取ってその潤んだ目を一瞬見つめ、部屋を出た。
風呂から上がったケンジを待ち構えていたケネスは、彼が部屋に入ってくるなり言った。「ケンジ、おまえに言いたい事があんねけど」
「何だよ」
「マユミはん、えらく落ち込んでるで」
「落ち込んでる?」
「そや」
「あいつは落ち込んでるんじゃなくて、怒ってるんだろ。俺に」
「ちゃうちゃう。おまえもいいかげん意固地になんの止めた方がええで」
「意固地になんかなってねえし」
「おまえ、マユミはんの気持ち、考えてないやろ?」
「何言ってるんだ。俺はあいつの事をいつも気にしてやってる。妹だからな」
「わかってへんな。おまえ、マユミはんがいつも優しく声を掛けてくれる事を『当然や』思てるんとちゃうか?」
「え……」
「今日やのうても明日でええやろ、一緒に暮らしてる仲やし、てな感じで思てたんちゃうか?」
ケンジは動揺したように目を泳がせた。「な、何のこと言ってるんだ? おまえ」
「普通の恋人同士やったら、そない簡単には会えへんのやで? 二人の時間は大切にせな」
「な、何だよ、恋人って」
「何とぼけとるんや。見え見えやがな、おまえら兄妹」
ケンジは頬を赤く染めて困ったような目をした。
ケネスは静かに続けた。
「兄の事を誰よりも思てるマユミはんの言葉を、おまえはちゃんと聞いてやらんかった。おおかたそんなとこやろ。そやからケンカみたいになっとるんとちゃうか?」
「……」ケンジはうつむいてわずかに唇を噛んだ。
「ま、マユミはんがどれだけ兄を想てるか、っちゅうことをおまえ自身、過小評価しとるっちゅうことやな」

少しの沈黙があった。
ケネスは優しく言った。「どうしたらええかわかれへん、ちゅうて、泣いてたで、妹はん」
「えっ?……」ケンジは思わず顔を上げた。
「自分もわがまま言って、ケン兄の気持ちを考えなかった、ちゅうてな」
「そうか……」ケンジはまた目を伏せた。
「おまえとマユミはんが、お互い気まずい思いしたまま背中を向け合って、ケンジが部活にも集中できへんようになって、結果わいのライバルでなくなる事が、わいにとっては一番悔しい」ケネスは笑顔を作って続けた。「また日本に来る時、ケンジが変わらずわいのライバルでいてくれる事が、わいの最大の望みやからな」
ケンジは恐る恐る目を上げた。「どうしたら……いいかな」
ケネスは肩をすくめた。「簡単なこっちゃ。とにかくマユミはんといっぱい話すんやな。都合良く一つ屋根の下に住んどるわけやし」
ケンジは小さくため息をついて、またうつむいた。
「わかり合うっちゅうのんは、お互いへの思いやりがあってこそやで」
「ケニー……」
「わいがここにおる間に、仲直りせなあかんぞ」
ケネスはにっこり笑ってケンジの肩を叩いた。
「わい、大阪の血が混じってるせいか、めっちゃお節介焼きなんや。悪う思わんといてな」
感想を書く
この話の感想を書きましょう!
全て感想を見る:感想一覧
