| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |
Chocolate Time
作者:Simpson
しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。
ページ下へ移動第1章 双子の兄妹
1-2 兄妹
兄妹
1-2 兄妹
すずかけ高校の室内プールは、校地の北の端に位置していた。その建物は二階建てで、一階にある水泳部の部室の横にロッカールーム。その奥に会議室と食堂。二階に25m6コースのプールがあり、奥には事務所と教官室、反対側にミーティングスペースを兼ね備えた、トレーニングマシーンが並べられた広いジムがあった。
クールダウンのために軽く500mを泳いだケンジは、プールから上がるなり、二人の友人に声を掛けられた。
「なんでこの学校に一緒に入学しなかったんだ? ケンジ」色白で痩せた拓志がいきなり言った。
「誰と?」ケンジがキャップを脱ぎながら言った。
「妹のマユミちゃんだよ」
もう一人の小太りの康男がにやにやしながら言った。「マユミちゃん、かわいいよな」
「ふんわりしてそうで、抱き心地いいだろうな」
「いやらしい目で妹を見るな」
「なんだよ、おまえシスコンか?」
「そんなんじゃない」
「俺たちの誰かがマユミちゃんに告白したら、おまえどうする?」
「どうする、って……」
ケンジは思いっきり困った顔をした。
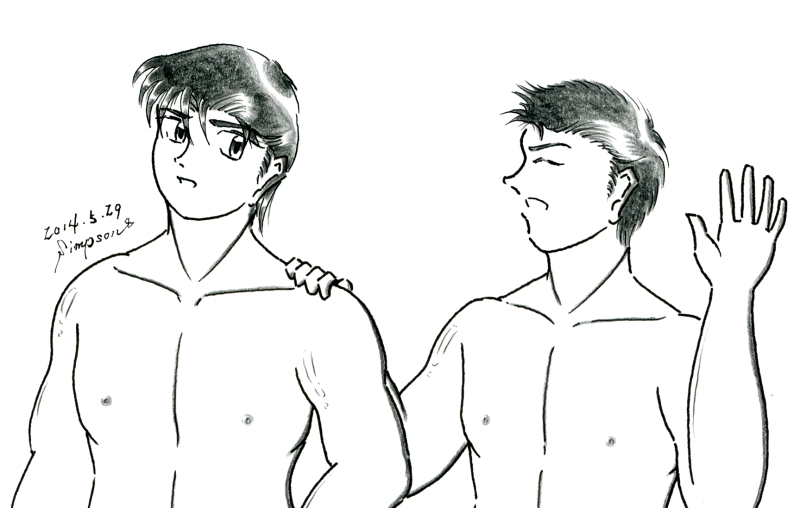
「やっぱ反対するのか? 兄として」
「っつーか、こいつとマユミちゃん双子だろ?」康男がケンジの肩を人差し指で小突いた。「そんなの『兄』って言うのか?」
「どうなんだ? ケンジ」
「ど、どうって?」
「どんな目で見てるんだ? おまえ、マユミちゃんを」
「ふ、双子でも妹だ。それ以上でも以下でもない」
「ふうん」拓志があまり納得していない様子で言った。「そんなもんなんだな」
「でもよ、」康男がにやにやしながら言った。「マユミちゃんと一緒に暮らしてっと、妙な気にならねえか? ケンジ」
「なんだよ、妙な気、って」
「あの巨乳、おまえいつも見てるんだろ? 風呂上がりとか」
「そそられるよな、確かに」拓志もにやにやしながら言った。
「み、見ないよ」ケンジは赤くなって二人から目をそらした。
「思わず触りたくなるよな」
「触っちまったら、絶対そのまま押し倒してやっちまいそうだな」
「マユミちゃんとヤれたら気持ちいいだろうなー」
「いいかげんにしろ!」
ケンジは鋭く二人を睨み付けて恫喝した。
拓志も康男もびっくりして黙り込んだ。
「じょ……冗談だって。ケンジ、本気にするなよ」
「そ、そうだ。単なる妄想だ。気にすんな。ケンジ」
その日の夕食時、いつになく口数少なく、おかずも半分以上残して食卓を立ったマユミの背中をケンジはいぶかしげに見送った。
ケンジは向かいに座った母親に訊いた。「どうかしたの? マユのやつ」
「さあね」母親はそう言って麦茶のコップを手に取った。
「昨日からずっとあんな感じだよね」
「そうね。なに? あんたそんなに心配? 妹が」
横で肉じゃがの人参を箸で持ち上げながら、父親が無言のままちらりと目を上げた。
「べ、別に心配ってわけじゃ……」ケンジは茶碗のごはんを口に掻き込んだ。
「たまには慰めてやったらどうだ? ケンジ」父親が言った。
「そうね、兄妹なんだし」母親も言った。
「ごっそさん」
ケンジは食器を持って立ち上がった。
夕食を済ませた後、ケンジは自分の部屋で宿題を始めたが、なかなか集中できずにペンを置いた。そして小さなため息をついた後、立ち上がり、部屋を出た。
彼は、隣のマユミの部屋のドアをノックした。
「マユ、いるか?」
「あ、ケン兄、どうしたの?」
「開けるぞ」
ドアを開けると女の子特有の甘い香りがケンジの鼻をくすぐった。マユミは机に向かっていた顔を兄に向け直した。
「あ、あのさ、おまえの好きなチョコレートがあるんだ。部屋に来ないか?」
「ほんとに?」マユミは椅子から立ち上がった。しかし、すぐに怪訝な顔をした。「って、どうして?」
「どうして、って……」ケンジは一瞬言葉に詰まった。「いいから、来いよ」
「う、うん」
ケンジの部屋に入ったマユミが躊躇いがちに言った。「あたし、お茶淹れてくる。ケン兄、何がいい?」
「え? あ、ああ、俺コーヒーが……い、いや、マユに合わせる。何でもいい」
「じゃあ紅茶でもいい?」
「ああ。いいぞ」ケンジはぎこちなくもにっこりと笑った。
マユミはドアを出た。
ケンジの部屋のカーペットに座って、二つのカップにティーポットから紅茶を注ぎながらマユミは訊ねた。「ほんとに紅茶で良かった? ケン兄」
「いいよ」
「珍しいね、ケン兄がお茶に誘ってくれるなんて」
「い、いや、チョコレートもらったから。おまえ好きだろ?」
「いいの? 誰からもらったの?」
「友だちだよ」
「女の子?」
ケンジはカップを手に取った。「ま、まあな」
「えー。いいのかな、あたしが食べても」
「遠慮するなよ。俺がもらったんだから。俺がどうしようと勝手だろ」
「でも、偶然だね」
口にカップを運びかけた手を止めて、ケンジが言った。「何が?」
「あたし、このチョコ大好きなんだ。メリーのアソート」
ケンジは少し腰をもぞつかせて、紅茶を一口飲んだ。「そ、そうか。良かったな」

「じゃ、いただきまーす」
マユミはそのアソートのチョコレートに手を伸ばした。
「どれにしようかなー」
マユミのその仕草を見ながらケンジは自分の鼓動が速くなっていくのを感じた。
ケンジは一週間程前、自分の洗濯物をベランダで干している時に、隣の部屋のマユミが着替えをしているのを偶然見てしまった。妹のマユミは気づかなかったようだが、ケンジはその時彼女の白くて柔らかそうな肌に目が釘付けになってしまったのだった。その身体つきは、あのグラビアのモデルによく似ていた。ショートカットで幼さが残る髪、豊かな胸の膨らみ、腰のくびれ……。
双子の兄妹なので、小さい頃から例えば入浴も一緒だった。しかしそれも小学校5年生までで、当時のマユミとは全く別人のような艶っぽい部屋の中のその姿に、ケンジの呼吸は自然と荒くなり、股間も熱を帯びていった。ケンジは焦って部屋に駆け込んだのだった。
「おまえさ、最近元気ないけど、何かあったのか?」
唐突にケンジが言ったので、マユミは、つまみ上げたチョコレートを思わず取り落としてしまった。
「え?」
「明らかに落ち込んでるように見えるけど」
「……」
マユミは落としたチョコレートを箱に戻した。
「ケン兄……心配してくれるんだね」
「そ、そりゃそうだ。当たり前だろ、兄妹なんだから」ケンジは顔を赤くして焦ったように言った。
「そうだね、兄妹だもんね。ごめんね、ありがとう……」
マユミの眼に涙が滲んだ。
「お、俺で良ければさ、話してみろよ。話せばすっきりする事だってあるだろ」
ケンジの優しい声を聴いて、マユミの眼に溜まった涙がぽとりと落ちた。
「マユ……」
マユミは決心したように顔を上げた。「ケン兄」
ケンジはぎこちない微笑みを返した「どうしたんだ?」
「あたし……あたしね、先輩に抱きつかれた……」
「えっ?! だ、抱きつかれた?」
マユミはコクンと頷いた。
「い、いつ?」
「昨日」
「そ、その先輩って?」
「うん。つき合ってた先輩……」
「お、おまえ彼氏がいたのか?」
「彼氏……って言うか……」マユミは言葉を濁した。
「で? 何されたんだ? 抱きつかれただけだったのか?」
ケンジは少し興奮気味にマユミに訊いた。
「メールではよく話してたけど、リアルにはあんまり会ってなかった。先輩部活で忙しい人だから。だから『彼氏』って言う程の関係じゃなかった……ってあたし、思ってた」
「そ、それで、昨日、おまえ……」
「初めて街でデートして、先輩の家に呼ばれて、部屋で……」
マユミは言葉を詰まらせ、唇を噛みしめた。
「ら、乱暴されたのか? ま、まさか、む、無理矢理……」
ケンジは身を乗り出し、顔を赤くして声を荒げた。
マユミは指で涙を拭い、寂しそうに微笑んでケンジを見た。「ううん。服脱がされたりしたわけじゃないんだ。いきなり抱きつかれて、その……」
ケンジは固唾を呑んでマユミの次の言葉を待った。
「む、胸に触られた……」
またマユミの眼から涙がぽろぽろとこぼれた。
「む、胸に……」ケンジはようやくそれだけ言って、腰を浮かせたまま固まった。
彼はうつむいたままのマユミの胸元を見た。ゆったりとした裾の短いTシャツの大きく開いた襟の奥に、ブラに包まれた彼女の大きなバストの谷間がちらりと見えた。ケンジは慌てて目をそらし、自分の胸を手で押さえた。図らずも鼓動は速く大きくなっていて、彼はそれを必死で落ち着かせようと焦った。
しばらく沈黙の時が流れた。
「その先輩にされたのって、それだけ……だったのか? マユ」
「……うん」
「いやだった……んだな」ケンジは紅茶を一口飲んだ。「で、でも良かったな、それだけで済んで」
マユミは顔を上げて、ケンジを睨むような目で見た。
「男のコって、みんなそうなの?」
「えっ?!」
「高校生の男子って、みんなそんな事したい、って思ってるわけ? チャンスがあったら、女のコの身体に触りたいって」
ケンジはまるで自分が責められているような気がして、身体を固くしてうつむいた。
マユミは自分が発した言葉の熱さと鋭さにいささかたじろいで、思わず息を呑み、慌てて続けた。「あっ……、ご、ごめん、ケン兄。あたし、ケン兄を責めてるわけじゃなくて……」
「わ、わかってる」
「あたしの事、心配してくれてるのに、きつい態度だったね……ごめん……」
「無理もないよ。それだけショックだったんだろ? マユ」
「う、うん……」
「初めてのデートでそんな事されたら、やっぱりショックだろうな、女のコは……」
マユミはティーポットからケンジのカップに紅茶をつぎ足した。「ケン兄には、彼女がいるの?」
ケンジは意表を突かれて身体を一瞬小さくびくつかせた。
「つき合ってる子、いるの?」
「い、いないよ」
「ほんとに? だって、ケン兄モテモテなんでしょ?」
「し、知らないよ、そんなの」ケンジは顔を赤らめ、マユミから目をそらした。
「あたしの学校の部活の友だちもみんな言ってるよ、ケンジ君素敵だ、って」
「な、なんでそんな事……」
「それにケン兄、学校でも、もう何人もの女子に告白されてるんでしょ? 噂はあたしの学校まで届いてるよ」
「な、何人ものって……お、大げさだよ」
事実、ケンジは所属している部活のみならず、他のクラス、他の学年の女子生徒からもほぼ毎月のように告白まがいの行為を受けていた。
「いるの? 彼女」
「い、いないってば」
「じゃあさ、どうなの? もし彼女ができたら、一刻も早く抱いたりキスしたいって思ったりする?」
「い、一刻も早くって……」ケンジは思いきり困ったように顔を歪めた。「そ、そりゃあ、俺だってオトコだし、そんな気になるかも……知れないけど」
「やっぱり?」
マユミが少しがっかりしたように肩を落としたのを見て、ケンジは慌てて付け加えた。「で、でも、俺は相手の気持ちを確かめずに、そんな事しないぞ」
「ほんとに?」
「だ、だって、そんな事したら、いっぺんに嫌われちまうじゃないか」
「そんな冷静な判断ができるの?」
「た、確かにその時になったら、どんな行動に出るか……わからないけど……、でももしやっちまった、って思ったら、俺ならきっと速攻で謝る」
顔を真っ赤にして、必死で訴えるように真剣な顔をしている目の前のその兄を見て、マユミはほっとしたように小さなため息をつき、柔らかく微笑んだ。
「ケン兄優しいからね。きっとそうだね」そしてカップを口に運んだ。
「その先輩とは、別れたのか?」
「うん。もう会わないってメールした」
「で、そいつは諦めたのか? おまえを」
「それからメールもこないし、学校ですれ違っても何もない」
「そうか……」ケンジも冷めてぬるくなった紅茶を口にした。
「しばらくは、そんな時ちらっとあたしを見て、申し訳なさそうな顔をして目をそらしてた」
「後悔してるんだな、そいつも。きっと突っ走り過ぎた、って思ってるんじゃないか?」
「そうだね。たぶん……」
「だけど、謝って、またつき合い続けたい、って言ってきたわけじゃないんだな」
「そこまであたしの事、思ってくれてたわけじゃなかったんだよ、きっと。先輩もあたしの事を彼女だってあんまり意識してなかったんじゃないかな」
ケンジは肩をすくめた。「なるほどな……」
「ごちそうさま。ケン兄、ありがとうね」
マユミはすっきりした顔でにっこり笑うと、カップをトレイに戻した。「何だか気が晴れた。こんな話聞いてくれる男子って、考えてみればケン兄しかいないね。ほんとにありがと」
「気にするな」ケンジも少しこわばったような微笑みを返した。
「やっぱりさ、つき合うにしても、まずこうやって直接いっぱい話さなきゃだめだね。メールなんかじゃだめだよ、うん」
マユミは自分を納得させるように言ってトレイに手を掛けた。
「ま、また何かもらったりしたら誘うから」
「嬉しい。期待してる」マユミはウィンクをした。
ケンジはどきりとした。そしてますます目の前の、そのある意味無防備な態度の妹に対する想いの温度が上がっていく感じがした。
「じゃあ片付けるね」
「いや、俺が片付けるよ」
「あたしがやらなきゃ。ごちそうになったんだもの」
「おまえ勉強の途中だろ。俺に任せろ。時々こういう事をしとけば母さんに好印象だろ」
マユミは笑った。「そういう事かー。じゃあ、お願い」
マユミと一緒に立ち上がって、ケンジは彼女を隣の部屋まで送った。マユミの身体からほんのりとバニラの香りがした。そしてほのかな彼女の体温を感じてケンジはまた鼓動を速くした。
「ケン兄が彼氏だったら、素敵だろうな」
マユミは屈託のない笑顔でそう言って部屋の中に消えた。
部屋に戻ったケンジは、マユミが座っていた所に彼女の小さなハンカチが置き忘れてあるのに気づいた。彼はそれを恐る恐る手にとって、自分の鼻に近づけた。やっぱりバニラの香りがした。妹が座っていた場所に同じように座ってみた。彼女の温かさがまだ少し残っていた。そして妹が使ったカップを手に取った。彼女が口をつけたカップの縁にそっと自分の唇を押し当てた。ケンジの鼓動はますます速く、強くなっていった。

その夜、ベッドで寝ていたマユミは、かすかな物音と人の声に気づいて目を開けた。それは隣のケンジの部屋から壁越しに聞こえてくる。「ケン兄、こんな夜中に何してるのかな……」
マユミは耳を澄ました。ベッドが軋む音とケンジの小さな声。小さな声で「マユ」と呟いているようにも聞こえる。
「えっ? あたし?」
マユミそっとベッドから起き上がり、音を立てないようにベランダに出てケンジの部屋の中を窺った。
「なに? ケン兄、具合でも悪いのかな……」
ベッド脇の小さなライトだけが灯っていた。その黄色い光の中でケンジはベッドにうつ伏せになって、両腕できつく抱きしめた枕に鼻と口をこすりつけながら喘いでいる。荒い息で彼は時折、確かに「マユ」と呟いている。目を凝らしてよく見ると、彼が鼻と口をこすりつけているのは、自分がケンジの部屋に置き忘れたらしいハンカチだった。やがて兄の腰が上下に激しく動き始め、掛かっていた薄いタオルケットがベッドから滑り落ちた。彼は黒の下着一枚という姿だった。それを見たマユミは焦ったように部屋に戻った。彼女の胸の鼓動は大きく、速くなっていた。
◆
8月1日。火曜日。
その日、県下の高校水泳部が集まる競泳の大会が開催された。
マユミの学校の女子部員は、男子バタフライのプログラムが始まると、こぞって観覧席の最前列に陣取り、スタート台に立つケンジに熱い視線を送ってきゃーきゃー騒ぎ合った。マネージャのマユミは、自分のチームの男子選手の記録を取るべく、プールサイドにストップウォッチを手に立っていたが、下からそのいつもの光景を見て、困ったような、それでも少し誇らしいような気持ちになっていた。
「もう……恥ずかしいったら……」
マユミは小さく独り言を言って、ため息をついた。
スタートのアラームが場内に鳴り響いて、選手は一斉に水に飛び込んだ。
最初のバサロですでにケンジは他の選手を圧倒していた。彼が頭を出した時には、もう半身以上の差をつけ、そのまま100m安定した泳ぎでトップを維持し、余裕でゴールした。
そんな接戦でもないレース展開にも関わらず、観覧席からは黄色い声がのべつ送られていた。ケンジを目で追う女子たちである。レースが終わって観覧席を見上げたマユミは、自分の学校の生徒だけでなく、他の学校からもたくさんの女子生徒がケンジの一着ゴールに大騒ぎしている姿を目の当たりにした。
学校の部員たちの荷物を並べ直していたマユミの背後から声がした。
「今日も凄かったよね、マユミ」
そして駆け寄ってきた美穂がマユミの背中をばしばし叩きながら興奮したように飛び跳ねた。
「ちょ、ちょっと、痛いんだけど、美穂」マユミは遠慮なく迷惑そうな顔をして、美穂の腕を払いのけた。
美穂は構わず言った。「もう、最高じゃん、ケンジ君。あたしコクろうかな、真剣」
「な、なんでケン兄がそんなに……」
横から別の部員が言った。「だってそうじゃない、最高のイケメンだし、身体つきもかっこいいし」
「そうそう」美穂だった。「他の男に比べて、ごりごりのマッチョでもないし、バランスいいよね」
「それにさ、あたし会場の入り口でおばあちゃんの荷物持ってあげてるケンジ君、見たよ」
「あたしも、」違う部員が首を突っ込んできた。「ゴーグル落として気づかないで歩いてたよその男子生徒に、それを拾って手渡してた」
「誰でもするよ、そんな事」マユミが恥ずかしげに言った。
「違うって、その時ケンジ君、ちゃんと両手で差し出して、にこにこしながら『お疲れ、次のレースもがんばって』って言ってた」
「すごいよね、敵のしかも男子なのに、そんな言葉かけができるんだから」
「親切だけど媚びないし、優勝しても威張らないし、」
「そうそう、メダル掛けてもらう時の、少し赤くなってはにかんだような顔と態度、もうめちゃめちゃ胸キュンだよー!」
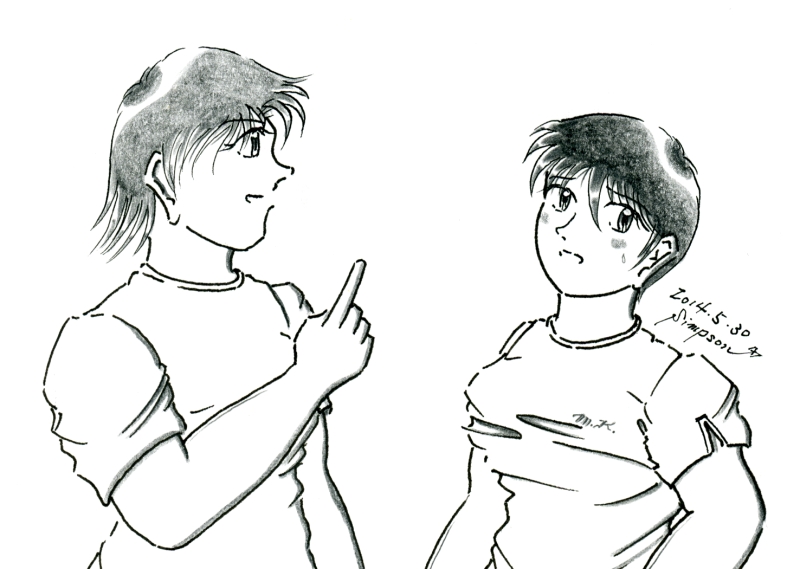
マユミはそう言って騒ぐ部員たちを見ながら、自分の双子の兄が女のコに人気がある理由が今さらながらわかったような気がした。
美穂がにこにこ笑いながら言った。「マユミ、」
「え? なに?」
「あんた本当に幸せだね、あんな男のコと一つ屋根の下で暮らせるなんて」
「な、何言ってるんだよ。兄妹だから当然でしょ」
美穂は心底羨ましそうに言った。「贅沢だよ。あたしたちが簡単にできない事、あんたにはできるんだから」
「か、簡単にできない事?」
「一緒に話したり食事したり、プレゼントあげたり……」
「あたしケン兄にプレゼントなんかした事ないよ」
「それ以上の事、できるじゃん。それにもし、あんたがその気になればハグしてもらったりキスしてもらったりもできるんじゃない?」
美穂は悪戯っぽく笑った。
「無理無理無理!」マユミは耳まで真っ赤になって大声を出した。
美穂はにわかに声を落とし、冷静に抑揚を抑えた口調で言った。
「何よ、わかってるよ、そんな事。兄妹なんだから、あんたとケンジ君。冗談だから。そんな力一杯否定すると、まるであんたがケンジ君に気があるのかも、って勘違いしちゃうでしょ」
マユミは顔を赤くしてまま黙り込んだ。
「ケンジ君だったらアキラ先輩みたいに野獣にはならないね、きっと」
「えっ?!」
「そう思うでしょ? マユミも」
「そ、そうだね……確かに。あの人優しいし……」
「やっぱり優しいんだ」美穂は目を輝かせた。「妹のあんたにも優しいんだったら間違いないよね。あたし本気でコクっちゃお、今度」
「え、あ、あの、美穂、で、でもケン兄優柔不断だし、優しいって言っても、そ、その、単に臆病なだけ……だから」
「いいんだ、それでも」
美穂は指を組んでうっとりしたように上目遣いで中空を見た。「彼は絶対、オトコの中の残り1㌫だよ。ユカリが言ってた通り」
マユミは、そんな美穂の様子をちょっと疎ましげに見やった。
「そうそう、マユミ、」
「な、なに?」
「あたしさ、兄妹で愛し合うっていう本、持ってるよ。貸してあげる」
そう言いながら美穂は自分のエナメルバッグを漁り始めた。
「ええっ? な、何それ!」
「ライトノベルなんだけど、『兄貴に胸キュン!』っていうの。兄妹で一線を越えちゃう、っていう話。なかなか面白くてどきどきしちゃうよ。あったあった。これこれ」
「そ、それって……」
美穂は、取り出した文庫本サイズの薄いその本をマユミに差し出した。「ま、実際そんな事になるわけないけどさ、フィクションだから逆に楽しめるよ。妄想も膨らんじゃうし」
美穂は必要以上にハイテンションになっていた。マユミはその本を躊躇いがちに受け取りながら、それでも鼓動を速くして兄ケンジの水着姿を頭に思い浮かべたりしていた。
ページ上へ戻るすずかけ高校の室内プールは、校地の北の端に位置していた。その建物は二階建てで、一階にある水泳部の部室の横にロッカールーム。その奥に会議室と食堂。二階に25m6コースのプールがあり、奥には事務所と教官室、反対側にミーティングスペースを兼ね備えた、トレーニングマシーンが並べられた広いジムがあった。
クールダウンのために軽く500mを泳いだケンジは、プールから上がるなり、二人の友人に声を掛けられた。
「なんでこの学校に一緒に入学しなかったんだ? ケンジ」色白で痩せた拓志がいきなり言った。
「誰と?」ケンジがキャップを脱ぎながら言った。
「妹のマユミちゃんだよ」
もう一人の小太りの康男がにやにやしながら言った。「マユミちゃん、かわいいよな」
「ふんわりしてそうで、抱き心地いいだろうな」
「いやらしい目で妹を見るな」
「なんだよ、おまえシスコンか?」
「そんなんじゃない」
「俺たちの誰かがマユミちゃんに告白したら、おまえどうする?」
「どうする、って……」
ケンジは思いっきり困った顔をした。
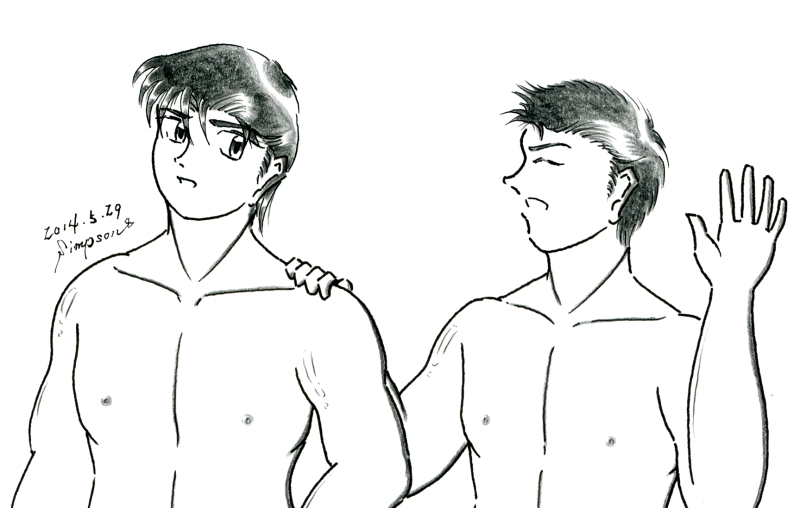
「やっぱ反対するのか? 兄として」
「っつーか、こいつとマユミちゃん双子だろ?」康男がケンジの肩を人差し指で小突いた。「そんなの『兄』って言うのか?」
「どうなんだ? ケンジ」
「ど、どうって?」
「どんな目で見てるんだ? おまえ、マユミちゃんを」
「ふ、双子でも妹だ。それ以上でも以下でもない」
「ふうん」拓志があまり納得していない様子で言った。「そんなもんなんだな」
「でもよ、」康男がにやにやしながら言った。「マユミちゃんと一緒に暮らしてっと、妙な気にならねえか? ケンジ」
「なんだよ、妙な気、って」
「あの巨乳、おまえいつも見てるんだろ? 風呂上がりとか」
「そそられるよな、確かに」拓志もにやにやしながら言った。
「み、見ないよ」ケンジは赤くなって二人から目をそらした。
「思わず触りたくなるよな」
「触っちまったら、絶対そのまま押し倒してやっちまいそうだな」
「マユミちゃんとヤれたら気持ちいいだろうなー」
「いいかげんにしろ!」
ケンジは鋭く二人を睨み付けて恫喝した。
拓志も康男もびっくりして黙り込んだ。
「じょ……冗談だって。ケンジ、本気にするなよ」
「そ、そうだ。単なる妄想だ。気にすんな。ケンジ」
その日の夕食時、いつになく口数少なく、おかずも半分以上残して食卓を立ったマユミの背中をケンジはいぶかしげに見送った。
ケンジは向かいに座った母親に訊いた。「どうかしたの? マユのやつ」
「さあね」母親はそう言って麦茶のコップを手に取った。
「昨日からずっとあんな感じだよね」
「そうね。なに? あんたそんなに心配? 妹が」
横で肉じゃがの人参を箸で持ち上げながら、父親が無言のままちらりと目を上げた。
「べ、別に心配ってわけじゃ……」ケンジは茶碗のごはんを口に掻き込んだ。
「たまには慰めてやったらどうだ? ケンジ」父親が言った。
「そうね、兄妹なんだし」母親も言った。
「ごっそさん」
ケンジは食器を持って立ち上がった。
夕食を済ませた後、ケンジは自分の部屋で宿題を始めたが、なかなか集中できずにペンを置いた。そして小さなため息をついた後、立ち上がり、部屋を出た。
彼は、隣のマユミの部屋のドアをノックした。
「マユ、いるか?」
「あ、ケン兄、どうしたの?」
「開けるぞ」
ドアを開けると女の子特有の甘い香りがケンジの鼻をくすぐった。マユミは机に向かっていた顔を兄に向け直した。
「あ、あのさ、おまえの好きなチョコレートがあるんだ。部屋に来ないか?」
「ほんとに?」マユミは椅子から立ち上がった。しかし、すぐに怪訝な顔をした。「って、どうして?」
「どうして、って……」ケンジは一瞬言葉に詰まった。「いいから、来いよ」
「う、うん」
ケンジの部屋に入ったマユミが躊躇いがちに言った。「あたし、お茶淹れてくる。ケン兄、何がいい?」
「え? あ、ああ、俺コーヒーが……い、いや、マユに合わせる。何でもいい」
「じゃあ紅茶でもいい?」
「ああ。いいぞ」ケンジはぎこちなくもにっこりと笑った。
マユミはドアを出た。
ケンジの部屋のカーペットに座って、二つのカップにティーポットから紅茶を注ぎながらマユミは訊ねた。「ほんとに紅茶で良かった? ケン兄」
「いいよ」
「珍しいね、ケン兄がお茶に誘ってくれるなんて」
「い、いや、チョコレートもらったから。おまえ好きだろ?」
「いいの? 誰からもらったの?」
「友だちだよ」
「女の子?」
ケンジはカップを手に取った。「ま、まあな」
「えー。いいのかな、あたしが食べても」
「遠慮するなよ。俺がもらったんだから。俺がどうしようと勝手だろ」
「でも、偶然だね」
口にカップを運びかけた手を止めて、ケンジが言った。「何が?」
「あたし、このチョコ大好きなんだ。メリーのアソート」
ケンジは少し腰をもぞつかせて、紅茶を一口飲んだ。「そ、そうか。良かったな」

「じゃ、いただきまーす」
マユミはそのアソートのチョコレートに手を伸ばした。
「どれにしようかなー」
マユミのその仕草を見ながらケンジは自分の鼓動が速くなっていくのを感じた。
ケンジは一週間程前、自分の洗濯物をベランダで干している時に、隣の部屋のマユミが着替えをしているのを偶然見てしまった。妹のマユミは気づかなかったようだが、ケンジはその時彼女の白くて柔らかそうな肌に目が釘付けになってしまったのだった。その身体つきは、あのグラビアのモデルによく似ていた。ショートカットで幼さが残る髪、豊かな胸の膨らみ、腰のくびれ……。
双子の兄妹なので、小さい頃から例えば入浴も一緒だった。しかしそれも小学校5年生までで、当時のマユミとは全く別人のような艶っぽい部屋の中のその姿に、ケンジの呼吸は自然と荒くなり、股間も熱を帯びていった。ケンジは焦って部屋に駆け込んだのだった。
「おまえさ、最近元気ないけど、何かあったのか?」
唐突にケンジが言ったので、マユミは、つまみ上げたチョコレートを思わず取り落としてしまった。
「え?」
「明らかに落ち込んでるように見えるけど」
「……」
マユミは落としたチョコレートを箱に戻した。
「ケン兄……心配してくれるんだね」
「そ、そりゃそうだ。当たり前だろ、兄妹なんだから」ケンジは顔を赤くして焦ったように言った。
「そうだね、兄妹だもんね。ごめんね、ありがとう……」
マユミの眼に涙が滲んだ。
「お、俺で良ければさ、話してみろよ。話せばすっきりする事だってあるだろ」
ケンジの優しい声を聴いて、マユミの眼に溜まった涙がぽとりと落ちた。
「マユ……」
マユミは決心したように顔を上げた。「ケン兄」
ケンジはぎこちない微笑みを返した「どうしたんだ?」
「あたし……あたしね、先輩に抱きつかれた……」
「えっ?! だ、抱きつかれた?」
マユミはコクンと頷いた。
「い、いつ?」
「昨日」
「そ、その先輩って?」
「うん。つき合ってた先輩……」
「お、おまえ彼氏がいたのか?」
「彼氏……って言うか……」マユミは言葉を濁した。
「で? 何されたんだ? 抱きつかれただけだったのか?」
ケンジは少し興奮気味にマユミに訊いた。
「メールではよく話してたけど、リアルにはあんまり会ってなかった。先輩部活で忙しい人だから。だから『彼氏』って言う程の関係じゃなかった……ってあたし、思ってた」
「そ、それで、昨日、おまえ……」
「初めて街でデートして、先輩の家に呼ばれて、部屋で……」
マユミは言葉を詰まらせ、唇を噛みしめた。
「ら、乱暴されたのか? ま、まさか、む、無理矢理……」
ケンジは身を乗り出し、顔を赤くして声を荒げた。
マユミは指で涙を拭い、寂しそうに微笑んでケンジを見た。「ううん。服脱がされたりしたわけじゃないんだ。いきなり抱きつかれて、その……」
ケンジは固唾を呑んでマユミの次の言葉を待った。
「む、胸に触られた……」
またマユミの眼から涙がぽろぽろとこぼれた。
「む、胸に……」ケンジはようやくそれだけ言って、腰を浮かせたまま固まった。
彼はうつむいたままのマユミの胸元を見た。ゆったりとした裾の短いTシャツの大きく開いた襟の奥に、ブラに包まれた彼女の大きなバストの谷間がちらりと見えた。ケンジは慌てて目をそらし、自分の胸を手で押さえた。図らずも鼓動は速く大きくなっていて、彼はそれを必死で落ち着かせようと焦った。
しばらく沈黙の時が流れた。
「その先輩にされたのって、それだけ……だったのか? マユ」
「……うん」
「いやだった……んだな」ケンジは紅茶を一口飲んだ。「で、でも良かったな、それだけで済んで」
マユミは顔を上げて、ケンジを睨むような目で見た。
「男のコって、みんなそうなの?」
「えっ?!」
「高校生の男子って、みんなそんな事したい、って思ってるわけ? チャンスがあったら、女のコの身体に触りたいって」
ケンジはまるで自分が責められているような気がして、身体を固くしてうつむいた。
マユミは自分が発した言葉の熱さと鋭さにいささかたじろいで、思わず息を呑み、慌てて続けた。「あっ……、ご、ごめん、ケン兄。あたし、ケン兄を責めてるわけじゃなくて……」
「わ、わかってる」
「あたしの事、心配してくれてるのに、きつい態度だったね……ごめん……」
「無理もないよ。それだけショックだったんだろ? マユ」
「う、うん……」
「初めてのデートでそんな事されたら、やっぱりショックだろうな、女のコは……」
マユミはティーポットからケンジのカップに紅茶をつぎ足した。「ケン兄には、彼女がいるの?」
ケンジは意表を突かれて身体を一瞬小さくびくつかせた。
「つき合ってる子、いるの?」
「い、いないよ」
「ほんとに? だって、ケン兄モテモテなんでしょ?」
「し、知らないよ、そんなの」ケンジは顔を赤らめ、マユミから目をそらした。
「あたしの学校の部活の友だちもみんな言ってるよ、ケンジ君素敵だ、って」
「な、なんでそんな事……」
「それにケン兄、学校でも、もう何人もの女子に告白されてるんでしょ? 噂はあたしの学校まで届いてるよ」
「な、何人ものって……お、大げさだよ」
事実、ケンジは所属している部活のみならず、他のクラス、他の学年の女子生徒からもほぼ毎月のように告白まがいの行為を受けていた。
「いるの? 彼女」
「い、いないってば」
「じゃあさ、どうなの? もし彼女ができたら、一刻も早く抱いたりキスしたいって思ったりする?」
「い、一刻も早くって……」ケンジは思いきり困ったように顔を歪めた。「そ、そりゃあ、俺だってオトコだし、そんな気になるかも……知れないけど」
「やっぱり?」
マユミが少しがっかりしたように肩を落としたのを見て、ケンジは慌てて付け加えた。「で、でも、俺は相手の気持ちを確かめずに、そんな事しないぞ」
「ほんとに?」
「だ、だって、そんな事したら、いっぺんに嫌われちまうじゃないか」
「そんな冷静な判断ができるの?」
「た、確かにその時になったら、どんな行動に出るか……わからないけど……、でももしやっちまった、って思ったら、俺ならきっと速攻で謝る」
顔を真っ赤にして、必死で訴えるように真剣な顔をしている目の前のその兄を見て、マユミはほっとしたように小さなため息をつき、柔らかく微笑んだ。
「ケン兄優しいからね。きっとそうだね」そしてカップを口に運んだ。
「その先輩とは、別れたのか?」
「うん。もう会わないってメールした」
「で、そいつは諦めたのか? おまえを」
「それからメールもこないし、学校ですれ違っても何もない」
「そうか……」ケンジも冷めてぬるくなった紅茶を口にした。
「しばらくは、そんな時ちらっとあたしを見て、申し訳なさそうな顔をして目をそらしてた」
「後悔してるんだな、そいつも。きっと突っ走り過ぎた、って思ってるんじゃないか?」
「そうだね。たぶん……」
「だけど、謝って、またつき合い続けたい、って言ってきたわけじゃないんだな」
「そこまであたしの事、思ってくれてたわけじゃなかったんだよ、きっと。先輩もあたしの事を彼女だってあんまり意識してなかったんじゃないかな」
ケンジは肩をすくめた。「なるほどな……」
「ごちそうさま。ケン兄、ありがとうね」
マユミはすっきりした顔でにっこり笑うと、カップをトレイに戻した。「何だか気が晴れた。こんな話聞いてくれる男子って、考えてみればケン兄しかいないね。ほんとにありがと」
「気にするな」ケンジも少しこわばったような微笑みを返した。
「やっぱりさ、つき合うにしても、まずこうやって直接いっぱい話さなきゃだめだね。メールなんかじゃだめだよ、うん」
マユミは自分を納得させるように言ってトレイに手を掛けた。
「ま、また何かもらったりしたら誘うから」
「嬉しい。期待してる」マユミはウィンクをした。
ケンジはどきりとした。そしてますます目の前の、そのある意味無防備な態度の妹に対する想いの温度が上がっていく感じがした。
「じゃあ片付けるね」
「いや、俺が片付けるよ」
「あたしがやらなきゃ。ごちそうになったんだもの」
「おまえ勉強の途中だろ。俺に任せろ。時々こういう事をしとけば母さんに好印象だろ」
マユミは笑った。「そういう事かー。じゃあ、お願い」
マユミと一緒に立ち上がって、ケンジは彼女を隣の部屋まで送った。マユミの身体からほんのりとバニラの香りがした。そしてほのかな彼女の体温を感じてケンジはまた鼓動を速くした。
「ケン兄が彼氏だったら、素敵だろうな」
マユミは屈託のない笑顔でそう言って部屋の中に消えた。
部屋に戻ったケンジは、マユミが座っていた所に彼女の小さなハンカチが置き忘れてあるのに気づいた。彼はそれを恐る恐る手にとって、自分の鼻に近づけた。やっぱりバニラの香りがした。妹が座っていた場所に同じように座ってみた。彼女の温かさがまだ少し残っていた。そして妹が使ったカップを手に取った。彼女が口をつけたカップの縁にそっと自分の唇を押し当てた。ケンジの鼓動はますます速く、強くなっていった。

その夜、ベッドで寝ていたマユミは、かすかな物音と人の声に気づいて目を開けた。それは隣のケンジの部屋から壁越しに聞こえてくる。「ケン兄、こんな夜中に何してるのかな……」
マユミは耳を澄ました。ベッドが軋む音とケンジの小さな声。小さな声で「マユ」と呟いているようにも聞こえる。
「えっ? あたし?」
マユミそっとベッドから起き上がり、音を立てないようにベランダに出てケンジの部屋の中を窺った。
「なに? ケン兄、具合でも悪いのかな……」
ベッド脇の小さなライトだけが灯っていた。その黄色い光の中でケンジはベッドにうつ伏せになって、両腕できつく抱きしめた枕に鼻と口をこすりつけながら喘いでいる。荒い息で彼は時折、確かに「マユ」と呟いている。目を凝らしてよく見ると、彼が鼻と口をこすりつけているのは、自分がケンジの部屋に置き忘れたらしいハンカチだった。やがて兄の腰が上下に激しく動き始め、掛かっていた薄いタオルケットがベッドから滑り落ちた。彼は黒の下着一枚という姿だった。それを見たマユミは焦ったように部屋に戻った。彼女の胸の鼓動は大きく、速くなっていた。
◆
8月1日。火曜日。
その日、県下の高校水泳部が集まる競泳の大会が開催された。
マユミの学校の女子部員は、男子バタフライのプログラムが始まると、こぞって観覧席の最前列に陣取り、スタート台に立つケンジに熱い視線を送ってきゃーきゃー騒ぎ合った。マネージャのマユミは、自分のチームの男子選手の記録を取るべく、プールサイドにストップウォッチを手に立っていたが、下からそのいつもの光景を見て、困ったような、それでも少し誇らしいような気持ちになっていた。
「もう……恥ずかしいったら……」
マユミは小さく独り言を言って、ため息をついた。
スタートのアラームが場内に鳴り響いて、選手は一斉に水に飛び込んだ。
最初のバサロですでにケンジは他の選手を圧倒していた。彼が頭を出した時には、もう半身以上の差をつけ、そのまま100m安定した泳ぎでトップを維持し、余裕でゴールした。
そんな接戦でもないレース展開にも関わらず、観覧席からは黄色い声がのべつ送られていた。ケンジを目で追う女子たちである。レースが終わって観覧席を見上げたマユミは、自分の学校の生徒だけでなく、他の学校からもたくさんの女子生徒がケンジの一着ゴールに大騒ぎしている姿を目の当たりにした。
学校の部員たちの荷物を並べ直していたマユミの背後から声がした。
「今日も凄かったよね、マユミ」
そして駆け寄ってきた美穂がマユミの背中をばしばし叩きながら興奮したように飛び跳ねた。
「ちょ、ちょっと、痛いんだけど、美穂」マユミは遠慮なく迷惑そうな顔をして、美穂の腕を払いのけた。
美穂は構わず言った。「もう、最高じゃん、ケンジ君。あたしコクろうかな、真剣」
「な、なんでケン兄がそんなに……」
横から別の部員が言った。「だってそうじゃない、最高のイケメンだし、身体つきもかっこいいし」
「そうそう」美穂だった。「他の男に比べて、ごりごりのマッチョでもないし、バランスいいよね」
「それにさ、あたし会場の入り口でおばあちゃんの荷物持ってあげてるケンジ君、見たよ」
「あたしも、」違う部員が首を突っ込んできた。「ゴーグル落として気づかないで歩いてたよその男子生徒に、それを拾って手渡してた」
「誰でもするよ、そんな事」マユミが恥ずかしげに言った。
「違うって、その時ケンジ君、ちゃんと両手で差し出して、にこにこしながら『お疲れ、次のレースもがんばって』って言ってた」
「すごいよね、敵のしかも男子なのに、そんな言葉かけができるんだから」
「親切だけど媚びないし、優勝しても威張らないし、」
「そうそう、メダル掛けてもらう時の、少し赤くなってはにかんだような顔と態度、もうめちゃめちゃ胸キュンだよー!」
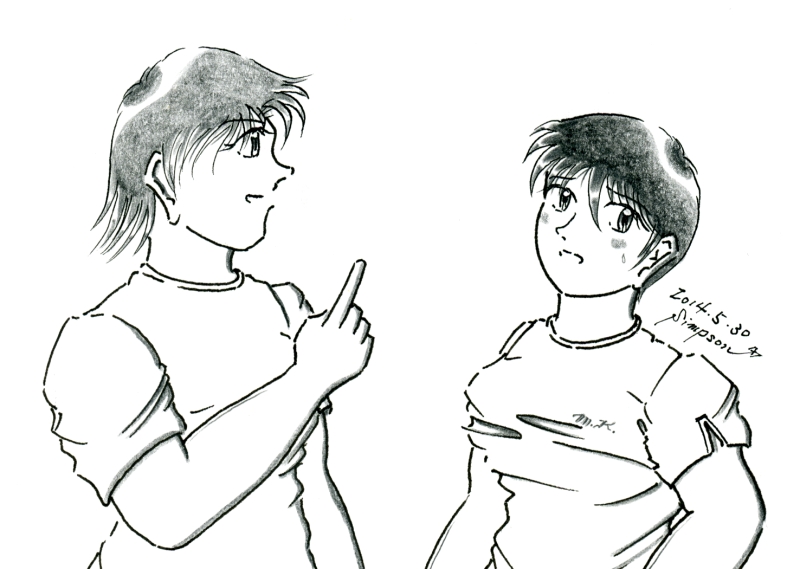
マユミはそう言って騒ぐ部員たちを見ながら、自分の双子の兄が女のコに人気がある理由が今さらながらわかったような気がした。
美穂がにこにこ笑いながら言った。「マユミ、」
「え? なに?」
「あんた本当に幸せだね、あんな男のコと一つ屋根の下で暮らせるなんて」
「な、何言ってるんだよ。兄妹だから当然でしょ」
美穂は心底羨ましそうに言った。「贅沢だよ。あたしたちが簡単にできない事、あんたにはできるんだから」
「か、簡単にできない事?」
「一緒に話したり食事したり、プレゼントあげたり……」
「あたしケン兄にプレゼントなんかした事ないよ」
「それ以上の事、できるじゃん。それにもし、あんたがその気になればハグしてもらったりキスしてもらったりもできるんじゃない?」
美穂は悪戯っぽく笑った。
「無理無理無理!」マユミは耳まで真っ赤になって大声を出した。
美穂はにわかに声を落とし、冷静に抑揚を抑えた口調で言った。
「何よ、わかってるよ、そんな事。兄妹なんだから、あんたとケンジ君。冗談だから。そんな力一杯否定すると、まるであんたがケンジ君に気があるのかも、って勘違いしちゃうでしょ」
マユミは顔を赤くしてまま黙り込んだ。
「ケンジ君だったらアキラ先輩みたいに野獣にはならないね、きっと」
「えっ?!」
「そう思うでしょ? マユミも」
「そ、そうだね……確かに。あの人優しいし……」
「やっぱり優しいんだ」美穂は目を輝かせた。「妹のあんたにも優しいんだったら間違いないよね。あたし本気でコクっちゃお、今度」
「え、あ、あの、美穂、で、でもケン兄優柔不断だし、優しいって言っても、そ、その、単に臆病なだけ……だから」
「いいんだ、それでも」
美穂は指を組んでうっとりしたように上目遣いで中空を見た。「彼は絶対、オトコの中の残り1㌫だよ。ユカリが言ってた通り」
マユミは、そんな美穂の様子をちょっと疎ましげに見やった。
「そうそう、マユミ、」
「な、なに?」
「あたしさ、兄妹で愛し合うっていう本、持ってるよ。貸してあげる」
そう言いながら美穂は自分のエナメルバッグを漁り始めた。
「ええっ? な、何それ!」
「ライトノベルなんだけど、『兄貴に胸キュン!』っていうの。兄妹で一線を越えちゃう、っていう話。なかなか面白くてどきどきしちゃうよ。あったあった。これこれ」
「そ、それって……」
美穂は、取り出した文庫本サイズの薄いその本をマユミに差し出した。「ま、実際そんな事になるわけないけどさ、フィクションだから逆に楽しめるよ。妄想も膨らんじゃうし」
美穂は必要以上にハイテンションになっていた。マユミはその本を躊躇いがちに受け取りながら、それでも鼓動を速くして兄ケンジの水着姿を頭に思い浮かべたりしていた。
感想を書く
この話の感想を書きましょう!
全て感想を見る:感想一覧
